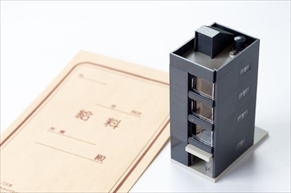生活保護を受けるときの家賃上限は?住宅扶助ってなに?
生活保護では一定額の家賃補助(住宅扶助)を受けることができる

生活保護とは、国民に憲法25条の規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度である。病気や怪我など、さまざまな事情で暮らしに困窮している人に、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるように援助することを目的としている。
しかし、生活保護の受給金額には一定のルールが設けられているため、無制限に支給されるわけではない。
生活保護の保障には、生活や教育をはじめさまざまな扶助があり、住まいの確保も「住宅扶助」として対象の1つになっている。
このページの目次
住宅扶助制度とは

生活保護を受給できるようになると、定められた額の範囲で家賃分の金額が住宅扶助として支給される。
住宅扶助(家賃補助)の上限は地域・世帯数によって異なる
住宅扶助の上限額は、日本全国を等級地別にして定められている。また、世帯数によっても上限額は異なる。
なお、単身世帯の場合、床面積でも限度額が変わってくるので注意が必要だ。
東京と大阪の住宅扶助の限度額
住宅扶助の限度額には都市ごとにかなりの差がある。 すべてを紹介するのは難しいので、参考までに東京と大阪の住宅扶助の限度額を見てみよう。
| 都内23区と1級地24市 (羽村市・あきる野市を除く) | 大阪市 | |
|---|---|---|
| 単身世帯(15㎡以上) | 53,000円 | 40,000円 |
| 2人世帯 | 64,000円 | 48,000円 |
| 3人世帯 | 69,800円 | 52,000円(3〜5人世帯) |
この数字が基準で算出されるが、以下の注意点があるので確認しておこう。
住宅扶助(家賃補助)の3つの注意点
住宅扶助の注意点①:住宅扶助の限度額は自治体によって異なる
家賃や間代(間借りする場合の家賃)に充てる住宅扶助は、世帯人数によって定められた金額が支給されるが、住宅扶助の限度額は自治体によってそれぞれ異なる。たとえば、東京都は市区町村によって等級が決められており、同じ東京都内でも2級地-1である特定市(羽村市・あきる野市)や3級地-1の島しょ部では都市部よりも低い金額に設定されている。
東京都の1級地に住む一人世帯の限度額は53,700円だが、2級地では45,000円、3級地になると40,900円に下がってしまう。また、このような限度額の差は都内だけに限らない。全国でも市町村ごとに違いがあるので、自分の住む街の限度額が知りたい場合は役所に問合せてみよう。
住宅扶助の注意点②:場合によっては「特別基準」の住宅扶助
母子家庭や障害、病気などで特定の病院の近くに住む必要があるといった場合には、特別加算分が計上される場合もある。
市区町村によって住宅扶助の限度額は決められているが、世帯の状況や住んでいる地域の住宅事情によって特別基準が適応されることがある。特別加算分は、「生活保護法による保護の実施要領について」に明記されている。
たとえば東京都の1級地に住む一人世帯の場合、特別基準の限度額は69,800円であり、2級地は59,000円、3級地では53,200円となっている。特別基準についても市町村で異なるため、こちらも一度確認してみよう。
住宅扶助の注意点③:住宅扶助は金額や制度の見直しが行われることがある
平成27年に厚生労働省は、「社会保障審議会生活保護基準部会」の検証を元に生活保護の基準の見直しを実施している。その結果、横浜市ではほとんどの世帯人数で一般基準上限額の引き下げが行われることになった。
世帯数一人の場合、一般基準上限額を現行の53,700円から52000円に、2人世帯では69,800円から62,000円に引き下げている。しかし、車椅子使用者や高齢者などが広い住居を必要とする場合の基準額は引き上げている。このように、住宅扶助は定期的に見直しが行われているため、最新の情報を確認することが重要だ。
家賃補助の対象範囲は決められている

住まいに関わる支出であっても、住宅扶助(家賃補助)の対象外となる項目がある。 家賃補助の対象となるものと、ならないものについて細かく解説していこう。
家賃補助の対象となるもの
月々の家賃に加えて敷金や礼金、契約更新料や住居維持費などは住宅扶助の対象となる。
敷金や礼金は転居の際に必要になるため、「一時扶助金」として受け取ることができる。場合によっては、引越し費用や仲介手数料・火災保険料なども補助の対象になる。
ただし、これらの費用については、あらかじめ決められた一時扶助金の範囲内に収めなければならないので注意が必要だ。
家賃補助の対象とならないもの
管理費や共益費、水道光熱費などは住宅扶助の対象とならないため、「生活扶助」から補う必要がある。
生活保護を受給している場合は、管理費や共益費まで含めた金額を念頭に物件を探すか、管理費や共益費が家賃に含まれている物件を探すのがよいだろう。
ここからは、住宅扶助(家賃補助)を受けるまでの流れを解説していく。
住宅扶助(家賃補助)を受けるまでの流れ
住宅扶助を受けるまでの流れをまとめてみた。
住宅扶助を活用して物件を借りる際は、下記のような流れで進めていく。
- 不動産会社に初期費用の見積もりを依頼する
- 見積もりをケースワーカー(生活保護窓口の担当者)に確認し、了承を得る。
- 初期費用をケースワーカーに用意してもらう手続きを進めてもらい、賃貸契約を交わすスケジュールを決める。
- 初期費用をケースワーカーから受け取り、不動産会社で契約を完了させ、支払いを済ませる
- 賃貸契約書と、初期費用を支払った領収書をケースワーカーに提出する
住宅扶助を受けるにあたり、注意したい点がある。
生活保護を受給している場合は物件を借りる際、扶助の中で家賃が収まるかどうか慎重に確かめる必要がある。
また、ケースワーカーとのやり取りにも時間がかかるため、余裕を持って行動することが大切だ。
生活保護を受けている場合、賃貸物件を借りるのはハードルが高い

生活保護を受けている人が賃貸物件を借りようとすると、以下のようなトラブルが生じることがある。
- 取り扱う不動産会社がなかなか見つからない
- 大家さんから支払い面で懸念される場合がある
- 担当のケースワーカーから許可が出ない
- 保証人がつけられない、保証会社の審査が厳しい
これらを解決しないと、賃貸物件を借りることが難しい。
どのようなハードルがあるのか確認し、自治体のケースワーカーに相談をしてきちんと対策していこう。
生活保護を受けている場合の保証会社の審査
生活保護を受けていると、家賃保証会社から厳しい目で見られることが多い。
しかし、以下のポイントを押さえておけば審査に通りやすくなるので、事前にチェックしておこう。
保証会社の審査に通るコツ①:代理納付
代理納付を活用すると、保証会社の審査に通りやすくなる。代理納付とは、生活保護を受給する人に代わって、福祉事務所が大家さんに住宅扶助費を支払う制度だ。
平成18年に定められ、平成26年に改正された「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」に、代理納付に関する記載がある。代理納付であれば滞納などの家賃トラブルのリスクを回避できるため、保証会社の審査に通りやすくなるのだ。
保証会社の審査に通るコツ②:生活保護受給者の審査に慣れている業者を選ぶ
生活保護受給者の審査に通るためには、業者を選びも重要だ。保証人がいない、生活保護を受けているなど、賃貸を借りるハードルが高い人向けの業者がある。ケースワーカーに相談して、生活保護受給者でも通りやすい業者を探そう。
生活保護受給者OKの賃貸物件を探すには?

ここまでの解説で、生活保護を受けている場合の賃貸物件探しは、かなり難易度が高いことがわかる。しかし、きちんとした住まいを探しておかないと、今後の生活に響いてくる。
ここからは、希望の賃貸物件を探す手順について解説していく。
生活保護者OKの賃貸物件を探す方法①:仲介経験のある会社を探す
インターネットを使い、生活保護受給者に強い不動産会社を検索することも有効だ。 またケースワーカーに相談して、ほかの生活保護受給者がどうやって部屋探しをしたのか聞いてみるのもいいだろう。
さらに、気になる物件を仲介している不動産仲介業者に電話で確認をするという方法もある。時間がかかるが、地元の業者を地道に訪ねてみてほしい。
生活保護者OKの賃貸物件を探す方法②:大手の不動産会社へ相談する
地元の小さい不動産会社の方が、生活保護を受けている場合でも対応をしてもらいやすいように感じるかもしれないが、来店客数の多い大手の不動産会社はの方が多くの事例を扱っており、親身になって対応してくれる場合が多い。
まずは、大手の不動産会社に「生活保護を受けている」と伝えて物件を紹介してくれるかどうか相談してみよう。 生活保護に関する知識が豊富な担当者が対応してくれるケースも多いので、物件探しの相談にも親身になって乗ってくれるだろう。
生活保護者OKの賃貸物件を探す方法③:物件検索サイトで「生活保護」と入力する
物件検索サイトで検索するときに、「生活保護」を条件に入れて検索してみよう。生活保護受給者OKの物件や相談可能の物件が登録されていると、検索結果に出てくる。
また、「高齢者」「外国人」「保証人不要」などの項目にチェックして検索するのもおすすめだ。柔軟な対応を受け入れている物件だと、生活保護受給者でも入居できる可能性が高くなる。
住宅扶助を受けるには、まずは地域の上限額を確認!
今回は生活保護を受けるときの家賃の上限額と、住宅扶助制度について紹介した。住宅扶助の限度額や特別加算分は地域や世帯人数によって異なるため、自分が住んでいる自治体に問い合わせて最新の情報を得るようにしよう。
生活保護を受けている場合、賃貸物件を借りるのに不安がある人もいるはずだ。ケースワーカーに相談したり、不動産会社に尋ねたりするなど、プロの力を借りながら希望の物件を探していこう。
▼賃貸物件の家賃が安い時期について知りたい人はこちら!