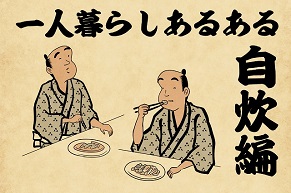【二人暮らしのインテリア】インテリアコーディネーター直伝!部屋作りのダンドリとポイント
「二人暮らしの部屋作りを成功させるためのダンドリ」と「注意したい7つのポイント」

同棲の新居でこだわりたいのがインテリア。住み始めてから後悔しないよう、計画的に部屋作りを進めていきたいもの。二人らしい空間をつくるためには、どんなことに気を付ければいいのだろう?
今回は、インテリアコーディネーターの山口恵実さんに、「二人暮らしの部屋作りを成功させるためのダンドリ」と「注意したい7つのポイント」を教わる。
「理想的な部屋をつくるためには、まず『自分たちがどんな過ごし方をしたいか』を考えることが大切。それによって求める部屋や家具が変わります。部屋づくりは物件探しの前から始まっているのです」(山口さん)
二人暮らしのインテリア 完成までの流れ
まずは二人暮らしのインテリアが完成するまでの、理想的な流れを紹介しよう。
「部屋が決まってからインテリアを考えよう」という人が多いかもしれないが、山口さんいわく、イメージ通りのインテリアを実現するにはそれだと遅いのだそう。できれば、部屋を探す1ヵ月前には、二人でライフスタイルの相談を始めたい。
1. ライフスタイルを相談
「二人でどんな過ごし方をしたいか」「インテリアのテイスト」などを話し合う。実例写真を見て想像を膨らませよう。
2. 家具の優先順位を決める
ライフスタイルのイメージに合わせて、新居に必ず置きたい家具、できれば置きたい家具など、優先順位を決めよう。
3. 物件探し
部屋の広さや間取りを確認。空間をどのように使うか、置きたい家具が置けるか、寸法をチェックしながら内見しよう。
4. 間取り図で家具の配置をチェック
物件を決定する前に、間取り図を使って置きたい家具が無理なく配置できるかをチェック。
5. 家具の選定
物件の広さや間取りをふまえて家具を購入。あわせて新居に持って行く家具、捨てる家具を決める。
6. 引越し
ベッドやテーブルなど暮らしにマストな家具は、引越し時までに届くように手配しておこう。
7. 小物集め
小物類は引越し作業が落ち着いてから少しずつそろえていけばOK。実際に暮らしながら、必要なアイテムを検討しよう。
失敗しない!二人暮らしで理想の部屋をつくる7つのポイント
「置きたい家具が置けない」「イメージした空間と違う」という失敗は避けたいところ。部屋作りを成功させるために次の7つのポイントを意識しよう!

1. 内見にはメジャーを持って行く
事前に新居に置きたい家具を決め、だいたいの寸法を調べておく(3人掛けのソファを置きたい等)。内見時には置きたい家具がきちんと置けるかをメジャーでチェック。
2. 間取り図で家具配置&動線チェック
内見時に測った寸法をもとに間取り図で家具配置をチェック。切った付箋を家具に見立て、レイアウトを検討しよう。「動線が悪い」「家具が多すぎる」等の問題点に気付くことも。
3. 人が通る場所は幅を60cm確保
行き来が多いキッチンやダイニングは特に動線を意識したい。人がスムーズに通るためには幅60cmを確保できることが理想的。それ以下だと動きにくくなってしまうので注意。
4. お金をかける家具、かけない家具を決める
インテリアで重視する点を決め、予算をかける家具にメリハリをつけよう。たとえば食を楽しみたい人はダイニングテーブルにこだわるなど。手持ちの家具で十分な場合は引き続き活用を。
5. 色数は3色にしぼる
インテリアがごちゃついた印象になる理由の一つは色数の多さ。家具の色は3色以内にまとめ、ベースの色とアクセントカラーを決めることが空間に統一感を出すコツ。
6. 大きな家具はニュートラルな色を選ぶ
頻繁な買い換えが難しいソファやテーブル、棚などの大きな家具はシンプルな色&デザインを選ぶのがポイント。将来的にインテリアの好みが変わっても長く使うことができる。
7. クッションやアートで空間を飾る
家具をシンプルにした分、ソファにクッションをたくさん置いたり、アートを飾ったりなど、小物で空間を飾ってみよう。小物なら入れ替えやすく、模様替えも気軽にできる。
二人暮らしのインテリアは、理想のイメージを共有するところから始まる
二人とも納得のいく部屋をつくるためには、部屋探しの前に理想の部屋のイメージを共有することが大事だとわかった。
「イメージの共有には実例写真が役立ちます。『北欧風』と言ってもいろいろなテイストがあります。インテリアショップの展示を見たり、雑誌やウェブなどで実例写真を見たりしてお互いのイメージを共有していくと、スムーズに部屋づくりを進められるはずです!」(山口さん)
二人暮らしを始める時の部屋作りは、初めての共同作業になることも。「将来どんな暮らしをしたいのか」をよく話し合い、楽しみながら進めよう!
文=村上佳代
イラスト=イチカワエリ
※雑誌「CHINTAI」2018年6月号の記事をWEB用に再編集し掲載しています