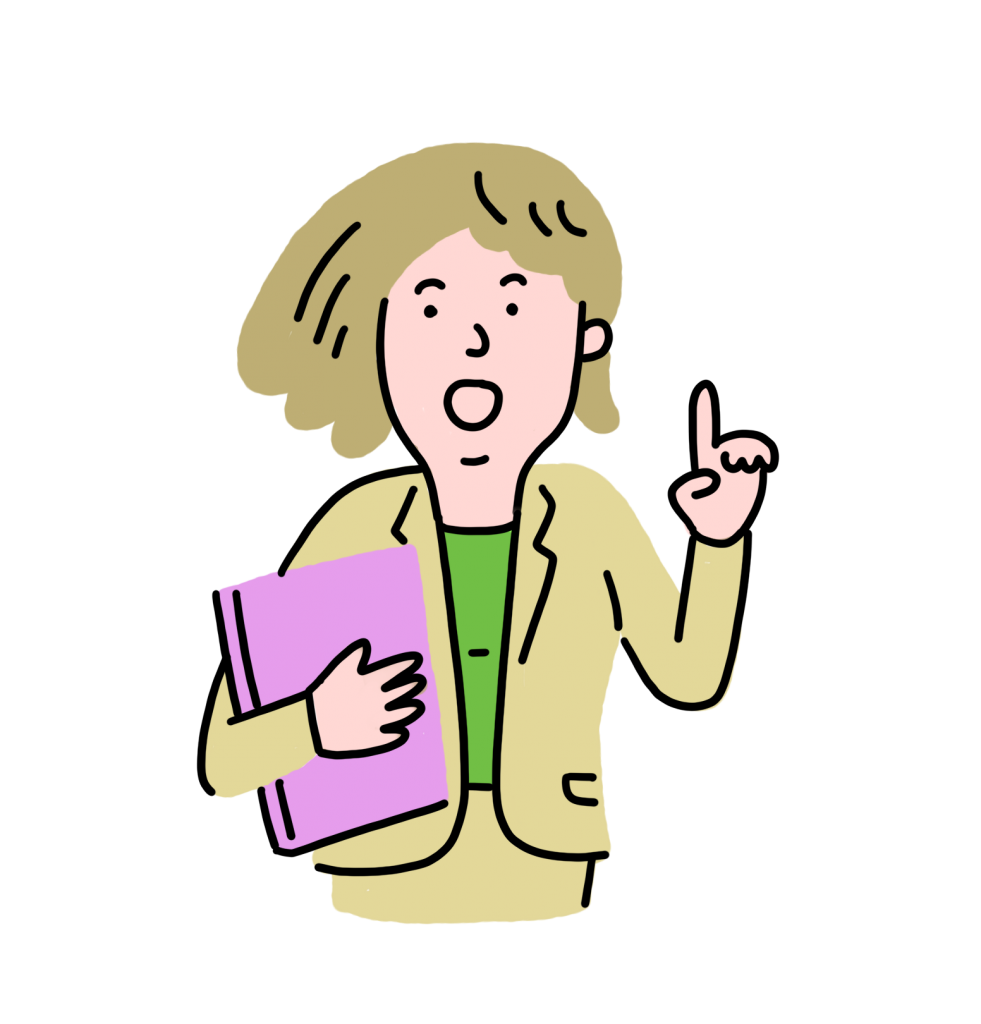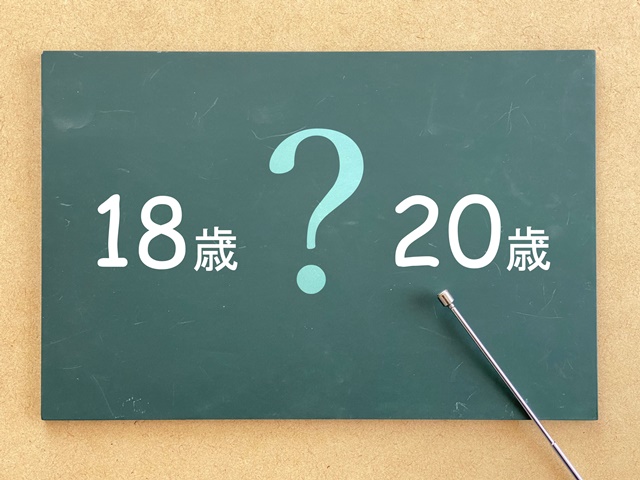
【弁護士が解説】成年年齢(成人年齢)が18歳に引き下げ!生活にはどんな影響がある?
弁護士さんが成年年齢(成人年齢)引き下げをわかりやすく解説!
2018年に民法が改正され、2022年4月から「18歳以上が成人」となった。この変更は私たちの生活にどんな影響を及ぼすのだろうか。
大江橋法律事務所の弁護士・和田祐以子先生によると、注目すべきは「契約」に関わるリスクだという。18歳になると、親権者などの同意がなくてもさまざまな契約ができるようになる。一人でできることが増えるということは、思わぬトラブルにあうリスクも高くなってしまうということだ。
今回は法律のプロフェッショナルである弁護士さんに解説をいただき、新たに「成年(成人)」となる方に向け、注意すべきポイントをまとめてみた。
このページの目次
成年年齢(成人年齢)の引き下げとは?
「20歳になったら大人」といった常識は今や過去のもの。2022年4月からは成年年齢が引き下げられ、さまざまな場面で「18歳から大人」という扱いになった。
和田先生によると、政治・法律の世界では、何年も議論を重ねて取り組みが進められてきたとのこと。
2007年に国民投票法が制定、2015年に公職選挙法が改正されるなど、国の政治に関する重要な判断について「18歳~19歳も大人として扱う」政策が進められてきました。憲法改正国民投票の投票権や選挙権を持つ年齢が18歳と定められ、民法についても成年の年齢を18歳以上にすべきではないか、という議論が進みました。
世界的に見ても、アメリカの多くの州、ヨーロッパでもイギリス・フランス・ドイツ、アジアでも中国など、多くの国で18歳以上を成年としています。今回の成年年齢の引き下げは、世界の主流に合わせるという意味合いもあります。
成年年齢(成人年齢)引き下げの内容(何ができる? 何ができない?)
まずは、今回の成年年齢引き下げによって18歳からでもできるようになったこと、以前と変わらず20歳にならなければできないことを整理してみよう。
| 18歳からできること | 20歳にならなければできないこと |
|---|---|
| ・親権者の同意なしでの契約行為 ・10年有効のパスポート取得 ・国家資格取得 (公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許など) ・性同一性障害の方が性別取り扱いの変更審判を受ける ※結婚 (女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に) ※選挙への投票、普通自動車免許の取得 (これまでと変わらず、18歳から可能) | ・飲酒 ・喫煙 ・競馬、競輪、オートレースなどのギャンブル ・養子を迎える ・大型・中型自動車運転免許の取得 |
民法では成年年齢に2つの意味があります。1つは「父母などの親権に服さなくなる年齢」。親権とは、親などの大人が子供の利益のために教育などを行ったり、財産を管理したりする権限のことです。成年になったら、この親権に服さなくなるのです。
もう1つの意味は「一人で有効な契約をすることができる年齢」です。親の同意を得ることなく1人で有効な契約ができるようになります。
未成年がスマートフォンを購入したり、クレジットカードの契約を結んだりする際は、原則として親権者の同意が必要だ。
そして、民法では「未成年者取消権」が定められている。これは、未成年が親の同意を得ずして契約を結んだ場合、その契約は取り消すことができるという権利。
契約について未成年は「守られるべき存在」なのだ。
未成年者取消権は、社会的な経験の少ない未成年がトラブルに遭うことを防ぐためのもの。成年年齢の引き下げによって、18歳以上であれば親などの同意を得なくても契約が締結できるようになります。
だからこそ、若いみなさんには「契約」について意識を高め、対処するための知識を持ってほしいと思います。
18歳になると、一人で「契約」ができる
成年になると、民法上は親などの同意がなくとも契約ができる。契約といえば「書類に印鑑を押して取り交わすもの」……といったイメージが強いが、そもそも「契約」とは何だろうか? あらためて和田先生に教えていただこう。
確かに、契約書に署名押印すること=契約と思われている方も多いかも知れませんね。民法の定義で言うと、一方から申し込みの意思表示があり、もう一方がそれを承諾する意思表示を示すと、それが契約の締結になります。ここは一般的な感覚とのギャップがあるところかもしれません。
契約書を取り交わさなくても、双方が合意していたら契約になる。つまり、どこかに書き記していなくとも「口約束」でも契約は成立するのだ。
私たちがお店で商品を購入するのは売買契約、スマホでゲームに課金するのもサービスの購入契約だ。日常的にやり取りしている行為の多くが「契約行為」なのである。
LINEやDMでも起こる!? 契約を巡るトラブル
契約によって発生する行為や対価が自分にとってメリットがあるものか、重大な被害につながるリスクがないか、きちんと確認しましょう。社会経験が少ない場合、正しく判断しにくいことがあるかもしれません。18歳になったばかりの方は、その点で注意したいところです。
和田先生によると、契約トラブルの多くは「自分が意図していないところで契約が締結されてしまった」ケースだという。
たとえば部屋を借りたり、お金を借りたりする際は、ほとんどの場合契約書や借用書を取り交わすため、「契約」に慎重に向き合う場面を設けやすい。提示された書類をチェックし、本当に契約していいものかどうかを真剣に考えるだろう。
ところが、それがLINEなどSNSのダイレクトメッセージだったらどうだろうか?
実際にあった相談例で、SNSのメッセージをよく確認しないまま返信してしまったことにより、実際には払わなくてもよいお金を払うことになっていた、というケースもありました。
「お金を貸した」「キャンセル料が生じる」などのメッセージにその場しのぎで肯定するような返信をすると、それが「消費貸借契約」などとみなされ、支払い義務が生じてしまうケースがあるという。
このように、相手が友人や先輩である場合など、何気ないレスでも「はい」と答えれば契約締結とみなされる――カジュアルにメッセージをやり取りする中でも、常にそんな意識を持っておいてほしいですね。
気軽にコミュニケーションが取れる時代だからこそ、気を付けておきたいポイントといえそうだ。
契約で失敗しないために、注意すべきポイント
1.契約を結ぶ前に気をつけること
契約を締結するにあたっては、契約に伴って何らかの権利・義務が発生することを意識しておいてほしいですね。その場の空気に流されて、何となく契約を結ぶのはやめましょう!
ほしい商品を購入できたり、自分名義で部屋に住むことができたり、契約ではメリット面に気を取られがちだが、和田先生が強調するのは「それはどんな契約なのか?」「その契約によって自分にはどんな権利、義務が発生するのか」への意識を持つことだ。
契約書や資料があったら、流し読みはしてはいけない。わからないことがあったら質問し、ポイントを押さえて読むようにしよう。
2.契約書ってどこを読んだらいいの?
契約書を読む際に押さえておくべきポイントとは? 和田先生は「契約書はボリュームがあって、細かく書かれているもの。強弱をつけて読んでいきましょう」とアドバイスをくれた。
和田先生によると、特に注意してチェックすべきポイントは下記のとおりだという。
- 契約対象(何について契約をするのか)
- 商品やサービスの金額
- 支払い回数、支払期間
- 解約に関すること
最もチェックすべきは契約対象です。何について契約をするのか、ということですね。契約書では前半部分に書いてあることが多くなっています。
解約に関しては、解約できる期間はどれぐらいで、解約に伴って違約金などは発生するのか、どんな場合に解約できるのかといった細かいことが定められています。契約書では後半に書かれていることが多く、「解除」という項目が立てられていることが多いですね。
サブスクリプションのサービスのように、解約しない限りは定期的に支払いが発生し続けるものもある。特にスマホ画面などネットで契約する場合はクリックで次々に契約手続きが進んでしまい、締結されてしまうパターンもある。ここでも和田先生は「契約するという意識を持っていてほしい」と強調する。
パソコン、スマホ経由だとクリック、画面タッチでさくさくと進んでしまうものもあるでしょう。だけど、それも一つの契約である、という意識を持っていただくことが大事です。ネット上の場合、契約書面をスクロールすることになるので流し読み、読み飛ばししてしまうことがあるかもしれません。
紙の契約書が発行されない場合、画面のデータを保存しておくといった対策も考えておきましょう。
3.望まない契約を結んだ場合はどうしたらいい?
契約を結ぶまでの注意点をガイドしていただいた。では、その気がないのに「意図しない契約」を結んでしまったら、どうしたらいいのだろうか。
まず、契約した相手に対して「契約をキャンセルしたい」という意思を伝えることです。これは早ければ早いほどいいですね。解約金が定められていない場合、スムーズに解約できることもあります。
契約後でも解約できる「クーリングオフ」という制度も知られている。この制度を使えば、契約後でも何とかなるのでは、と考える人もいるだろう。
クーリングオフで無条件に解約できる契約には細かい定めがあり、すべての契約で使える制度ではありません。ケースバイケースだと考えておいてください。
ただ、自分が締結した契約でクーリングオフが利用できるのではないか、という視点を持っていただくことは有効かもしれませんね。
もちろん、密室などで契約書の締結を強要されたり、「この価格で購入できるのは今だけ」などのセールストークで、冷静な判断ができないようにして契約をさせる手口もある。
身の危険を感じる場面に遭った際は、まずは身の安全を確保しよう。その後一人で抱え込まず、警察やこの後紹介する消費生活センターなどに相談してほしい。
契約トラブルで困った際の相談先
「契約を解消したい」と速やかに相手に伝えても、スムーズに解約できないこともあるだろう。トラブルになりそうなケースでは、どうしたらいいのだろうか。
消費者がトラブル、困りごとについて相談できる窓口として、自治体には消費生活相談窓口、消費生活センターがあります。
最寄りの窓口がわからない場合は、消費者庁が設置している「消費者ホットライン」、188という電話番号にかけて相談してみましょう。最寄りの消費者生活窓口を案内してもらうことができます。
参考:消費者庁ウェブサイト「消費者ホットライン」188
契約のトラブルにあったら、法律のプロである弁護士に相談するという手段もある。弁護士への相談は高額な印象もあるが、和田先生によると意外にリーズナブルな料金で相談もできるそうだ。
さまざまな地域の弁護士会で、収入が少ない方向けに低額の法律相談を設けています。近くの弁護士会に問い合わせてみることをおすすめします。弁護士事務所での相談は、初回だと30分5,000円~という料金設定をしているところも多いです。
不本意に高額商品やサービスを契約してしまった場合、数十万円以上の負担がのしかかることもある。和田先生も「放置するほどトラブル解決が困難になることもあります。まずは相談してみてください」とアドバイスをくれた。一人で悩みを抱え込まず、困りごとはプロフェッショナルに相談してみるのがいいかもしれない。
成年年齢が18歳に引き下げられ、若いみなさんの自己決定権が尊重され、自分の意志でさまざまな契約を締結できるようになりました。自分の考えをもとに契約を締結できるようになると、いろいろな可能性が広がってくるでしょう。
一方で、今回の改正は「18歳=自分の行為に責任を持たなければいけない年齢になった」ということでもあります。自分の決定によっていろんな権利、義務も発生するようになります。契約について知識を持ち、ちょっとだけ意識をするようにしていってほしいですね。
和田先生、ありがとうございました!
教えてくれたのは?
取材・文=佐々木正孝