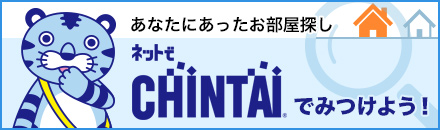「引越しそば」とはどんなもの?由来や食べ方を解説
日本の風習「引越しそば」って知ってる?

引越しにまつわる風習「引越しそば」
日本にはさまざまな風習があるが、引越しをするときの風習として「引越しそば」というものがある。引越しをすると周囲の環境が大きく変化するが、それと同時に近所への挨拶もしておかなくてはいけない。
引越しそばは、この挨拶のときに近所の人に配るというものだが、近年はそば以外の品物をプレゼントする人も増えているようだ。ここでは、古くから残る風習の1つである引越しそばの意味や由来について紹介していこう。
そもそも引越しそばとは?
もともと、そばというのは米が育たない寒冷地に住む人が、米の代わりの主食になるものとして作っていた救荒作物である。地方によっては粗食とされていたが、現代ではパンやうどんなどと同じように食べられている。
都内の高級なそば屋であれば、ざるそば1枚で2,000円以上するものもある。一方、最寄りの駅前には気軽に食べられる立ち食いそば屋もあるように、日本人の食生活に馴染んでいる。
また、普段の食事だけではなく、戸隠そばやわんこそばなど特別な日やお祝いの席で食べられることも多い。例えば年越しそばは、新しい年を迎えるにあたり、寿命や家運が細く長く伸びるようにとの祈りが込められている。そして、1年の厄災を断ち切って新年を迎えるという意味で食べる風習もあり、地域によってそれぞれ異なる。
引越しというのも昔はお祝い事の1つであったので、引越しそばという風習が定着した。引越しそばというと、引越しをした日のお昼に食べるものというイメージを持っている人も多いのではないだろうか。ダンボールなどが散乱している部屋の中で、引越しを手伝ってくれている友人と一緒にそばをすすっている風景が頭に浮かぶ人もいるかもしれない。
しかし、本来の引越しそばは自分たちで食べるものではなく、近所の人へ引越しの挨拶として配るものだ。どうしてそばを配るのかというのは、引越しそばの由来にその理由が隠されている。
引越しそばの由来・意味
引越しそばを配るという風習が始まったのは江戸時代からといわれている。当時は木造の長屋が一般的で、壁一枚で隣とつながっていたため、生活音が漏れてしまうのは当たり前のことだった。近所に迷惑をかけてしまうことも多く、三軒両隣の範囲まで挨拶をするのが常識で、そのときに粗品としてそばを持参したことが始まりとされている。では、なぜそばを配るようになったのかというと、2つの理由がある。
もともとは縁起もののお餅や小豆を配っていたようだが、当時はどちらも安く手に入るものではなかった。そのため、手軽に手に入れることができるそばを贈るようになった。これが1つ目の説である。
もう1つは、江戸っ子ならではの洒落である。「そば(蕎麦)に越してきた」という語呂合わせや、「そばのように細く長くお付き合いしてください」という意味合いを込めて、引越しそばを贈るという説である。
この2つの説で有力なのは後者の方だ。コスト削減のためにそばを贈られるというのは気持ちのよいものではないため、洒落を効かせた説の方が広まったといわれている。
なお、引越しそばの風習は関東や甲信越、東北などでは浸透しているものの、ほかの地域ではまったく知らないというところもある。例えば、近畿地方では女性がいつまでも美しくいられるように、新居には最初に鏡を運び入れるという風習がある。
また、香川県では太く長く生きられるようにという願いを込めて、新築を建てたときの最初のお風呂に入りながらうどんを食べる風習がある。さらに沖縄県では家族や友人と泡盛を飲んで引越し祝いをしたりするなど、さまざまな風習があるそうだ。
現代、引越しそばはどう変わった?
最近は、引越しをしても挨拶をすること自体少ないといわれている。特にアパートやマンションなどの賃貸物件では、いずれまた引越しをする可能性もあるため、隣近所と顔見知りになる必要がないという認識の人もいるようだ。
たしかに顔見知りになったからといって、何かあったときに助けてくれるとは限らない。また、風変わりな人と知り合いになってしまうと。余計なトラブルに巻き込まれてしまう可能性もある。
しかし、引越しの挨拶というのは、周りにどんな人が住んでいるのかを知るよい機会でもあるので、面倒であってもしっかり済ましておくのがベストだろう。そのときに配るのが引越しそばなのだが、今はそばを配る風習を知っている人も減っているうえに、見知らぬ人から食べ物をもらうのは抵抗があるという人もいるかもしれない。
そのため、そば以外のものを配ることが多くなっている。挨拶品のアンケートでも、1位はお菓子で2位は洗剤、3位はタオルというように、すぐに消費できたり日常生活で使えたりするものが多い。しかし、何を贈ればいいのかわからないという人のために、ここからはおすすめの粗品を紹介しよう。

引越しの挨拶自体が減った昨今では引越しそばの風習も下火になっている
乾麺
引越しそばの風習に習いたいというのであれば、乾麺を贈るのがおすすめだ。生麺ではすぐに食べなくてはいけないうえに、食べられない場合は捨てることになってしまう。
乾麺であれば保存が利くし、仮に苦手な場合でも友人などにプレゼントできるので、相手に迷惑をかけることも少なくなる。
日用品
引越したばかりで隣近所の家族構成がわからないというのであれば、日用品を贈るといいだろう。日用品であれば、比較的安価で手に入れることができる。
ただし、石鹸やシャンプーなどは個人の好みがあるので、食器用洗剤や衣類用洗剤など消費しやすいものを選ぶのがおすすめだ。
お菓子類
隣近所の家庭で子どもがいるようであれば、お菓子をあげると喜ばれる。お菓子を選ぶときは、チョコレートやクッキーといった誰でも気軽に食べられるようなものにしよう。
日用品と同じで人によって嗜好は違うので、あまり変わったお菓子を選ぶのはNGだ。また、旅行中など場合によっては渡すまでに時間がかかってしまうこともあるため、賞味期限が短いものも避けておこう。
現代では引越しそばを贈るという風習は薄れてきているが、新たに定着しているのが、引越し当日にそばを食べるということだ。実は、新居で引越しそばを食べるというのは大正時代ごろから広まっていったといわれている。
大正時代には「そば切手」というものがあり、これを隣人に配っていた。現代の食券のようなもので、この切手をお店で出すとそばを食べることができる。これが「引越しをしたら新居でそばを食べる」という風習になり、現代にいたっている。
慌ただしい引越し作業の中で、縁起を担ぐ意味でそばを家族や友人と食べるのは、どこか気持ちが浮き立つものである。引越しの際、隣人からそばを受け取ったときは、めったに食べることのない引越しそばを堪能しよう。
日本の風習、引越しそばを楽しんでみよう!
今は、引越しの挨拶でそばを配るという人は少ないかもしれない。たしかに、洗剤やタオルといった実用的なものの方がコストもかからないだろう。
しかし、引越しそばは江戸時代から続く日本ならではの風習であり、古いものが見直されている現代では、逆にそばを贈ることで交流が深まることもある。新生活は環境作りが大切だが、その中でもご近所など人間関係を良好にしておくことも重要なので、引越しそばを持参して挨拶回りを楽しんでみるといいだろう。