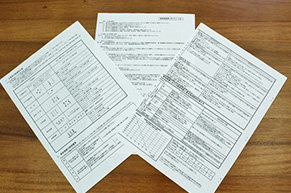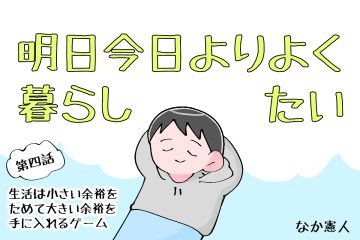木造とは|防音性などの注意点、物件選びのポイントを建築・不動産のプロが解説

鉄骨造やコンクリート造の物件に比べると、家賃が安い傾向にある木造の賃貸物件。「音漏れが心配」「耐震性や耐火性が不安」といった声を耳にすることも。
しかし、木造の物件だからといって必ずしもそうとは限らない。また、近年は建築工法等の進化によって、防音性に優れた木造物件や耐震性・耐火性を強化した木造物件も増えてきている。
この記事では、木造物件のメリット・デメリットを整理し、内見時にチェックすべきポイントを解説する。建築・不動産のプロの視点から判断材料を提供するので、ぜひ参考にしてほしい。
この記事でわかること
木造物件のメリットやデメリット、注意点
耐震性や耐火性能が高い「木造マンション」とは?
建築・不動産のプロが伝える「木造物件選びのポイント」
このページの目次
木造物件とは?
木造とは、柱や梁といった主要な構造部分に木材を使用した建築構造のことを指す。日本では古くから住宅に多く採用されてきた。現在でも戸建て住宅やメゾネット、上下階で住戸が分かれた重層長屋、2~3階建てのアパートに多い。
木造物件は、工法ごとに防音性や耐震性などが異なる
木造アパートといっても、すべてが同じ造りではない。代表的な工法は、柱と梁、筋交いで骨組みした「在来軸組工法」と、壁や床、天井などの面で支える「枠組壁工法(ツーバイフォー工法、2×4工法)」の2つだ。

ツーバイフォー工法は、構造用製材で構成した枠組みに構造用合板や石膏ボードなどを組み合わせて壁・床・天井をつくり六面体の箱として構成する。構造上重要な「耐力壁」と「剛床」が一体となるため、耐震・耐火性、気密・断熱性、防音・遮音性などの面で在来軸組工法の性能を上回るとされている。
ただし、近年の在来軸組工法の物件は、主要な構造の接合部分を金属製の接合金物で補強し、建物の強度や耐震性を高めているものが多い。また、ツーバイフォー工法のように構造用合板を使って壁で建物を支えるタイプの工法が採用されているケースもあり、新築や築年数の浅い在来軸組工法の物件はツーバイフォーと同等の性能を備えているものもある。
木造は建築コストの低さ、環境への配慮などの面で社会的なニーズが高いことから、近年は大規模建築物や高層建築物にも採用されるなど「最も進化している建築構造」といえます。現在は、デザイン性も含め性能や品質が高い木造住宅が増えています。
耐火性や耐震性を強化した「木造賃貸マンション」については、後ほど紹介する。
木造物件のメリット
木造の物件には「安い」「古い」といったイメージを持つ方もいるかもしれない。しかし、実際には暮らしやすさにつながる利点も多い。特に近年は工法の進化によって性能が底上げされ、ステータスを感じる住まいの選択肢として十分に検討できる物件が増えてきた。代表的なメリットは以下のとおりだ。
1.家賃が比較的安い
木造は、ほかの建築構造の物件に比べ建築コストが低いため、鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の物件に比べて家賃が安い傾向がある。毎月の固定費や引越しの初期費用を抑えたい人にとっては大きな魅力だ。
2.カビや結露が発生しにくい
木材は湿気を吸収・放出する調湿性に優れているため、カビや結露が発生しにくいという利点がある。
さらに、近年は外壁材と下地の間に空気の通り道を設ける「外壁通気工法」を採用した物件が多い。木は濡れると劣化しやすいが、この工法によって湿気がこもらず乾きやすくなるため、結果的に木材の耐久性を高めることにつながる。
3.木の温かみや柔らかい質感を味わえる
木造は鉄骨やコンクリートにはない、自然素材ならではの温かみや柔らかさを味わえる。
木造物件のデメリットと注意点
一方で、木造には弱点もある。特に「音」や「気密性」は、入居後の快適さに直結するため注意が必要だ。
1.防音・遮音性が低い
木材は鉄やコンクリートに比べて軽いため、上下階や隣の部屋の生活音がどうしても伝わりやすい。そのため、一般的には鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの建物よりも防音・遮音性能が低くなる。
2.気密性が低い
一般的な在来軸組工法は隙間が生じやすく、外気が入り込みやすい。よって、特に築年数の古い木造物件では気密性が低い場合が多く、冷暖房効率が下がる等のデメリットがある。
ただし、ツーバイフォー工法は面構造となっているため、気密性が高い。
なお、在来軸組工法であっても、近年建てられた物件では、耐震性を高めるためにツーバイフォー工法と同様の工夫が施されている場合が多いです(外壁下地や床下地に構造用合板を採用する等)。
また、室内側の壁・床・天井の下地に石膏ボードを採用したり、気密性の高い窓を採用したりと、気密性や防音・遮音性を強化した物件も多くなってきました。
木造の物件は、火に弱い?
防音性や気密性といったデメリットのほかに、気になるポイントが「火災のリスク」だ。木は可燃物であるため「火に弱そう」「耐火性が不安」と思う人も少なくない。
しかし、木造の物件は必ずしも「火に弱い」わけではない。断面の大きい木材は表面が燃えると炭化層ができ、その層が内部を保護して急激な倒壊を防いでくれる。また、石膏ボードなどの不燃素材を使うことで、適切な耐火被覆処理がされていれば耐火性はさらに高められる。
木造の物件は、地震に弱い? 地震に強い物件を見極めるポイント
「木造は地震に弱いのでは?」と不安に思う人もいるだろう。しかし実際には、耐震性能は築年数や耐震補強・改修の有無によって大きく変わる。構造特性が違うので単純に比較はできないが、2000年の改正建築基準法で定められた現行の耐震基準を満たした木造は、住宅性能評価を受けることで鉄骨やRCに劣らない耐震等級を表示することができる。
地震に強い木造物件を見極めるポイントを藤浦さんが教えてくれた。
1.新築や築年数が浅い物件
工法の進化により、木造物件の耐震性能は底上げが進んでいる。新築や築年数が浅い木造物件であれば、新しい技術が採用されている可能性がある。不動産会社に「木造でも地震に強い物件に住みたい」と相談してみよう。
2.現行の耐震基準を満たして建てられた物件か
1995年の阪神・淡路大震災の被害を受け、2000年の改正建築基準法では、木造住宅の耐震基準に関する規制が強化された。この耐震基準を「2000年基準」と呼ぶ。新築ではなくとも、2000年基準をクリアした物件であれば、木造物件の中でも耐震性が比較的高いといえる。不動産会社に確認してみよう。
3.古い物件の場合、耐震補強工事を行っているか
築年数が古い物件でも、耐震診断を行い耐震補強工事を行うことで、耐震性能を引き上げることができる。耐震補強済みかどうかは、やはり不動産会社に確認したい。
木造が本格的に進化し始めたのは2000年の建築基準法改正以降です。同年4月1日に施行された「住宅性能表示制度」により評価の仕組みが整い、木造住宅の耐震性能は飛躍的に向上してきました。いまの木造は昔のイメージとはまったく違い、安心して選べる水準にあると考えてよいでしょう。
最近では、耐震性や耐火性能の高い「木造マンション」も登場
近年は、工法や建築材料の進化によって、耐震性・耐火性・耐久性などに優れた木造物件が数多く登場している。
CHINTAIでは、建物が3階建以上かつ共同住宅 (テラスハウス除く)で以下の条件を満たす木造の物件を「木造マンション」と表示している。
劣化対策等級(構造躯体等)が等級3で、①~③の内いずれか1つに該当する
① 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) が等級3
② 耐火等級(延焼の恐れのある部分[開口部以外])が等級4
③ 耐火構造
外観やデザインは鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造に引けを取らず、おしゃれな雰囲気の物件も多い。
木造は建築時に排出する二酸化炭素の量がほかの構造に比べて圧倒的に少なく、木が炭素を蓄積することから、カーボンニュートラルや脱炭素化社会に貢献できます。環境にやさしい素材でもあるので、サステナブルな暮らしを意識する人にとっても魅力的です。
木造物件がおすすめなのはこんな人
木造は、鉄骨造やRC造に比べて防音や気密性の面では劣る部分もあるが、暮らし方によっては魅力的な選択肢となる。特に以下のような人におすすめだ。
生活スタイルの面では、単身や夫婦二人など少人数で暮らす人に適している。共同住宅でも大きな生活音を立てない、または多少の音を気にしない人であれば、木造でも快適に暮らしやすい。
ファミリー層であれば戸建てやメゾネットタイプの木造物件がおすすめ。庭付きや駐車スペース付きの物件もあり、子育てや趣味の時間を楽しむのに向いている。車やバイクが好きな人には、1階が車庫になっている木造二階建てのガレージハウスという選択肢もある。
そして、メリットで挙げたように、木のやさしさや温かみといった質感を大切にしたい人にもおすすめできる。無垢材や木目の風合いを楽しめる物件は、ナチュラルな雰囲気を好む人に心地よい住まいとなる。また、古民家や築年数の経った物件のレトロな雰囲気を楽しみたい人にとっても木造は魅力的だ。
建築・不動産のプロが教える!木造物件選びのポイント
木造アパートは築年数や工法、間取りなどによって性能に差が出やすい。内見のときに以下の点を不動産会社に確認しておくと安心だ。
1.耐震補強や改修の有無
築年数が古い場合は、耐震補強工事やリフォーム歴があるかを不動産会社に確認しよう。
2.外装や共用部分の劣化
屋根の傷み具合・外壁のひび割れや外階段・バルコニーの傷み、防水処理の状態をチェックしよう。劣化が進んでいると雨漏りや腐食につながる。
3.界壁や界床の仕様を確認する
界壁(住戸と住戸を仕切る壁)や界床(上下階の住戸を仕切る床)の厚みや材質は、防音・遮音性に影響する。広告や間取り図では分からないことが多いため、内見時に同行する不動産会社の担当者に許可を取って壁を軽くノックしてみたり、防音・遮音性が高い仕様かを確認すると安心だ。
4.集合住宅の場合、界壁の向こうに何があるか
「界壁の向こうに何があるか」も重要。例えば、浴室やキッチンなどの水回り同士が隣り合う配置だったり、隣の居室との間に収納スペースや廊下などがあったりすれば、音や振動の影響を受けにくい。逆に、自分の部屋のリビングと隣室のベッドルームが隣り合っていると騒音トラブルが起きる可能性もある。配置を確認しておくと安心だ。
5.防音・遮音性を左右する建具や内装
窓の性能や内外装の仕上げ材によっても防音性は変わる。防音性や断熱性に優れた窓が使われていたり、壁・床・天井に吸音性能のある建材を採用している物件なら防音・遮音性に期待できる。
6.内見時の音チェック
部屋では内装や設備などを目で見るだけではなく、耳も活用してほしい。上下階や隣室からの音の響きを体感することが大切だ。
7.部屋の位置や立地など
木造以外の建築構造でも同様だが、共同住宅の場合、角部屋や最上階、1階など隣や上下と接する部屋が少ないほど音や振動の影響を抑えられる。また、幹線道路や駅、学校などの近くは外部からの音に悩まされる可能性がある。不動産会社に、「過去に騒音トラブルがなかったか」も確認するといいだろう。
木造は工法の進化で性能が向上している一方で、築年数が古い物件では特に音の問題に対する注意が必要です。外装や共用部分の劣化に加え、上下階や隣戸の水回りの配置も重要なチェックポイントになります。
木造物件で「音の問題」が不安な場合の対処法
木造物件でも、自分や家族が発する生活音を抑えたり、外部からの音に対して防音対策を行うことはできる。
例えば、防音性の高いカーペットや防音・防振マットを用意することで足音の響きを抑えることができる。また、厚みのあるカーテンを設置する、本棚などの大型の家具を隣室との界壁側に配置するなどの工夫で、生活音の反響を軽減することも可能だ。
詳しい防音対策や防音グッズについてはこちらの記事で紹介している。
木造=質が低いは思い込みかも。自分の暮らし方に合う物件を探そう
木造に「家賃は安いけれど質が低い」というイメージを持つ人もいるが、そうとは限らない。特に近年は工法や建築材料の進化によって、防音性や耐久性に優れた木造物件も増えている。
重要なのは、建築構造そのものよりも「物件の状態」と「自分の暮らし方との相性」だ。築年数や耐震工事・リフォームの状況、間取りや水回りの配置などを不動産会社にしっかり確認すれば、木造でも快適に暮らせる。木の温かみやナチュラルな雰囲気を好む人にとっては、他の建築構造にはない魅力を味わえるだろう。
最初から木造物件を選択肢から外すと、住まい選びで視野を狭めることになりかねない。メリット・デメリットを理解した上で、ライフスタイルに合った住まいを選ぶことが、満足度の高い賃貸生活につながる。
賃貸住宅の魅力は、住み替えができることです。進学や就職、結婚、単身赴任など、人生の節目ごとにライフスタイルに合う住まい選びができます。引越しを通して、新しい街の良さに気づいたり、いろいろな間取りを楽しんだり、快適に暮らすための工夫をしたり、きっと良い経験が得られるでしょう。
なかには、将来的に持ち家やマンションの購入を考える方もいるかもしれません。大切なご家族の安全や、建物や土地の資産価値を考えるとき、賃貸住宅での経験や気づき、建築構造の知識がきっとお役に立ちます。
この記事が、みなさまの人生をより良くする一助となれば幸いです。
賃貸物件のほかの建築構造について知りたい方はこちら
軽量鉄骨造(S造)
重量鉄骨造(S造)
鉄筋コンクリート造(RC造)
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
その他
監修、取材協力:藤浦 誠一 (株式会社エイブル)
文:佐々木正孝(キッズファクトリー)