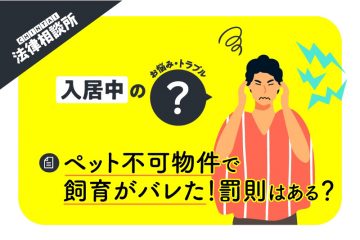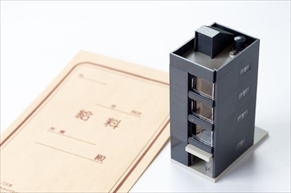【弁護士が解説】家賃が払えない場合どうしたらいい?住居確保給付金など制度も紹介
家賃が払えない!そんな時どうする?
コロナ禍の影響に限らず、仕事を失ったり、収入が激減したりした結果、「家賃が払えない」と困ることは誰にでもありえる。金銭面の悩みは打ち明けづらい場合もあり、一人で抱えてしまう人も多いのではないだろうか。
日本には、家賃が払えない状況におかれた方に向け、さまざまなサポート制度がある。
この記事では、家賃が払えない場合の対処法について下記を解説する。
- 家賃を滞納した場合のリスク
- 家賃が払えなくなってしまった場合の対処法
- 利用できる公的制度(給付・無利子貸付)(すぐに解説を読みたい方はこちら)
お話を聞いたのは、あかり法律事務所の弁護士・小久保哲郎先生。さまざまな事情から、家賃の支払いに不安がある方はぜひ参考にしてほしい。
小久保先生:
「住まい」は生活の基盤。一度失ってしまうと、たちまち生活再建が難しくなってしまいます。ただ、意外と知られていないのですが、法律では住む人(賃借人)の権利が比較的手厚く保障されているのです。
大切な「住まい」を失うことのないよう、正しい法律の知識を身につけるとともに、公的な支援の活用方法を知っていただきたいと思います。
※この記事でご紹介している情報は、2022年(令和4年)4月時点の情報です。本記事の公開直前に期間延長された支援制度もあったため、制度の利用を検討する際は、適用期間について最新情報を支援窓口や公式サイトで確認してください
家賃が払えないとどうなる?滞納した場合のリスク
月々の生活費のうち、大きな割合を占める家賃。「仕事ができなくなってしまった」「予定外の出費で手持ちのお金がなくなった」など、家賃が払えなくなる可能性は誰にでもある。
「家賃が払えない状態(=家賃滞納)」をそのままにした場合のリスクとしては、「強制退去」、場合によって「信用情報に傷がつく」の2つがある。
※家賃が長期的に払えない状態をを防ぐための公的支援は、次のページで紹介します
小久保先生:
「1~2ヶ月でも家賃を滞納したら、すぐに家を出ていかなければならない」と誤解している方もおられますが、そんなことはありません。賃貸借契約は、その当事者間の信頼関係が破壊されるような債務不履行があって初めて解除することができます(民法541条但し書き)。
仮に有効に契約解除がなされたとしても、貸主が借主を強制退去させるためには、明渡訴訟を提起して判決を得たうえで強制執行手続を行う必要があり、さらに何か月もかかります。
家賃が払えず長期滞納すると、強制退去の可能性がある
賃貸物件を借りる際に締結する賃貸借契約書には、「家賃の滞納」が、契約違反とみなされる行為のひとつとして記載されている。細かい条件はそれぞれの契約によって異なるものの、家賃滞納が長期間に及ぶと、退去(=物件から出ていくこと)を求められる可能性が出てくる。一般的に強制退去の目安は、3~6ヶ月以上の家賃滞納なので注意しなければならない。
ただし、法務省民事局は、コロナ禍の影響で生じた賃料不払いについて、不払いの期間が3ヶ月程度であれば契約解除が認められないケースも多いとしている。
※参考:法務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ~賃貸借契約についての基本的なルール~」
家賃滞納により強制退去を求められる場合、具体的に以下のような流れで各種手続きが進んでいく。
- 支払い督促が行われる
- 連帯保証人などに連絡が入る
- 賃貸契約が解除される
- 明渡し訴訟(裁判)が行われる
- 強制退去になる
強制退去の流れ①:支払い催促が行われる
家賃を1~2ヶ月間滞納した場合、大家さんや管理会社より「家賃の支払い督促」が行われることになる。連絡手段は訪問、電話、メール、手紙などで、担当者から「家賃を支払ってください」という請求が複数回行われる。
滞納が続くと、大家さんから内容証明郵便で督促状が届くことがある。この督促状には、家賃滞納の確認、支払いを催促する記述のほか、支払いがなければ契約解除となる支払期日も記載されていることが多い。
※編集部注:内容証明郵便とは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」ということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度。裁判などで「〇月〇日に家賃の督促を行った」という有効な証拠になる。
強制退去の流れ②:連帯保証人などに連絡が入る
どのタイミングで行われるかは場合によるが、入居者が督促に応じない場合、契約書に記載した連帯保証人や保証会社などに連絡がいく。保証会社が滞納家賃を代わりに支払った場合は、保証会社から督促が入ることになる。
強制退去の流れ③:賃貸契約が解除される
入居者自身や連帯保証人が、滞納家賃を支払わないことが3~4ヶ月続くと、賃貸借契約を解除する通知がされることが多い。契約解除となれば、入居者が引き続き住み続けると不法占拠状態となるので、本来はすみやかに物件を退去しなければならない。
強制退去の流れ④:明渡し訴訟(裁判)が行われる
賃貸契約が解除された後も入居者が退去しない場合には、「不動産明渡請求訴訟」を起こされる可能性がある。これは、建物の明渡しと滞納分家賃の支払いを求める裁判である。③の契約解除通知が内容証明付きの郵便で送付されるのは、この裁判で大家さん側が使用するためだ。
強制退去の流れ⑤:強制退去になる
裁判で大家さん側の主張が認められても立ち退かないでいると、大家さんは判決に基づく強制執行を申し立てることができる。裁判所の執行官が物件の現状の調査に来たうえで明渡しの催告が行われ、そこから約1ヶ月後に明渡しの「断行日」が設定される。この「断行日」まで明け渡さない場合には、入居者の所有物が強制的に建物外へ運び出されてしまう。
家賃が払えない場合、信用情報に傷がつくことはある?
家賃が払えなかった場合に信用情報に傷がつくかどうかについて、結論から言うと、契約内容や家賃の支払い方法によって変わってくるようだ。
そもそも信用情報とは、住宅ローンなどのローンを組んだり、クレジットカードを契約したりする場合に、銀行やクレジットカード会社などが審査のために照会する個人の取引情報のこと。「この人を信用してお金を貸してもよいか」を判断するために使う、これまでの支払い状況の履歴といったイメージだ。
新たにこれらの契約を結ぶ際、信用情報に過去の支払い遅れや家賃滞納の記録があれば、審査において考慮される可能性がある。
信用情報のデータベースは、クレジットカード会社や家賃保証会社など、複数の企業によって連携されている。このため、家賃を滞納すると、家賃保証会社を利用している場合は、連携している信用情報のデータベースに記録される場合がある。連携先のデータベースによっては、今後新規でクレジットカードを作ることができなかったり、ローンの審査に通りにくくなったり、家を借りにくくなったりする可能性があるのだ。
ただし、信用情報の扱いは利用している家賃保証会社によって異なるようだ。既に家賃を滞納したことがあり、今後のクレジットカードや住宅ローンなどの審査に影響するかどうかが心配な場合は、ご自身の利用している家賃保証会社に確認するのが確実だろう。
一方、連帯保証人を家族などに頼んでいる場合(=いわゆる人的保証の場合)は、家賃の振り込みが遅れた場合でも、それだけで信用情報に記録される可能性は低いといえる。
家賃が払えないときの対処法は?
ここまで、家賃が払えない場合に起きる可能性のあることについて解説した。
前述の通り、家賃が払えなくなった場合もすぐに退去になるわけではないので、自分を追い込まず、できることを確認しよう。対応しておきたいことを紹介していく。
小久保先生:
管理会社や保証会社の中には、部屋に立ち入って物を放り出したり、留守中に鍵を替えるなどして入居者を閉め出したりする手荒な会社もありますが、このような「自力救済※」は違法です。
また、期限を切って強引に立ち退きを求め、「念書」に署名をさせようとする業者もいますが、できない約束はしてはなりません。仮に署名してしまったとしても、意思表示の取消し等を主張する余地もあるので、対応に困ったらぜひ弁護士会などで相談してください。弁護士費用を「法テラス」が立替払いしてくれる民事法律扶助制度もあります。
※参考:法テラス(日本司法支援センター)
※編集部注:自力救済とは、自身の権利が侵害されていると考え、法律にのっとらず実力行使をもって権利を回復しようとすること。法務省の「紛争解決・司法」の資料にも「力や立場の強い者が自力救済による解決を図るなどして弱い立場の者が虐げられ,社会秩序が混乱しかねません。」と記載があり、司法の仕組みを用いた紛争解決を呼び掛けています
家賃が払えないとき:まずは大家さんや管理会社に報告・相談する
1ヶ月など一時的に家賃が払えない場合には、素直に大家さんや管理会社へ相談してみよう。少しの期間であれば待ってもらえる可能性もある。その場合は「〇月〇日までにはきちんと支払う」など返済の意思を伝え、その期日までに家賃分のお金を用意するようにしよう。
家賃が払えないとき:公的制度を利用する
家賃が払えない、生活費がなくて困っているといった状況を救済するさまざまな制度を、国や自治体、公的機関が用意している。家賃が払えないときに利用できる公的制度には「住居確保給付金」「休業支援金・給付金」「緊急小口資金」「総合支援資金」「生活保護」があるほか、新型コロナウイルスの影響を受けた人をサポートするさまざまな制度もある。これらについては次のページで詳しく説明する。
次のページでは、家賃が払えないときに利用できる公的制度を紹介している。
ほか、本質的な解決ではないかもしれないが、選択肢としては下記のようなものもある。
家賃が払えないとき:短期的な理由であれば消費者金融を利用することもできる
家賃を支払うときにちょうどお金がないなど、一時的な金欠の場合は消費者金融を利用するという手もあるが、消費者金融は利息が高い(上限金利は金額に応じて年15%~20%)。「初回利用のみ30日間無利息」をうたっている所もあるが、一度借りてしまえば、次回以降は無利息では利用できなくなるし、期日までに返せなければ利子がどんどん増えていく。一方の公的制度には無利子・保証人不要のものがある。まずはこの後紹介する公的制度の利用を検討してほしい。
家賃が払えないとき:実家など頼れる人の家を間借りする
今後も家賃の支払いが難しいと判断したら、実家など頼れる人の家を間借りするのもひとつの手段だ。家賃の負担金額をこれまでよりも浮かせて、お金の心配を減らすことができる。もちろん、家族や知人との関係性は人によるので、頼るのが難しいと感じる場合はすぐに公的制度を申請しよう。
家賃が払えない!そんな時どうする?
この記事では、家賃が払えなくなった場合や、支払いに不安があるときに役立つ情報を解説している。このページでは、困ったときに・困る前に利用を検討してほしい、公的制度を紹介する。
家賃が払えないときに利用できる公的制度
家賃が払えないときをはじめ、生活困窮している場合に利用できる公的制度は複数ある。また、新型コロナウイルスの影響もあり、近年さまざまな制度の要件が緩和されたり新設されたりしている。まずは以下の5つについて利用を検討してみよう。
①住居確保給付金(短期的な給付)
②休業支援金・給付金(短期的な給付)
③求職者支援制度(2ヶ月から6ヶ月の訓練と月10万円の給付)
④生活保護(長期的な給付)
⑤緊急小口資金(無利子貸付)
⑥総合支援資金(無利子貸付)
※制度の名前をクリックすると、各制度の公式ページへ遷移します
返済の有無や支給額など異なる部分が多いので、それぞれひとつずつ解説していく。
家賃が払えないときに使える公的制度①:住居確保給付金
住居確保給付金は、収入減となった人に代わり、国が大家さんへ家賃(の一部)を支払ってくれるという家賃救済制度。申請には一定の条件をクリアする必要があるものの、返済の必要はない。
審査に通過すると、入居者ではなく大家さんへ直接家賃が支払われるのが特徴だ。給付される家賃の上限額や、利用できる世帯収入の上限額は、地域により変わる。給付期間は3ヶ月間だが、申請したタイミングによっては延長も可能だ。
小久保先生:
住居確保給付金はコロナ禍前からあった制度ですが、「離職後2年以内」「熱心な求職活動」など要件が厳しくてほとんど利用されていませんでした。それが、コロナ禍後、要件がかなり緩和されて使いやすくなり、爆発的に利用が増えました。家賃の支払いに困った方はぜひ利用を検討してください。
ただ、収入基準が厳しすぎる、家賃の上限が(生活保護の基準と同じで)安すぎるなどの問題があり、欧米並みの「住宅手当(家賃補助)」制度への改善が必要だと考えています。
また、これもコロナ特例で、最大6か月職業訓練を受けながら月10万円の給付を受けられる求職者支援制度と住居確保給付金を一緒に受けることもできます。
住居確保給付金の概要
| 目的 | 家賃の補助 |
|---|---|
| 対象者 | 賃貸物件に入居中で、 離職・廃業2年以内または収入が減少し、家賃の支払いが難しくなった世帯 |
| 支給額 または 貸付上限 | 家賃額(上限は市区町村で異なる) × 原則3ヶ月間~最大9か月間 |
| 返済・利子の有無 | 給付(返済不要) |
| 申請・相談先 | 役所の自立相談支援機関 |
- 賃貸物件に入居中で、離職・廃業2年以内または収入が減少している人を対象に、国が家賃相当額を代わりに支払う
- 審査通過後は、大家さんなどへ自治体より直接家賃が支払われる
- 給付金のため返済不要 ・世帯の収入や預金額が上限を超えない、求職活動をしているなど、申請には一定の条件あり
- 給付金額は家賃額(上限は市区町村で異なる)×3ヶ月で、延長は2回まで、最大9ヶ月間給付される
- 外国籍の方も対象になる可能性がある
※参考:厚生労働省「住居確保給付金」
家賃が払えないときに使える公的制度②:休業支援金・給付金
正式名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」。新型コロナウイルスの影響で休業したお店や会社に勤めており、その期間の賃金も休業手当も支払われない場合に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支払われる。対象となる休業期間が令和4(2022)年3月末まで延長されている(申請は6月末まで)ので、自分が対象になるかまずは確認してみよう。
小久保先生:
「不可抗力による休業」以外の休業の場合、本来、使用者(労働者を雇っている会社やお店など)は休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません。
この手当を支払う企業に対する雇用調整助成金による助成制度もありますが、手当を支払わない企業も多いため、特別に新設されたのがこの休業支援金です。
休業支援金・給付金の概要
| 目的 | 賃金の補填 |
|---|---|
| 対象者 | 新型コロナが原因の休業により、 賃金も休業手当も支払われない方や 雇用保険の被保険者ではない方 |
| 支給額 または 貸付上限 | 休業前賃金の8割 (日額上限11,000円) |
| 返済・利子の有無 | 給付(返済不要) |
| 申請・相談先 | 厚生労働省 |
- 一定の期間に新型コロナの影響を受けた事業主の指示により休業した労働者で、その休業に対する賃金も休業手当も支払われていない方、雇用保険の被保険者ではない方が対象
- 休業の対象期間が令和4(2022)年3月末まで延長された(申請は6月末まで受付)
※参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」
家賃が払えないときに使える公的制度③:求職者支援制度
再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を2~6か月間にわたり受講できるという制度。給付金の対象となるのは、離職して雇用保険を受給できない方や廃業したフリーランス・自営業の方、パートタイマーなど収入が一定額以下の在職者の方など。ハローワークによる無料の職業訓練を受講しつつ、求職活動のサポートを受けることもできる。注意点としては、同じ世帯から複数名の受給ができないこと、訓練を欠席すると給付金が日割りになってしまうことだ。
小久保先生:
この制度は非常に厳しい運用(1時間でも理由なく授業を休むと1ヶ月分全額の給付が受けられなくなるなど)のため、コロナ禍前はほとんど使われていませんでした。ですが、コロナ特例で「欠席の場合も日割りで支給」とされました。そのほか、対象となる本人月収(8万円→12万円)や世帯月収(25万円→40万円)の変更、住居確保給付金との併給が認められるなど運用が緩和されています。
生活費をもらいながら職業訓練が受けられる親切な制度なので、コロナ禍後もこうした運用を続けてほしいところです。
休業支援金・給付金の概要
| 目的 | 再就職、転職、スキルアップを目指す人の 職業訓練と給付金、就職サポート |
|---|---|
| 対象者 | 雇用保険の適用のない離職者の方や、 廃業された方、雇用保険の受給が終了した方、 正社員を目指すパートタイマーの方など (給付金を受けず、無料の訓練のみの申請もできる) |
| 支給額 または 貸付上限 | 月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、 無料の職業訓練を受講できる |
| 返済・利子の有無 | 給付(返済不要) |
| 申請・相談先 | ハローワーク |
- 無料の職業訓練を受けながら、毎月10万円の支援金が受け取れる
- 訓練の期間は2か月~6か月
- 給付金のため返済不要 ・世帯の収入や預金額が上限を超えない、求職活動をするなど、申請には一定の条件あり
- 令和5年3月末までの特例として、転職せずに働きながらスキルアップを目指す方も対象になった
家賃が払えないときに使える公的制④:生活保護
①のように家賃に限る制度や、②③のように比較的単発の制度だけではなく、生活費全般で困っている場合には生活保護制度がある。この制度は「国民のだれもが申請できる制度」なので、自分が対象か迷う場合でも申請自体はすぐにすることができる。
小久保先生:
家賃が高すぎて払えない場合(生活保護で支給される家賃上限額を超えている場合)や、家賃を何ヶ月も滞納していて家主さんから立ち退きを求められている場合には、引越し代や新しい家の敷金・火災保険料等を保護費から支給してもらうこともできます。
生活保護のイメージが悪くて利用をためらう方も多いと思いますが、わたしは制度を利用して生活を立て直した方を何人も見てきました。特に、転居のためのまとまった費用を(一定の要件を満たせば)給付してもらえる点はとても助かるはずです。ぜひ利用を検討してみてください。
生活保護の概要
| 目的 | 生活をするうえで必要な費用 |
|---|---|
| 対象者 | 「最低生活費」よりも世帯全体の収入が少ない世帯 など |
| 支給額 または 貸付上限 | 内容による |
| 返済・利子の有無 | 給付(返済不要) |
| 申請・相談先 | 福祉事務所 |
- 生活困窮者の程度に応じて必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限の生活を保障する」制度
- 「最低生活費」よりも世帯全体の収入が少ないこと、財産・資産が一定以下であること、働く能力がある場合はその能力を「活用」すること(勤め先が見つからない場合はそれでもよい)など
- 親族による援助が可能かは条件ではない
※参考:厚生労働省「生活保護制度」
これから紹介する2つの制度は、「特例貸付」と呼ばれる制度。返済が必要になるお金なので、まずは①~④の利用を検討してほしい。
家賃が払えないときに使える公的制度⑤:緊急小口資金
緊急小口資金は、低所得世帯が新型コロナの影響による失業や休業などのため、緊急・一時的に収入減となった場合に20万円を上限として生活費を国から借りられる制度だ。この制度は無利子で保証人が不要となる点がポイントといえる。なお、相談先は市区町村の社会福祉協議会だ。
小久保先生:
この「緊急小口資金」と、次に紹介する「総合支援資金」はセットで利用されており、併せて「(生活福祉資金の)特例貸付」といいます。今回のコロナ対応で最も利用されている制度で、2022年4月2日時点で318万件以上、1.4兆円近くの貸付がされています※。地域差はあるものの、かなり柔軟に貸付されており、貸付が終わり一定の収入・資産要件を満たす世帯は、月6~10万円を3ヶ月(最大6ヶ月)給付する「生活困窮者自立支援金」の給付が受けられます。
ただ、あくまで借金なので、住民税非課税世帯以外は、2022年12月末までの据置期間(2022年3月現在)が終わると返済しなければなりません。住居確保給付金、休業支援金、求職者支援制度、生活保護などの給付制度の要件を満たす方は、そちらを利用することをおすすめします。
※厚生労働省「くらしと仕事の情報」:https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html
緊急小口資金の概要
| 目的 | 緊急・一時的な生活費用 |
|---|---|
| 対象者 | 新型コロナの影響により収入減となった世帯 |
| 支給額 または 貸付上限 | 20万円以内 |
| 返済・利子の有無 | 返済あり (住民税非課税世帯を除く) 無利子 |
| 申請・相談先 | 社会福祉協議会 |
- 新型コロナの影響により収入が減った世帯の一時的な生活費貸付制度
- 新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象
- 学生アルバイト、外国人・技能実習生も対象
- 貸付上限額は20万円
- 無利子で保証人も不要
- 償還(返済)期限は2年間だが、引き続き所得の減少が続く「住民税非課税世帯※」の償還を免除
※編集部注:住民税非課税世帯とは、所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって住民税の納付義務が免除される世帯のこと(参考:港区https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html)
※参考:厚生労働省「緊急小口資金について」
家賃が払えないときに使える公的制度⑥:総合支援資金
総合支援資金は、新型コロナなどの影響によって収入が減り、日常生活を送ることが難しくなった世帯を援助するために貸付されるお金のこと。貸付限度額は世帯人数により異なり、二人以上世帯では20万円以内/月、単身世帯では15万円以内/月となっている。貸付期間は原則3ヶ月であり、合計で「それぞれの月額×3ヶ月分」を借りられるのがポイントだ。
⑤の緊急小口資金と同様、無利子で保証人が不要であるが、返済期限は10年以内と緊急小口資金に比べて長めに設定されている。相談先は市区町村にある社会福祉協議会だ。
総合支援資金の概要
| 目的 | 生活再建までの生活費用 |
|---|---|
| 対象者 | 新型コロナの影響により収入減となった世帯 |
| 支給額 または 貸付上限 | 二人以上世帯:20万円以内・単身:15万円以内 ×原則3ヶ月以内 |
| 返済・利子の有無 | 返済あり (住民税非課税世帯を除く) 無利子 |
| 申請・相談先 | 社会福祉協議会 |
- 新型コロナなどの影響により失業、減収し日常生活の維持が難しくなった世帯を支援する制度
- 制度の利用により「再就職の見込みがある」と判断されることで審査に通過
- 貸付限度額は二人以上世帯で月額20万円以内、単身世帯は月額15万円以内
- 貸付期間は原則3ヶ月以内
- 据置期間は原則1年以内、償還(返済)期限は10年以内だが、引き続き所得の減少が続く「住民税非課税世帯※」は償還を免除
- 無利子で保証人も不要
※編集部注:住民税非課税世帯とは、所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって住民税の納付義務が免除される世帯のこと(参考:港区https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html)
※参考:厚生労働省「総合支援資金」について
家賃が払えないときに使える公的制度:その他
ここまで紹介した①~⑥の制度のほかにも、
- 低所得の子育て世帯向けの「子育て世帯生活支援特別給付金」
- 小学校が休校になったために、お子さんの世話で仕事を休まなければならなくなったフリーランス・個人事業主の方向けの支援「小学校休業等対応支援金」
- 社会福祉協議会の貸付を利用したものの、引き続きお困りの方向けの支援「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」
- アルバイトや仕送りなどで学生生活を維持するのが難しくなってしまった学生の方向けの支援「学生等の学びを継続するための緊急給付金」
など、さまざまな制度がある。自治体によってはオリジナルの支援を行っている場合もあるので、まずは「自分だけでどうにかしよう」と思わずに、何か制度がないか探してみてほしい。
小久保先生:
わたしも参加する「コロナ災害を乗り越えるいのちと暮らしを守る何でも電話相談会(2020年4月から偶数月に開催)」では、1万件以上の相談を聞いてきました。コロナ禍対応の制度はツギハギで頻繁に変更がありますが、相談会開催のたびに「いのちとくらしを守るQ&A」を更新しています。相談会の開催日と「Q&A」の最新版は、その都度、生活保護問題対策全国会議(生保会議)のHPにアップしていますのでご確認ください。
また、各地の弁護士会や司法書士会などには法律相談窓口があります。わたしの所属する大阪弁護士会には、常設・無料の「新型コロナ電話相談窓口(06-6364-2046)」があるのでお気軽にご利用いただければと思います。
※参考:大阪弁護士会「新型コロナウイルスに関する総合電話相談のご案内」
家賃が払えないときは、早めに公的機関や支援窓口を利用しよう
収入に関して心配があり、「家賃を滞納したらどうしよう?」「家賃を滞納してしまった」そう思ってこの記事にたどり着いた方もいるだろう。まず知ってほしいのは、公的制度があることだ。申請条件によって利用できないものもあるかもしれないが、さまざまなケースに対応した制度が用意されているのでまずは確認してほしい。
また、何か制度を利用しづらい事情がある場合も、同じ悩みを持っている人がいる可能性があるので一人で抱え込まないでほしい。すべての自治体におかれている生活困窮者自立相談支援窓口などで、専門的な知識を持っている人に相談してみよう。
※参考:厚生労働省「生活困窮者自立支援窓口」
小久保先生:
「人」や「制度」に頼るのも、人間が生き延びていくうえで大切な能力です。八方ふさがりのように見えても、相談してみたら何かしら突破口が見えてくるものです。家賃を滞納する前はもちろん、滞納してしまった後でも、この記事を参考にして身近な相談先に相談してみてください。
教えてくれたのは?
取材・文:CHINTAI編集部
協力:生活保護問題対策全国会議