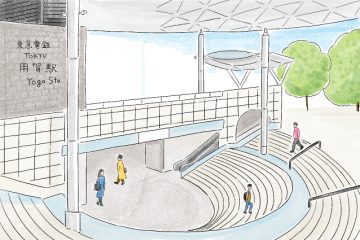【初めて猫を飼う人へ】猫と一日も早く家族になるための基礎知識
始めよう!幸せいっぱいな猫との暮らし
忙しく動き回る人間たちを一瞥しながら、我関せずとのんびり寝ているニャンコを見かけるたび「猫になりたい……」と思う今日この頃。知り合いの猫好きは「現世でたくさん徳を積むと来世は猫になれるらしいよ」と、まことしやかに語っていた。
愛猫家だったSF作家のロバート・A・ハインラインも「この世でどう猫に接したかで、天国でのステイタスが決まる」との言葉を残している。猫を愛すれば徳と積めるということか? ならば大いに猫と戯れながら、徳を積んで来世は猫になろう!
それはさておき、癒しとハピネスに満ちた猫との暮らしを夢見ている人は多いはず。初めて猫を飼うなら知っておきたいことを、長年にわたって猫の健康寿命アップを探求している獣医師の野澤延行さんにお聞きした。

このページの目次
まずは猫の体・習性・能力について理解しよう
猫が人間と暮らすようになったのは、農耕文化が発達した古代エジプト時代に穀倉のネズミ捕りとして飼われたのが始まりと言われている。
日本に猫が入ってきたのは6世紀半ば。仏教伝来にともない、経典をネズミ被害から守るために中国から連れてこられた猫が土着したとされているが、それ以前にも中国との交流はあり、正確なところはわかっていない。現在はペットとして人に飼われるようになった猫だが、その体や習性などには狩りをして生きていく機能が残っている。

猫の体
素早く高いところへジャンプしたり、まん丸くなって鍋に収まったり、ゴムのように伸びきったり、猫の動きは見ていて飽きない。

▼視力
人間で言うと0.3くらいで輪郭がややぼやけて見える程度。しかし、光の感度は人間の6~8倍で真っ暗闇の中でも難なく行動できる。動体視力もバツグン!
▼嗅覚
母猫の乳首を探るため、生まれた時から発達している。他の個体のニオイに敏感で、人間には感知できない猫特有のニオイで世界を作り上げている。
▼ヒゲ
ヒゲの根元には神経が集中し、風向きの変化などをキャッチするアンテナの役割をしている。ヒゲに異物が当たると反射的にまばたきが起きる。
▼歯
生後3~4週で犬歯から生え始め、8週目には上下20本が生え揃い、3~4か月から永久歯に生え変わる。全ての歯が尖っていて、肉を引きちぎるのに適している。
▼味覚
人間より鈍いものの、甘い、苦い、酸っぱいなどは分かる。猫になめられるとザラザラするのは、舌の表面に糸状乳頭という突起が生えているから。
▼聴覚
微細な低周波から9万ヘルツ以上の超音波まで聴こえている。耳には20以上の筋肉があって、音のする方向へ自由自在に動かすことができる。
▼知能
人間で言うと2歳児くらい。本能や欲求をつかさどる大脳辺縁系と、平衡感覚や運動能力をつかさどる小脳が発達している。猫は犬より知能が低いと思われがちだが、犬のように命令を聞く習性がないだけで、脳の発達具合は大差ない。

猫の習性
野生時代から単独で生きてきた猫は、とにかくマイペース。遊びたい時に遊び、甘えたい時に甘え、食べたい時に食べ、人間の思い通りになんか行動しない。
縄張り意識が強いのも、単独行動を好むがゆえの習性。野良猫はもちろんのこと、室内飼いの猫も出入り可能な室内全体を自分のテリトリーとし、毎日のパトロールを怠らない。壁に体をこすり付けたり、爪とぎをしたりなどの行為でマーキングをして「ここはアタシ(ボク)の場所!」と主張する子もいる。

ハンターとしての能力もズバ抜けている。チャンスが来るまで辛抱強く待ち伏せし、そっと忍び寄りながら距離が縮めて一気に飛びかかる。生きた獲物に出くわすことがほとんどない室内飼いでも、飼い主の足やヒラヒラ揺れるオモチャなどに反応を示す。猫が動くものに飛びついてしまうのは「動くもの=動物性たんぱく質=獲物」と本能に刷り込まれているため。
「猫という呼び名は〝寝子〟から付いた」とされるほど、猫は一日のほとんどを寝て過ごす。生後3か月未満の子猫だと20時間以上、成猫でも平均16、7時間は寝ている。しかし、大半はうたた寝で、物音や光を感じれば起きて反応する。寝床を用意してあげる際は、静かでニオイや光などの刺激が少ない場所を選ぼう。
半夜行性動物の猫がもっとも活発に行動するのは夕暮れと明け方。狩りをしていた野生時代の習性とされている。猫との生活に慣れるまでは、早朝の大運動会で起こされて寝不足が続くことだろう。
猫は顔を覗き込まれると、必ずと言ってよいほど目線を逸らす。それは「アナタに敵意はありません」という意思表示。可愛い顔を撮りたくてカメラを向けてもそっぽを向いてしまうのも同じ理由。猫にとってカメラレンズは〝目〟に見えているのだ。むしろ鋭く見つめ返してきたらケンカする気満々だと言うこと。

猫を迎える前に用意したい必須アイテム4点
猫の行動範囲はサッカー場の1.5倍とも、家を中心に直径500メートル前後とも言われている。
しかし、室内飼いが主流となった今、ほとんどの猫は外に出ることなく、家の中だけで暮らしている。安全と食事は保証されているけれど、猫にとっては制約も多いはず。そのような状況で、猫ができるだけストレスなく過ごせる環境をつくることは飼い主の大事な役割。
まずは、初めて猫を迎え入れる時に必ず用意してほしいもの、初日は無理でも早めに揃えておきたいものをご紹介しよう。

猫を迎える前に用意したいアイテム①:清潔なトイレ
猫は部類のキレイ好きに加え、人の数万~数十万倍と言われる嗅覚の持ち主。ゆえに、トイレは〝清潔感〟が最重要となる。そして、野生時代の名残りで〝無防備になる排泄中は危険が多い〟と感じてしまうため、他のニオイがしない、静かで落ち着いた場所での用足しを好むので〝置き場所〟にも気をつけてあげたい。トイレが気に入らないと排泄を我慢してしまい、膀胱炎や尿路感染症などのリスクが高まるので要注意!
トイレの大きさは体長(頭から尻尾の付け根まで)×1.5倍以上が理想的。成長するにつれて市販されているトイレが窮屈になる場合は、プラスチック製の衣装ケースなどを活用してみよう。容器の縁が高い場合は踏み台を用意してあげて。
トイレの数は匹数×1.35個で計算すると良い。例えば、2匹なら3個(2×1.35=2.7)、6匹なら8個(6×1.35=8.1)。
猫は割と簡単にトイレの場所を覚えてくれる。床に鼻をつけて嗅ぎ回ったり、ソワソワし始めたりしたトイレのサイン。すぐトイレのある場所に誘導してあげよう。
トイレ掃除は週1回、ケースを丸ごと熱湯消毒するのがベスト。砂もこまめに取り替えよう。※耐熱素材であることを確認してから行なうこと

猫を迎える前に用意したいアイテム②:ヒゲの当たらない食器
猫はデリケートで、食器が気に入らないと食欲をなくしてしまうことがある。フード皿や水容器は〝ヒゲが当たらない(底が浅くて口径が広い)もの〟〝安定してグラつかないもの〟を選ぼう。
材質や床からの高さは好みによってさまざまなため、いくつか試してストレスなく使ってくれるものを見つけよう。食器からフードを咥えて好きな場所に持ち出して食べる〝持ち出し食い〟、前足でフードをかき出して食べる〝かき出し食い〟といった変な食べ方をしていたら、食器がお気に召さないサイン。
ちなみに、猫好き絵師で知られる歌川国芳の浮世絵をよく見ると、猫が〝アワビの殻〟で餌を食べている。夏目漱石の『吾輩は猫である』にも〝アワビ皿〟を使っている描写が出てくる。安定感があり、深さもちょうど良かったのだろう。ただし、生のアワビの内臓には猫の耳を壊死させる毒素があるため、絶対に食べさせてはいけない。

猫を迎える前に用意したいアイテム③:フード
市販のキャットフードには大きく分けて『総合栄養食』と『一般食』の2種類ある。総合栄養食はペットフード公正取引協議会が証明したフードで、猫に必要な栄養が全て含まれているので、あとは新鮮な水さえあれば生命を維持できるというもの。
一般食は食欲がない時などのカロリー補給などに与えるもので、それだけでは栄養が偏ってしまう。ウェットタイプは見た目がそっくりなので、パッケージ表記をしっかり確認して購入しよう。
なお、肉食動物である猫は動物性たんぱく質を好み、その味覚も良質のたんぱく質を感知する能力が高いとされている。キャットフードを選ぶ時は第一原料(もっとも多く使われている原材料)が肉もしくは魚であることが大切だ。
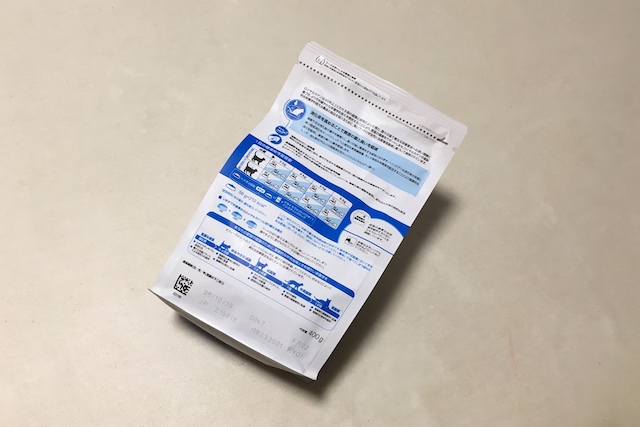
口ケアができるのは嬉しいポイントだ。
猫を迎える前に用意したいアイテム④:ベッド
生後2ヶ月前の子猫であれば、ケージ内で食事・トイレ・睡眠のすべてが行えるようにしておく必要がある。それ以降は、可能であればベッドを用意してあげよう。猫ベッドは、
猫がホッとできるパーソナルスペースになるからだ。
猫ベッドは日当たりの良い場所や、棚の上など人間の視線が気にならない場所など、猫の好みを探しながらいろいろな場所に猫ベッドを置いてみよう。
猫ベッドにはたくさんの種類の形があり、人間が「愛猫にぜひ使ってほしいと思って買ったのに使ってくれなかった!」ということもザラにある。夏用にはひんやり素材のものを、冬用にはフリース素材のものなど、季節で使い分けると洗濯もできて一石二鳥なので、いろいろ買ってみることをおすすめする。
早めに揃えたい猫アイテム
猫の爪は薄い層がいくつも重なっている。壁や柱をガリガリと引っかくのは古くなった表層の爪をはがしたいから。また、足の裏のニオイをつけて縄張りを示すマーキングの意味もある。
いずれも本能ゆえ止めさせることはできないので『爪とぎ板』を用意してあげよう。材質は縦方向に長い繊維で構成されている針葉樹を好む猫が多い。置き場所は日当たりの良いところがおすすめ。
猫は高低差を必要とする動物。タンスや本棚など背の高い家具の上には不要なものを置かず、猫が『見張り台』や『寝床』に使えるスペースを作ってあげると◎。高さの違うカラーボックスを『階段』状に配置するだけでも喜んで上り下りする。
和室の場合は鴨居に長い板を渡すだけで『キャットウォーク』に。ただし、猫が飛び乗ってもグラグラしない丈夫な板を使い、鴨居から絶対に外れない工夫を忘れずに。
ハンターの血が流れている猫は〝狩りごっこ〟が大好き。虫や小動物に似せた『猫じゃらし』、獲物を捕らえた時のように思いっきりキックができる『蹴りぐるみ』などを用意して、その狩猟本能を満たしてあげよう。
猫じゃらしで遊んであげる時は、いかに本物らしく動かせるかがポイント。ネズミの動きのように低速・中速・高速を交えながら動かす〝変速送り〟、バッタやカエルにようにピョンピョン不規則に跳ねさせる〝跳ね飛び〟、弱った獲物風にゆっくり小刻みに動かす〝チョロリ足〟などで、ワクワクさせよう。

次は、猫と家族になるための【医・食・住】についてご紹介!
猫と家族になるための【医・食・住】
本記事では、長年にわたって猫の健康寿命アップを探求している獣医師の野澤延行さんに取材。初めて猫を飼うなら知っておきたいことを紹介している。
猫の健康維持には〝清潔〟〝食事〟〝コミュニケーション〟が不可欠。キレイ好きな猫は元々セルフグルーミングが得意だが、人間が手伝ってあげれば美しさも清潔感もアップする。
そして、室内飼いの猫は飼い主が用意する食事だけで命をつないでいることを忘れずに。コミュニケーション不足で欲求不満やストレスがたまれば、猫だって肥満や生活習慣病になる。
【医】猫の抜け毛について
猫の被毛には〝オーバーコート〟と〝アンダーコート〟があり、それぞれ役割が違う。オーバーコートは体の表面を覆っている毛のことで、撥水性があり、紫外線から皮膚を守っている。アンダーコートはオーバーコートの内側に生えている細く柔らかい毛のことで、猫の体温調整をしている。
春と秋が猫の換毛期。特に春は、暑い夏に向けてアンダーコートを脱ぐため、大量な抜け毛が出る。秋の換毛も冬に向けての準備だ。
ブラッシングの道具には、コーム、獣毛ブラシ、ラバーブラシ、スリッカーなどがある。ラバーブラシは面白いほど毛が良く取れ、ブラッシングとマッサージも兼ねるのでおすすめ。獣毛ブラシは猫が肌触りを喜び、マッサージ効果も期待できる。スリッカーは細い針金状なので毛は良く取れるが、その肌触りを痛がる子も。
皮膚と被毛の状態は猫の健康のバロメーター。毎日のブラッシングを習慣にすると、猫の体を清潔に保てるだけでなく、毛ヅヤと毛並みの変化で体調に気づくことができる。お互いの親密度を深めるスキンシップの役割も大きい。

【食】猫にご飯をあげるタイミング
猫にとっても食べることは喜び。しっかり美味しく食べることが健康維持につながる。味よりもニオイで食べるかどうかを判断していたり、完食せず、ちょっとだけ皿に残す〝猫残し〟をしたり、猫には独特の食習慣があることにも注目したい。
〝猫残し〟をする理由は、猫の胃が小さいことと関係している。お腹をいっぱいにして動きが鈍くならないよう、小分けに食事をしていた野生時代の名残りだ。
猫は環境への順応性が高いので、ご飯をあげるタイミングは飼い主のライフスタイルでさまざまなケースが考えられる。理想としては、フードが酸化せず、ニオイが新鮮なうちに食べ切れる量をこまめに用意してあげたいところ。一人暮らしで日中は猫の面倒を見られない場合、一日に必要なフード量(ドライタイプ)を朝と晩の2回に分けて与えてみよう。
フードとともに新鮮な水もたっぷり用意してあげよう。犬と比べて猫は水をあまり飲まない動物だが、膀胱炎などの病気を防ぐためにも水分は積極的にとらせたいところ。水容器を部屋のあちこちに置いたり、ウェットタイプのフードを取り入れたりするなどの工夫を心がけて。
猫に与えてはいけない食べ物には、ネギ属(ネギ、タマネギ、ニラ、ニンニクなど)の野菜、アワビ、サザエ、チョコレートなどがある。ユリ、ポトス、アサガオなどの植物も気をつけて。これらには猫が中毒を起こす成分が含まれているからだ。

【住】猫と信頼関係を築く方法
猫の行動はいつもマイペースで自由気まま。その気ままに見える行動にも、猫の習性や気分によって、ちゃんと理由がある。そして、いろいろなサインを出していることにも気づくだろう。猫と信頼関係を築くには、このサインを見逃さないことが大事。
猫の〝すりすり〟行為はニオイ付け。自分のニオイをこすりつけて、自分の縄張りであることを確認し、安心しようとしているのだ。飼い主の足にすり寄るのは「アナタはアタシ(ボク)のもの!」という愛情確認。「私もキミが大好きだよ!」とやさしく応えてあげよう。
毛布や飼い主のお腹の上で、せっせと前足を交互に動かして〝ふみふみ〟してくる時は、子猫時代にお母さんからおっぱいをもらっていた頃の気分になっている。〝甘えたいモード〟に入っているので、思いっきり触れ合ってあげよう。
猫に限らず、動物は他者にお腹を見せたり触られたりするのを嫌う。柔らかいお腹は敵に攻撃されたら致命傷を受けかねない部分だからだ。猫がお腹を見せてくれるようになったら、飼い主に信頼と安心を感じている証拠。触っても猫が嫌がらなければ、やさしくマッサージをしてスキンシップを図ろう。

猫と仲良くするキーワード「ねこはときめく!」
最後に、野澤さんが教えてくれた〝ねこはときめく〟というキーワードをお伝えしよう。『ね』は寝る、『こ』はコミュニケーション、『は』は話しかける、『と』はトイレを清潔に、『き』は距離を保って、『め』は目出し窓で世界に触れさせる、『く』は空間を与える。
猫がのんびりマイペースに、できるだけ自由にストレスなく、家族の愛情がほど良く伝わることが、猫の健康寿命を延ばすことにつながるという。
猫を家族に迎えたい人は、この〝ねこはときめく〟を標語のように覚えて、猫も人も幸せな毎日を目指そう。
取材・文・写真=野中かおり
猫モデル=野中珠次郎(元・野良猫。右目に障害があるけれど元気いっぱい!)
2021年5月加筆=CHINTAI情報局編集部