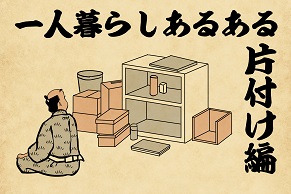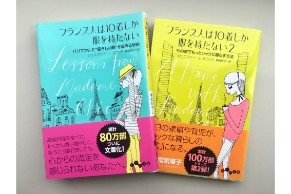【一人暮らしの防災対策・火災編】火事の原因は?事前対策を行い、安心な生活を!
一人暮らしだからこそ、火災に対しての意識を強く持とう
火の元点検を忘れて外出し留守中火事が起きると、自分だけでなく周囲に大変な迷惑をかけ、一生後悔するとともに、取り返しのつかないことになる。複数人で暮らしていれば、自分が起こしたボヤ騒ぎも誰かが気づいて大きな火災にならず済むかもしれない。しかし、一人暮らしだとそうもいかない。
火災の歴史を紐解いてみると地震発生時の火災を除き、火元の点検ミスで火災に至るケースがほとんどだ。火災に配慮した製品が増えたおかげなのか、ここ10年間火災は減少傾向にあるものの、住宅火災による死者数は総死者数の約61%と非常に高い割合を示している。
いつ自分の身に降りかかってくるかわからない火災。対策と対処法を知っていれば、最悪の事態は防げるかもしれない。

このページの目次
火災の事前対策その1:火災の原因、時期、時間を心得る
大多数の火災は、だいたい下記の4つが原因のことが多い。
- 冬季に使用するストーブやこたつ
- タバコ
- コンロやマッチ・ライター
- 電灯・電話等の配線機器
火災の多い時期は、意外にも春先の3月が一番多く次に5月が多い。意外な結果だ。時間帯もまたしかり。多くは午前から午後にかけて火災が起こっている。しかし、夜中も一定件数の発生があるのだ。
「冬も過ぎたから大丈夫」「食事時でもないし大丈夫」という気のゆるみが火災につながっているのかもしれない。気を抜かず常に上記の異常がないか点検を行うことが大切だ。
火災の事前対策その2:日常生活に対策を取り入れる

室内環境を変える
室内にはカーテンなど不燃性の素材を活用し、燃えにくい室内環境整備に努めよう。住宅用万が一に備え、住宅用火災警報器、消火器などを設置し、避難用の非常持ち出し袋も用意しておこう。この際、特に季節に応じた内容品や病気やアレルギー等個人の持つ特性に留意した内容品を準備しておこう。
チェックリストを作り点検を習慣化する
火災を起こさないために火気使用後、就寝前、外出前の点検を習性化しよう。点検を忘れないために、わかり易い場所に火気点検のチェックリストを置こう。
講習会や訓練に参加して防火能力を高める
火災講習会、消火訓練に参加し、消火知識と技能を習得して防災能力を高めよう。また、地域などで行われている消火訓練、通報訓練、避難訓練などの消防訓練に参加すれば、連携した訓練要領を習得することもできる。
避難場所、経路を確認しておく
防災マップを参考に避難場所、避難経路を複数確認する。なお、東京都では、火災が発生しても地区内に大規模な延焼火災のおそれがなく、広域的な避難を要しない「地区残留地域」が指定されているため、参考にしてみよう。
避難場所等の概要(東京都都市整備局)
地域と連携する
一人暮らしだと地域と連携することは難しいと考えている方も多いが、あなたも地域の一員。できれば、地域住民と気象情報、火災情報と各種情報を参考に住宅の防災委員等と情報交換をしよう。避難方法等についても打ち合わせを行い、防災マニュアルで定めた組織と役割、実施手順に従って担当を割り振れると良い。
いざというときにさっと使える「防災セット」を用意しておく。
万が一、火災が起きてしまった場合、自力で身を守るしかない。そこで揃えておきたいのが防災グッズ。火災以外の地震や台風などの災害対策としても有効なのでぜひ用意しておこう。
火災の事前対策その3:大火を知る
大火は、延焼を促進する強風や大地震などの気象現象と火災が同時に発生した際、消防力が不足し火災が大火へと発展する。下記の3項目をチェックし、大火が発生しやすい地域かそうでない地域か見極めよう。
・季節風やフェーン現象により強風が多く発生する地域かどうか
・地元消防の消防力はどれくらいか
・家の周りに木造建築物が多くないか
(東京都では一定の条件で木造家屋が多い地域を木造密集地域として指定している。東京都木造住宅密集地域整備事業:実施地区一覧表(東京都都市整備局))
上記情報は収集に手間がかかったり、自分で判断をするには難しい。しかし住む街について普段から情報を集め気を配っていればおのずと見えてきそうだ。
大火が発生しやすい地域に住んでいた場合は、地震による強い揺れを感知して電気を遮断することができる「感震ブレーカー」の設置を行うなど対策を強化しよう。
火災の事前対策その4:やってはいけないことに注意を払う

寝たばこ
ベッドサイドに灰皿を置き、横になりながら吸うことで、火が完全に消えずやがて火事に発展することが多くみられる。
コンセントのタコ足配線
過大電流が流れるため危険。どうしても使わなければいけない場合は、機器の電気使用容量を確認しコンセントを使用しよう。
配線に断線や傷み、プラグなどに破損がないかきちんと注意を払うことが重要だ。
火を扱っている時にその場から離れない
特に煮焚き物の場合、空炊きになったりして火災の原因となる。
ストーブの周りに物を置く
物が乾燥し、火事が起きやすくなるため要注意だ。
もし、火災に遭ってしまったら
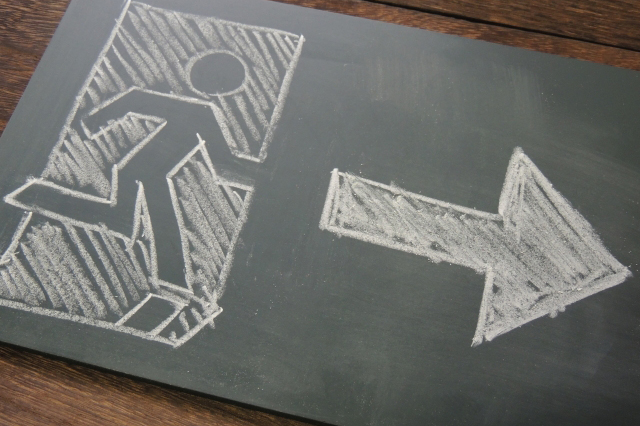
万が一火災が発生した場合は、大声で“火事だ”と叫び、消火器で初期消火に努めよう。
もしも火が天井まで届くようになった場合は、危険なので消火活動を断念し速やかに避難しよう。避難する際は、濡れたタオルで口を覆い低姿勢で煙を吸わないように部屋を出たら、ドアを締めて避難したのち、近隣の人に救助を求める。
多くのサイレン音、消防車両の火災場所への移動、TV等から火災発生の情報を得ることも忘れずに。火災に巻き込まれる恐れがある場合は、風向き・風速、火災の延焼状況、避難情報等の各種情報を見極め、早めに火災の風下を横切る方向に避難しよう。その後、一時集合場所(いっときしゅうごうばしょ)へ向かい、そこが危険となった場合は広域避難場所へ避難する。
この際、避難にあたっては近所の方へお声掛けし、要配慮者がいる場合は、避難に協力しよう。
火災はいつ起こるかわからない!一人暮らしだからこそ、事前の対策を
「自分は大丈夫だ。」と過信せず、事前対策を行おう。
また、火災が起きた際は、自分は地域住民の一人だという自覚を持ち、地域住民と協力して、消火や避難活動をしよう。
文=今野茂雄
陸上自衛隊幹部自衛官を退官のちに様々な経歴を経て現在は、NPO法人 日本防災環境顧問兼専務理事を務める。防災及び国民保護に係る講演や防災計画及びマニュアルの作成、防災図上訓練(ロールプレーイング、DIG、HUG)を行っている