119番マニュアル!救急車を呼ぶタイミングと必要なもの
もしものとき救急車を呼ぶ基準は?
急な体調不良に見舞われた場合、救急車を呼んでいいのか迷っているうちに悪化する危険性もある。そんなときに慌てないためにも、救急車を呼ぶ基準について事前に知っておこう。今回は、救急車を呼ぶかどうか迷ったときに相談する連絡先、救急車を呼ぶ基準、呼ぶときの準備などについて解説していく。
このページの目次
救急車を呼んでいいのか迷ったときは#7119に電話しよう

急に体調が悪くなったとき、一人暮らしだと相談できる家族や同居人がいないので心細くなるだろう。不安を打ち消すために、「寝ていれば治る」「心配することはない」と楽観的に考えたくなるかもしれない。日中なら病院に行こうと思えるが、診療時間外の夜間は判断に迷うもの。
とはいえ自己判断は禁物だ。そんなとき、東京消防庁が実施している「#7119(救急相談センター)」なら医療の専門家が24時間年中無休で相談に乗ってくれるので心強い。ただし、実施エリアは北海道の一部・宮城県・茨城県・首都圏・新潟県・関西地方の一部・鳥取県・九州地方の一部など、利用できるエリアが限られているため確認が必要だ。
また、「Q助」の愛称で知られる、総務省消防庁の「全国版救急受診アプリ」も便利である。こちらは症状を選択すると緊急度が表示されるサービスで、スマートフォンやパソコンから利用できる。
エリア外の場合は地域の医療センターの相談窓口に連絡しよう
「#7119(救急相談センター)」を実施していないエリアに住んでいて、救急車を呼んでいいのか迷った際には、厚生労働省の「医療情報ネット(地域の一般救急電話相談)」を利用しよう。
これらのサイトには、各都道府県の「お医者さんガイド」のリンクが張られている。医療機関の基本検索だけでなく、外傷・腹部の強い痛み・やけど・子どもの病気といった、急に現れた症状別に相談できる医療機関の連絡先も検索することが可能だ。
休日・夜間に子どもの症状で判断に迷ったら♯8000に電話しよう
子どもは身体も小さく、そして大人より免疫力が低いという特徴がある。休日や夜間に突然発熱したり、けいれんしたりすることも珍しくないため、そのような場合は「#8000(子ども医療電話相談)」を利用しよう。
こちらの番号は全国同一となっており、自動的に居住地の都道府県の相談窓口に転送される。相談の受付曜日は基本的に土日祝(日祝のみの場合もあり)、時間帯は19時~翌朝8時というところが多いが、エリアによっては24時間365日体制のところもあるようだ。万が一の場合に備えて、メモ帳などに番号を控えておくとよいだろう。
緊急を要する場合はためらわずに救急車を呼ぶ

症状が緊急の場合はすぐに119番へ。オペレーターに「火事ですか?救急ですか?」と聞かれるので、「救急」と答えて症状を伝えよう。自力で病院に行くことができるかどうか聞かれることもあるが、急病であれば無理をせずに救急車の出動を頼んだ方がよい。
住所・氏名・年齢・持病・アレルギーの有無・服用している薬・かかりつけ医の所在などを聞かれることがあるので、あらかじめまとめておくと安心だ。なお、こちらの電話番号は相手が自動探知しているが、意識の確認のために聞かれることもあるので、自分の番号も答えられるようにしておこう。
119番の電話を切った後は、部屋で待機する。意識を失う心配がある場合は、防犯上の注意が必要だが、先に鍵を開けておくのも1つの方法。意識に問題がなさそうであれば、救急車のサイレンの音が聞こえたり、救急隊からインターフォンや電話で連絡が来たりしたタイミングで解錠しよう。
救急車を呼ぶほどではないが病院に行きたい場合は、地域の民間救急コールセンターに連絡して、有料の民間救急車を利用してもよいだろう。
救急車を呼ぶ基準|こんな症状はすぐ「119」番に連絡しよう
症状を自覚できる大人と、自覚しにくい子ども・高齢者では、救急車を呼んでいいのかどうかの基準が少々異なる。対象が子どもや高齢者の場合は、周りの大人が判断する必要が出てくるため、救急車を呼ぶそれぞれの基準を知っておこう。
【大人の場合】の救急車を呼ぶ基準
大人の場合、以下のような症状が見られる場合はすぐに救急車を呼ぼう。
- 顔:顔半分が動きにくいまたはしびれる、笑ったときに顔の片方がゆがむ、ろれつがまわりにくくうまく話せない
- 頭:突然の激しい頭痛や高熱、支えなしでは立てないぐらいのふらつき
- 胸や背中:突然の激痛、急な息切れや呼吸困難、胸の中央が締め付けられるような痛みが2~3分続く
- 手や足:突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らない
- おなか:突然の激しい腹痛、吐血、血便、真っ黒い便
- いつもと違う症状:意識がない、ぐったりしている、強い吐き気、けいれんが止まらない
参考:「救急車利用リーフレット 成人版」|消防庁
【子どもの場合】の救急車を呼ぶ基準
子ども(15歳以下)の場合は以下のような症状が挙げられる。いつもと様子が違っておかしいと判断したら、すぐに119番で救急車を呼ぼう。
- 顔:くちびるが紫色、顔色が明らかに悪い
- 頭:頭を痛がってけいれんがある、頭を強くぶつけて出血が止まらない
- 胸:激しい咳やゼーゼーして呼吸が苦しそう、呼吸が弱い
- おなか:激しい下痢や嘔吐による脱水症状、激しい腹痛、嘔吐が止まらない、血便
- 手や足:手足が硬直している
- いつもと違う症状:意識がない、もうろうとしている、けいれんが止まらない、虫刺されで全身にじんましんが出ている
参考:「救急車利用リーフレット 子供版」|消防庁
【高齢者の場合】の救急車を呼ぶ基準
高齢者は自覚症状がない場合も多い。以下のような症状が出ていたら、周りにいる人はすぐに119番で救急車を呼ぼう。
- 顔:顔半分が動きにくい、笑うと顔の片方がゆがむ、ろれつがまわりにくい、見える範囲が狭くなる
- 頭:突然の激しい頭痛や高熱、急にふらつき立っていられない
- 胸や背中:突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、痛む場所が移動する
- 手や足:突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなる
- おなか:突然の激しい腹痛、吐血
- いつもと違う症状:意識がない、もうろうとしている、強い吐き気、食べ物をのどに詰まらせた
参考:「救急車利用リーフレット 高齢者版」|消防庁
ここからは、救急車の到着までに用意しておいた方が良いものを解説する。
救急車の到着までに財布や保険証を用意しよう

救急車が到着するまでに用意しておきたいものは、財布、健康保険証、常備薬、お薬手帳、携帯電話などだ。ただし、一人のときは安静にするのがベストなので、健康に直結するものは日頃からすぐ持ち出せるようにまとめて準備しておこう。ここでは、最低限そろえておきたい持ち物を順に紹介する。
救急車の到着までに用意するもの①:財布
夜間などの診療時間外は保険診療の会計ができないため、通常の診察よりも高額になる。後で差額分を返金してもらえるが、できれば現金は多めに用意しておきたい。
救急車の到着までに用意するもの②:保険証
保険診療ができない時間でも身分証明書代わりとして使用できる。アレルギーを持っている人や、服薬中の薬がある人はぜひ参考にしてみてほしい。
救急車の到着までに用意するもの③:常備薬
すぐに帰宅できない可能性もあるため、常備薬を用意しておく。服薬している薬の種類によっては受けられない検査もあるので、病院に着いたらその旨を医師に伝えよう。
救急車の到着までに用意するもの④:お薬手帳
持病やアレルギーがある人は、特に用意しておいた方がよい。アプリ版のお薬手帳を使うと手軽に管理できる。
救急車の到着までに用意するもの⑤:携帯電話
連絡手段や情報ツールとして欠かせないものだ。家族に緊急連絡が必要になる場合に備え、肌身離さず持っていたい。搬送された病院で検査や治療を終え、帰宅ルートを調べるときなどにも便利だ。
行きは救急車でも帰りは自力で帰る必要がある
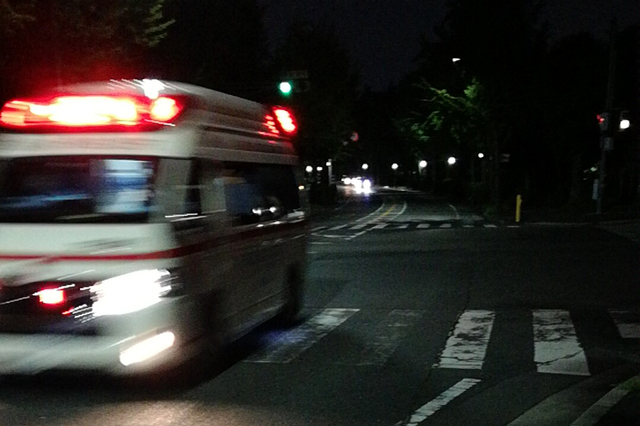
救急車に乗ると、休日や夜間の急患を受け付けている地域の救急病院に搬送されるケースが大半。当直の医師による診察や検査が行われ、症状によっては時間がかかることもある。帰宅するときに電車やバスが運行していなければ、家が近くであってもタクシーを呼んだ方が安心だ。
仮に一人で来ていて入院することになった場合、家族や友人に早めに連絡しておこう。大きい病院であれば院内で着替えや生活用品を購入できるが、入院期間によっては一旦自宅に帰って用意した方がいい場合もあるだろう。
救急車を呼ぶ基準を知りもしものときに備えよう
万が一に備えて、救急車を呼ぶ基準となる症状や、救急車の利用の流れをシミュレーションして覚えておきたい。また、一分を争う緊急時に必要な知識や情報を整理することと同じくらい、普段から健康でいられるような毎日を送ることも大切だ。
2021年8月加筆=CHINTAI情報局編集部






















