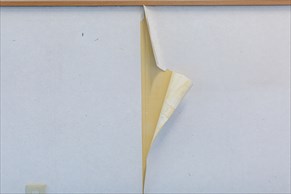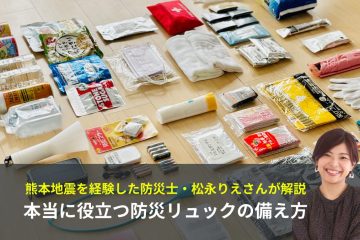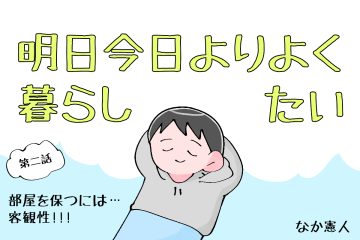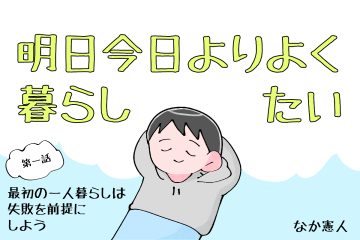引越し後、前の住所に届く郵便は転送できる? 住所変更などの手続きのしかたを解説!
引越し後、新居で郵便物を受け取る方法とは?

引越しをしたら、届く郵便物はどうなるの? と疑問を持つ人も多い。
仮に大事な郵便物が旧住所に送られてしまい、受け取ることができなくなっては困るだろう。
このような事態を避けるためにも、引越し時はぜひ郵便局の「転居・転送サービス」を利用しよう。
今回は、郵便の転居・転送サービスについて、手続きの仕方や注意点を詳しく説明していく。
▼引越しの手続きについてはこちらも合わせてチェック!
このページの目次
引越し後は郵便局にも「転居届」を提出する必要がある
引越し後、特に何もしないと郵便物がそのまま旧居に届いてしまうため、引越しのときは郵便局に転居届を提出しなければならない。これにより、提出日から1年間郵便物の転送サービスが無料で受けられる。引越し後に旧住所宛てに郵便物が送られてきた場合でも、新住所に送ってもらえるのだ。
世帯単位で引越しの場合は、一度の登録で6人分の登録ができる。家族のうち、子どものみが進学や就職で引越しをする場合でも利用できるサービスだ。なお、通常の郵便だけでなく「ゆうメール」「ゆうパック」など郵便局が行うサービスにも対応しているため安心である。
住民票を移していない場合も、郵便局に転居届を出すことは可能!
手続き先が役所とは異なるため、住民票を移さない場合でも転送サービスは利用できる。さらに長期の入院の際にも利用でき、病院宛てに郵便物を送ってもらうこともできる。
引越し後も郵便物を受け取れる「転居・転送サービス」の申し込み方法
ここからは、転居・転送サービスの申し込み方法について順を追って解説していく。
転居・転送サービスの申し込み方法①:インターネットで手続きをする(e転居)

郵便転送サービスは、インターネットから申込手続きが可能。日本郵便のWEBサイト「e転居」から手続きができる。ただし、インターネットからの手続きは「ゆうびんID」の取得が必要になる。
| 手続き場所 | e転居のホームページ |
| 手数料 | 無料 |
| 必要なもの | ・PCやスマートフォン、携帯電話など、インターネットに接続できるもの ・ゆうびんID |
| 注意点 | 日本郵便株式会社社員による現地訪問や旧住所に確認書が郵送されることがある |
e転居の手続きの手順は以下のとおりである。
- スマホやパソコンからe転居画面を開く
- ゆうびんIDを取得していないときは、IDを発行する
- ログイン後、必要事項を入力する(パソコンから申し込む場合、携帯のメールアドレスは使えない)
- 転居届受付確認センターに電話
- 確認が取れたら手続き終了
転居・転送サービスの申し込み方法②:郵便局の窓口へ行く

郵便局の窓口で転送サービスの手続きをする場合は、窓口に備えられている「転居届」に記入して提出する。このとき、本人確認書類と旧住所が確認できる書類も一緒に提出する必要がある。
▽郵便局窓口での手続き
| 手数料 | 無料 |
| 手続き場所 | 郵便局窓口 |
| 必要なもの | 旧住所確認書類 ・運転免許証 ・パスポート ・住民基本台帳カードまたは住民票等 ・官公庁が発行した住所の記載があるもの 本人確認書類(個人の場合) ・運転免許証 ・健康保険証など 本人確認書類(法人の場合) ・社員証 ・健康保険証など ※本人と会社の関係がわかるもの |
| 注意点 | 日本郵便株式会社社員による現地訪問や旧住所に確認書が郵送されることがある |
本人確認書類は、個人の場合は運転免許証、健康保険証などが必要になる。会社・団体など法人の場合は、社員証、健康保険証など本人と会社との関係がわかるものを用意しておこう。なお、会社・団体で申し込む際は、代表者の名前の記入および捺印が必要である。
転居・転送サービスの申し込み方法③:転居届をポストに投函する

郵便局の窓口ではなく、郵便ポストへの投函で転居届を提出することもできる。郵便局であらかじめ転居届を手に入れ、必要事項を記入しポストへ入れれば完了だ。
投函する際、切手の貼付や本人確認書類などの同封は不要である。ただし、ポスト投函で転居・転送サービスを申し込んだ場合も、インターネットの場合と同様に本人確認が行われる。
| 手数料 | 無料(切手の貼り付けや記入は不要) |
| 必要なもの | 転居届(本人確認書類は不要) |
| 注意点 | 日本郵便株式会社社員による現地訪問や旧住所に確認書が郵送されることがある |
引越し後も郵便物を受け取れる「転居・転送サービス」を利用する際の注意点
ここからは、郵便の転居・転送サービスを申し込むときの注意点を確認していく。
申し込みから転送開始までに3~7日ほどかかる
転居サービスの利用開始までには、転居届を提出してから3〜7営業日を要する。そのため、引越す前に早めに手続きを済ませておこう。そうすれば、引越し後旧居に自分宛ての郵便物が届く事態を防ぐことができる。
転居届には、「転送開始希望日」を記入する欄があり、転送開始日を指定できる。行き違いを防ぐために、転送開始希望日は旧居の退去日までに設定しよう。ただし、逆に転送開始日を早く設定しすぎても、前の住人や大家さんに迷惑がかかる可能性があるため注意しよう。
転送期間は転居届を提出した日から1年間
転送サービスの期間は転居届提出日から1年間となっている。転送サービス開始日から1年間ではないので、必ず「転居届提出日」を確認しておこう。ちなみに、転送サービスをもう1年延長したいときは、再度届出をすれば延長が可能となる。
郵便の転居・転送サービスの期間を延長する方法は、以下の3つである。
- 日本郵便のWebサイト(e転居)から申し込む
- 近くの郵便局窓口で申し込む
- 郵便局に設置されている「転居届」を郵送して申し込む
日本郵便のWebサイト(e転居)から期間延長を申し込む場合、電話番号の確認が必要となるので、あらかじめ手元にスマートフォンなどを用意しておこう。
また郵便局の窓口や郵送を利用して期間延長する場合は、本人確認書類と旧住所が確認できる書類が必要になる。
「転送不要」の郵便物は届かないこともある
転送不要と書かれている郵便物は、基本的に宛名以外の人物や住所に渡ることはない。つまり、差出人が「転送不要」と記した郵便物に関しては、転送不可となり差出人へ返送されてしまう。国や自治体、金融機関が差し出す郵便物によく見られる。具体的な例は以下で確認しよう。
| 「転送不要」となる郵便物の例 |
|---|
| ・税金関連の納付書 ・銀行から送付されるキャッシュカードまたはクレジットカード ・保険会社からの保険料納付証明書 ・年金の通知書 ・口座確認書類 ・国民健康保険証 |
上記で挙げたものは、個人情報が記載されている重要書類である。受け取るには正しい住所の登録、居住確認が必要となるため、転送不要の郵便物とされることが多いのだ。
大切な郵便物や通知がスムーズに届くよう、勤務先や金融機関など各種住所変更手続きは転送サービス期間中にしっかりと完了させておこう。
民間の宅配サービスを利用する荷物は転送されない
転送サービスはあくまでも郵便局に申請を出すものであり、民間の宅配サービスには適用されない。ただし、宅配業者によっては独自に転送サービスを実施しているところもある。
基本的に転居・転送サービスは途中で解除できない
転居届を提出すると、1年間は旧住所から新住所へ郵便物の転送が行われる。諸事情により旧住所へ荷物を配達してほしいということもあるかもしれないが、一度開始された転居・転送サービスは途中で解除・中止することはできない。
旧住所から新住所へ転送されている郵便物を旧住所で受け取りたいという場合には、改めて新住所から旧住所への転居届を提出することで、転送サービスを止められる。
郵便物の残り転送期間を確認する方法
前述のとおり、転送サービスの期間は「転居届提出日」から1年間となっている。転送期間の残りを確認するには、転居届を郵便局に提出してから経過した日数を数えればよい。
ただし、より正確な転送期間を確認したいのであれば、日本郵便の「転居届受付状況確認サービス」を利用するといいだろう。その際、事前に転居届受付番号を用意しておこう。
引越し後も大切な郵便物を受け取るために!転居・転送サービスを利用しよう
重要な通知やお正月の年賀状など大事なものをきちんと受け取れるよう、転居の際にはぜひ郵便の転居・転送サービスを活用しよう。ただし転送不可の郵便物もあるため、転送サービス期間中に各種住所変更手続きを行うことを忘れずに。
▼住所変更の他に引越し後にやることはこちらをチェックしよう
文=ブロック
2022年3月加筆=CHINTAI情報局編集部