児童手当や医療費助成、転園・転校の手続きも! 子連れの引越しTODOリスト
子供連れで引越しとなれば、手続きにも一苦労!
引越しで大変なのは、荷づくりや荷ほどきだけではない。転出(または転居)・転入届をはじめ、郵便局、水道や電気、インターネットに電話など、しなければいけない各種手続きがたくさん! しかも、これが子連れの引越しとなれば、手続きはさらに増えてしまう。
「書類の作成や提出は苦手……」という人こそ、早めにTODOを確認して締め切りを確認しておくのが吉。荷づくりは最後の気合いでどうにか間に合わせることができても、書類の不備や提出忘れは致命的。
そこで今回は子供関係で必要な手続きについて解説。TODOリストを作って漏れがないようにしておこう!

このページの目次
引越しが決まった! 子供関係の手続きの基本

引越しが確定したら、子供関係で“しなければいけないこと”は基本的に以下の3つ(※同一の市区町村内ではなく、別の自治体への引越しを想定)。
1. 現在通っている園や学校に引越しの予定があることを伝える
2. 旧住所の市役所等で転出に関する手続きを行う(転出の14日前から)
3. 新住所の市役所等で転入に関する手続きを行う(転入から14日以内)
学校関係(保育園・幼稚園含む)の手続きは、事務スタッフや担任の先生に手続きについて確認し、必要な書類を用意する。それ以外は、市区町村の役所・役場でほとんど完了する。転出届・転入届を提出する際に、「子供に関する手続きはどういうものがあり、どこの課でいつまでにするべきか」を確認すればOK。
具体的にはどんな手続きがあるのかは、以下の通り。
転出・転入時に行う、子供関連の各種手続き

子供関連の引越し手続き1、学校関係(未就学児の場合)
| 現在通っている園があれば、引越しの予定があることを伝えておく。 正確な新住所が決まる前でもOK。 | |
| 未就学児の場合は新住所での転園先を探し、直接空きがあるか確認。 | |
| パンフレットを郵送してもらうのは早めが吉。 | |
| 保育所(園)への入所(園)を希望する場合は、旧住所の市区町村が発行する所得課税証明書が必要になる場合も。 必要な書類について、転園先に問い合わせておきたい。 |
子供関連の引越し手続き2、学校関係(小学校の場合)の引越し手続き
| 現在通っている小学校(クラス担任)に、引越しの予定があることを伝えておく。正確な新住所が決まる前でもOK。 | |
| 最後の登校日に、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をもらう。旧住所で転出の手続きをする際にもらう「転出証明書」を学校に提出する。 | |
| 小学校の場合、引越し先の住所が決定しないと校区が定まらない。事前に転入先の教育委員会に連絡しておけば、必要な書類を送ってもらえることも。 | |
| 新住所で転入の手続きをする際にもらう「転入学通知書」と、前の学校でもらった「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を、転入先の学校に提出する。 |
子供関連の引越し手続き3、医療費関係の引越し手続き
| 「乳幼児医療費助成」「子ども医療費助成」による助成金額や利用方法は市区町村によって異なる。転出・転入の届出の際にしっかり確認する。 | |
| 予防接種がすべて終わっていない場合は、転入先の市区町村が発行する予防接種の「予診票」が必要になる。母子手帳で未接種のものをチェック。 | |
| 妊娠中の場合は「検診補助券」「妊婦・乳児健康診査受診票」、乳児がいる場合は「乳児検診の検診票」も転入先の市区町村のものが必要になるので用意する。 |
子供関連の引越し手続き4、児童手当の引越し手続き
| 旧住所で「受給事由消滅届」、新住所で「認定請求書」を提出する。認定請求書は転入した日から15日以内に提出する必要があり、遅れた月分の手当ては受給できない。手続きに必要な書類も、事前に確認しておきたい。 |
子供関連の引越し手続き5、子育て支援パスポート
| 各市区町村が発行する「子育て支援パスポート」は現在全国共通展開を進めているため、旅行中や帰省の際にも利用できるが、転居の際は返却をする。転入先の市区町村で改めて子育て支援パスポートを取得しよう。 |
子供関連の引越し手続き6、マイナンバーカードの住所変更
| 大人と同様、子供もマイナンバーカードの住所変更手続きが必須となるため、引越し際の役所で手続きを行う。必要な書類は免許証などの身分証明書や転出証明書、家族のマイナンバーカード、あるいは通知カードとなる。また、これらの書類のほかに印鑑が必要になり、引越しから14日以内に手続きを行わなければならない。 |
子供関連の引越し手続き7、その他
| 私立の小・中学校や高校の場合は、基本的に面接や転入試験が行われるため、入学願書や健康診断証明書の提出をする。 | |
| 全国展開の塾や習い事に通っている場合は、新住所近くの教室を紹介してもらえることもあるので、早めに相談する。 | |
| 自転車防犯登録や学資保険、子供名義の銀行口座などの住所変更も忘れずに行う。 |
子供連れで引越しをする際の3つの注意点
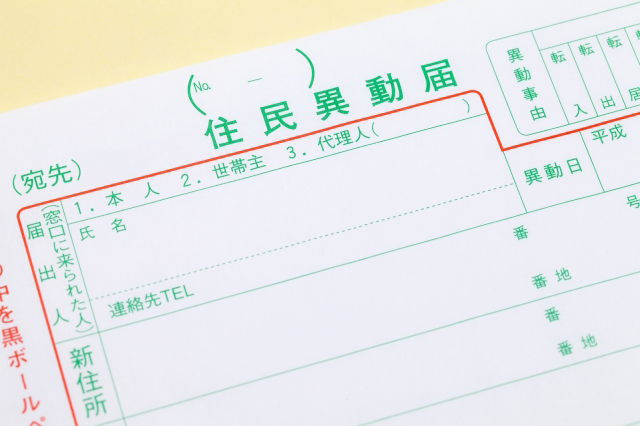
大人にとっても引越しは大きなイベントだが、子供にとっては大人の比ではないほど強い負担を感じることがある。引越した当日から、それまで感じたことがないようなストレスを受ける可能性もあるので、以下の3つの項目には深く注意しておきたい。
子供連れで引越しする際の注意点1、スケジュールや時間に余裕を持つ
子供連れの引越しでは特に手続きが多く、心身ともに疲弊しやすいため、普段はしないようなケアレスミスを起こす可能性は十分にある。ただでさえ役所で行う手続きには必要な書類が多く、申請方法もややこしいため、時間に余裕を持って行動することが重要だ。
申請が認められるギリギリのタイミングで手続きをした場合、何らかの不備があったときは申請が間に合わなくなることも考えられる。このような状況も想定して、期日までに余裕を持たせた行動を心がけることをおすすめする。
子供連れで引越しする際の注意点2、環境の変化による子供のストレスに注意する
乳児の場合、引越しによる環境の変化でストレスを感じ、夜泣きが増えたり、寝付けなかったりする場合がある。引越しの荷解きや片付けで忙しい中ではあるが、なるべく赤ちゃんのそばにいて、新居でも安心して過ごせるように気にかけたい。
また幼児や小学生以上の子供の場合、住環境が変われば、これまで気に入っていた公園で遊べなくなるし、顔なじみだった友達とも会えなくなる。友達を作り直すことになるので、不条理や理不尽を感じたり、ストレスを抱えたりすることも多いだろう。こういった問題をケアすることも、親の大事な役割の一つといえるだろう。
子供連れで引越しする際の注意点3、引越し先の小児科をリサーチしておく
以前住んでいた地域から遠く離れた場所に引越した場合、これまでのかかりつけだった小児科に通うことができなくなる。特に小さい子供の場合、夜中に突然熱を出すことがある。また、自宅で遊んでいるうちに思わぬケガをすることもあるだろう。
いざというときのために、引越し先が決まった段階で、いつでも相談できるような小児科に目星をつけておくことをおすすめする。新しい小児科を自力で探すことが不安ならば、今まで通っていた病院の先生に相談してみても良いだろう。
子供連れの引越しは事前に手続き内容の情報収集しておくと安心!
引越しにおける子供関係の手続きは役所での手続きがメインだが、マイナンバーカードがあれば電子申請も可能である。面倒でなければ転入先の役所に出向き、地域の子育て関連情報をまとめたパンフレットや、子育てサークルなどのチラシを入手するのも良いだろう。
転入先の子育て事情を知るためには、各自治体の役所や子育て支援センター、児童館などに足を運ぶのがいちばん。気になることがあれば相談窓口を紹介してもらえることもあるので、情報収集のためにもぜひ出かけてみて。
文=Spoo! inc.
2021年6月加筆=CHINTAI情報局編集部























