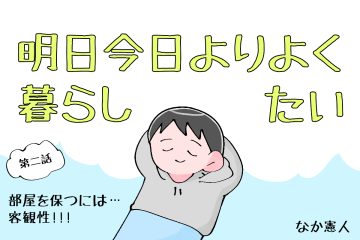賃貸でできる地震対策|地震への備え、家具の転倒防止対策とグッズを防災士が解説

2011~2020年に世界で発生したマグニチュード6以上の地震のうち、約2割が日本周辺で発生している(※1)。地震大国・日本に暮らす以上、自宅の地震対策は必須といえる。
ただし、「賃貸物件では壁に穴を開けられないから、家具の固定は難しそう」という声も。
そこで、熊本地震を経験された防災士・松永りえさんに、賃貸で暮らす人が「防災対策として無料で今すぐできること」や、賃貸物件でも導入できる「家具の転倒・落下被害を軽減する対策とグッズ」を伺った。
※1 出典:河川データブック 2024|国土交通省水管理・国土保全局(2-2-4 世界の活火山の分布)
防災対策はじめの一歩:災害に備えて、普段から「コミュニティ」を意識しよう
「地震への備えとして一番大切なのは、なにかのコミュニティに所属しておくこと」と松永さんは語る。例えば、ご近所さんや同じ職場で働く同僚、習い事やサークルの仲間、子どもの幼稚園・保育園のママ友やパパ友など、災害時に必要な情報を交換し、SOSを出し合える人と繋がっておくとよい。
「あの公園に給水車が来ている」「○○で炊き出しが始まった」などのリアルタイムの情報が、自治体の発表より早くコミュニティ内で得られる可能性があるからだ。
できれば自分の住む地域のコミュニティに属することがベストだが、難しければ職場の同僚や学生時代の友達など横のつながりをつくっておくと安心感が増える。一人暮らしの人も意識的に孤立を避けよう。
災害時は、自分からSOSを出すことも大切。「辛い気持ちを話せる相手がいる」というだけでも精神的に助けられるので、普段からコミュニティを大切にしましょう。
このページの目次
地震が起きる前に!0円で今すぐできる地震への備え
地震が起こった後は、ネット回線が混乱して災害情報を調べられないこともある。事前に自分の住む地域の災害リスクや避難所の位置、大切な人との連絡方法などを確認しておこう。
1.「重ねるハザードマップ」で地域の災害リスクを確認
住む地域ごとに、災害の種類は異なる。「津波の危険があるのか」「河川氾濫の可能性があるのか」など、ハザードマップで自分の住む地域が遭う危険性のある災害を調べておこう。
2.避難場所・避難所を確認
いざという時、どこに避難すればいいかは事前に調べておきたい。避難する場所には、下記の2種類がある。
避難場所と避難所の違い
指定緊急避難場所:災害の危機から命を守るために緊急的に避難する場所
例:対象とする災害の危険が及ばないグラウンドや駐車場、安全な構造の堅牢な建築物など
指定避難所:避難した被災者が一定期間生活するための施設
例:公民館や学校、体育館などの公共施設
災害発生時には原則として指定避難所ではなく、指定緊急避難場所へ避難する。また、避難場所・避難所の場所と避難経路は、国土地理院のホームページで確認できる。
避難場所の確認と経路を調べる|地理院地図の使い方 – 国土地理院
必ず一度は、平常時の夜間に防災リュックを持って指定緊急避難場所まで移動してみてください。
3.「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用伝言版(Web171)」の使い方を把握しておく
災害時、多くの人が電話やメールで連絡を取ろうとするので回線が混み合ってつながりにくくなる。そこで活用できるのが、各通信事業者が運営する以下のサービスだ。
災害用伝言ダイヤル(171)は、被災地への通信が増加してつながりにくい状況でも、安否情報を音声で録音・再生できる。一方、災害用伝言版(web171)では安否情報をテキストで登録・確認ができる。事前に使い方を把握しておくとよい。
NTT東日本のホームページでは、動画で使い方を紹介している。
災害用伝言ダイヤル(171) | NTT東日本
災害用伝言板(web171)ご利用方法|NTT東日本
※リンクはNTT東日本のものだが、東日本以外の地域でも使い方は同じ
災害用の伝言ダイヤルや伝言板は体験利用も可能。有事に備えて予行演習をしておきましょう。
災害用伝言ダイヤル(171)体験利用のご案内|NTT東日本
災害用伝言板(web171)体験利用のご案内|NTT東日本
※リンクはNTT東日本のものだが、東日本以外の地域でも使い方は同じ
自宅で地震対策をする前の大前提「モノを適正量に減らす!」

家の中の地震対策は、「モノを適正量に減らすこと」から始まる。
安全対策をしても、モノが部屋に溢れていては、転倒や落下などによる危険度がグンとアップする。
「地震が来た瞬間、全てのものは【落ちる・倒れる・移動する】と考えたほうがよい」と松永さんは語る。植木鉢や雑貨が破損したり、テレビが転倒したり、電子レンジが飛んで壁に穴が開くといった被害が発生することも。
家の中でいつもモノを探しているという人は、モノの量が多いか、整理整頓ができていない可能性がある。玄関や廊下に積まれたダンボールが避難経路をふさぎ、飾っておいた雑貨が窓ガラスを割る前に、部屋をすっきり片づけて災害時の安全を確保しよう。
「自分好みの素敵な部屋」と「地震があっても安全な部屋」は両立させられます。
モノを適正量におさえて、あるべき場所に収めたら、地震対策をしながらインテリアも楽しみましょう。
賃貸でもできる家具の転倒・落下対策を解説
阪神・淡路大震災で亡くなった方の原因の77%は「窒息・圧死」である(※2)。家の中で家具の下敷きになって大ケガをしたり、亡くなった方がたくさんいる。被害を減らすためにも、家具の転倒や落下防止に取り組む事が重要だ。
※2 出典:第1章 死者を減らすために|国土交通省 近畿地方整備局
ここからは、松永さんに教えてもらった家具の転倒・落下防止対策の方法を部屋ごとに紹介する。賃貸でも使える対策グッズもあわせて紹介する。
危険がいっぱいの「キッチン」
モノが多く、火を扱うキッチンは、危険度の高い場所。食器や調理用具が凶器にならないよう対策したい。
1.食器棚やキッチンボード
耐震ラッチの紹介(出典:松永りえ Instagram)
地震の揺れによって扉が開き、中のモノが飛び出さないように、開き戸の食器棚やキッチンボードには揺れを検知すると自動でロックがかかる「耐震ラッチ」の導入がおすすめ。両面テープで付けられるものもあるが、できればネジ式のもので取り付けるのがベスト。
また、ガラス扉の食器棚は、ガラスに「飛散防止フィルム」を貼るとよい。
いずれも、作り付けの棚に設置する場合は管理会社や大家さんに相談しよう。

食器棚の転倒防止のため、重い食器は下の段に、軽い食器は上の段に収納するようにしよう。食器の下には「滑り止めシート」を敷くだけで、動きにくく、割れにくくなる。
2.冷蔵庫
冷蔵庫は、「転倒防止ベルト(ベルトストッパー)」などで転倒防止対策を。また、冷蔵庫の扉は、大きな地震が来れば必ず開いてしまう。食品をボックスに入れてから冷蔵庫へ収納すれば、もし扉が開いても中身の飛び出しを抑えられる。
3.電子レンジ・オーブン
電子レンジやオーブンは、地震の際に宙を舞って凶器になる可能性がある。ネジで固定するものもあるが、「ジェルタイプの耐震マット」なら、揺れを吸収して、滑り防止にもなるのでおすすめ。足に履かせるだけなので設置もカンタンだ。

4.調理器具や食器
包丁や鍋、カトラリー類は、外に出しておいたり、フックなどで高いところにひっかけておくと地震発生時に落ちたり飛んだりして危険。
毎日使うものでも、きちんとケースや食器棚に収納を。
耐震ラッチや転倒防止ベルト(ベルトストッパー)は、取り付けの際に備え付けの棚に穴が空いたり、跡が残る可能性があります。
しかし、管理会社や大家さんに「地震対策として取り付けることで設備の破損を防ぎ、入居者の安全を守る」と説明すれば許可してもらえるかもしれません。貸主にもメリットがあるので、ぜひ相談してみてください。
家族や友達が集まる「リビング」
落ち着いて過ごせるリビングは、地震が起きた時も安全なように整えておきたい。ファミリーの場合は、なるべく家族の個人的なモノを置きっぱなしにしないようにして、整理整頓を心がけよう。
1.テレビ、テレビボード

重い家電が倒れると、その下敷きになって動けなくなるなど、避難の妨げになる可能性も。テレビは、「耐震ベルト」でテレビボードへつなぎ、脚の部分には「耐震ジェルマット」を敷いてダブルで対策すると良い。また、テレビボードは脚を外して直に置き、「転倒防止板」を挟むと安定感がアップする。

2.棚や本棚、タンスなど
棚や本棚、タンスなどは背が高いほど転倒しやすく危険。なるべく背の低い家具を選ぶようにしよう。
背の高い家具を置く場合は、「L字金具」や「突っ張り棒」で固定を。さらに脚元に「転倒防止板」を挟むと安定感がアップする。
また、本棚の前端には、本が揺れで飛び出にくいように「落下抑制テープ」を貼って対策するのもおすすめ。
L字金具などネジを使用する場合は、事前に管理会社や大家さんの許可を取ることも忘れずに。
3.ピアノ
グランドピアノでもアップライトピアノでも、、大きな地震が起きるとひっくり返る可能性がある。家具用の固定グッズ・転倒防止グッズではなく、「ピアノ専用の地震対策グッズ」を導入するとよい。ピアノメーカー等のホームページを確認しよう。
4.窓ガラス
室内のモノが飛んだり、倒れたりして窓ガラスを突き破ることがある。「飛散防止フィルム」を貼ったり、「レースカーテン」などを常に閉めておくと、ガラスでケガをする可能性を低減できる。フィルムを貼る場合は、管理会社や大家さんに確認を。
5.観葉植物
倒れにくいよう、重心が低く安定感のある鉢を選ぼう。また、鉢底に「滑り止めシート」を貼って動かないように工夫を。
キャスター付きの鉢置き台は、地震の際に激しく動くため避けたほうがよい。
6.雑貨、インテリア小物
雑貨や小物類も、底に「クッションゴム」や「耐震ジェルシート」を貼ると振動を吸収して動きにくくなる。安全に配慮すれば、好きなインテリア小物や推し活グッズなども楽しめる。


無防備になりやすい「寝室」
寝ている間は無防備で地震発生に気づきにくく、寝起きは動きが鈍くなるため、周到な防災対策が必要だ。寝室には、背の高い家具は置かないようにしたい。
背の高い家具を置く場合は、これまでに紹介したグッズで固定するほか、倒れた時にベッドに届かないように角度や置く位置を調整すること。
素足で過ごすことが多い寝室。私は、割れたガラスや釘などから足を守ってくれる「防災スリッパ」をベッドサイドに置いています。もちろんスニーカーなどでもOKです。
落下・転倒防止グッズは、検証実験済みのものを選ぼう
家具の固定に使うアイテムは、できる限り「防災用品専門のメーカー製」のものを購入したい。防災用品を専門的に開発しているメーカーは、地震の揺れを想定した検証実験を繰り返したうえで商品を提供しているからだ。命を守るための防災グッズは、妥協せずに選びたい。
ホームセンターの防災コーナーには、専門メーカーのものが種類豊富に並んでいます。インターネットで購入する際も、検証実験を行った商品を選ぶとよいでしょう。
まだまだある! 賃貸物件でできる防災対策
自宅の中に「安全スペース」を用意しよう
部屋の片付けや家具固定などの防災対策ができたら、ぜひ実行してほしい地震対策がもう1つある。それは「安全スペースづくり」。
地震を伝えるアラームや報知音が鳴ると、人はパニックになって動けなくなり、その間にモノが飛んできたり、家具が倒れてきたりして被害に遭ってしまう。そんな時、すぐに安全な場所に逃げ込めば、とりあえず身の安全を確保できる。
安全スペースを家の中で探すのは難しいので、家具が倒れない・落ちない・移動してこない場所を、自分で「つくる」しかないのだ。
備蓄品の準備のしかた
また、食料や日用品の備蓄については東京都防災HP「東京備蓄ナビ」を参照するとよい。カンタンな質問に答えて自分や家族に合う備蓄がわかるツールもある
参考サイト:自分に合った備蓄を調べてみよう | 東京備蓄ナビ
避難時の持ち出し用に備える「防災リュック」に関しては、以下の記事を参考にしてほしい。
その他の防災対策とポイント
上記以外にも、知っておきたい室内の防災のポイントをいくつかご紹介する。
- 避難経路(廊下や床)にはモノを置かない
- 玄関に置く靴は1人1足
- 防災リュックは玄関に置くとよい
- トイレに閉じ込められないよう、出入り口近くにモノは置かないようにする
- ドアが歪んで出られなくなった時のために、トイレにはスマホを持っていくとよい
- 裸で逃げることにならないよう、脱衣所に下着や着替えを置いておくとよい
知っていればカンタンにすぐできる方法がたくさんある。命を守るための地震対策を、今日から始めてみよう。
今の行動が「災害時の自分や家族」を守る
ここまで紹介してきた家具の転倒・落下防止対策は、あくまでも「避難するまでの時間稼ぎ」であり、命を守るための一時的なものです。
ただし、日頃からモノを適正量に減らし、整理整頓を心掛ければ、災害時の自分や家族を守ることにつながります。
お気に入りの家具や雑貨に地震対策を施すことで、生活を楽しみながら防災意識を高めることができる。命と安全を守るための対策を今日からぜひ実践してみてほしい。
監修・取材協力:松永りえ
参考書籍:松永りえ『地震に強い収納のきほん』
取材・文:元井朋子