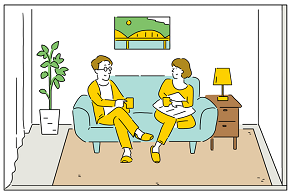一人暮らしの食費の節約術!食費事情とコストを抑えるコツ
このページの目次
自炊をしながら一人暮らしの食費を抑える具体的な方法

一人暮らしをしている人が食費を抑えるなら、やはり外食よりも自炊の食材費の方がコントロールしやすいだろう。
ここでは、無理なく食費を抑えるために、以下の具体的な方法を紹介する。
- コスパの良い食材を中心に購入する
- 安い店舗や割引デーを使い分ける
- セール日を狙ってまとめ買いする
- 買い物は午前中に。半額シールなど割引に惑わされない
- 食材の使いまわしを考えて購入する
- 「下味冷凍」や「冷凍貯金」をする
なお、レシピについては下記の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。
コスパの良い食材を中心に購入する
食費を抑えるには、 栄養価が高く、コスパの良い食材を中心に選ぶのがポイント。
グラムあたりの単価や、1パックで何食分作れるかを意識すると、より節約につながる。
たとえば、以下のような食材がコスパが良く節約しやすい。
| 食材 | 平均価格 |
|---|---|
| 野菜 | ・キャベツ(1玉) 322円 ・もやし (1袋)42円 ・じゃがいも(500g)279円 ・しめじ(1パック)160円 ・えのき茸(1パック)106円 |
| 肉類 | ・鶏むね肉 100gあたり 125円 ・豚肉こまぎれ 100gあたり 150円 ・豚ひき肉 100gあたり 166円 ・鶏むねひき肉 100gあたり 140円 |
| 加工食品 | ・納豆(3パック)85円 ・豆腐(1丁)106円 ・あぶら揚げ(1枚)74円 |
| 麺類 | ・パスタ(600g) 430円 ・うどん(2食)279円 ・焼きそば(3食)213円 |
| その他 | ・たまご (10個入) 236円 |
※すべて税込み表記
※実際の価格相場は時期や地域によって異なります
近年は、食料品をはじめとした物価の上昇が顕著で、特に肉や卵、野菜などの価格変動が激しくなっている。家計への負担が増す中で、少しでも食費を抑える工夫が必要だ。
肉は、節約しやすい「鶏むね肉」「豚こま肉」「豚ひき肉」や「鶏ひき肉」を中心に、特売品や旬の野菜、大豆製品を取り入れながらかさ増しすると、食費を抑えやすい。
また、鳥インフルエンザなどの影響で価格が変動しやすい「卵」は、栄養価が高く、自炊の助けになるため、ストックしておくと便利だ。
野菜が高いときは、業務用スーパーなどの冷凍野菜を活用するなど、臨機応変に使い分けるとよい。
安い店舗や割引デーを使い分ける
店舗によって値段設定は異なる。近隣のディスカウントスーパーや業務用スーパー、ドラッグストアなど、安く買える店を上手に使い分けることで、購入費用を抑えられる。
よく買う定番の食材については、買い物をしながら価格をリサーチしておくと、どの店で購入するのが得か分かり、時間の節約にもつながる。
また、同じ店舗でも日によってお買い得商品が変わるため、チラシアプリなどで事前にチェックしておくと便利だ。
特に食パンや卵、牛乳などの「白物食材」はドラッグストアでも安く提供されることがあるので、近隣のドラッグストアで価格をチェックしておくとよいだろう。
セール日を狙ってまとめ買いする
食費を抑えるために有効活用したいのが、近隣スーパーのセール日や特売日だ。
多くのスーパーでは、曜日ごとに特売商品が決まっていたり、月に1回ほど大規模なセールを実施したりしている。セール情報は、各スーパーの公式アプリやチラシアプリで確認できるので、事前にチェックすることをおすすめする。
また、食費を抑えるには、スーパーやコンビニが独自に製造・販売しているプライベートブランド(PB)商品を活用するのも効果的だ。PB商品は、一般的なブランド商品よりも 価格が低めに設定されていることが多く、食品だけでなく調味料類もPB商品を選ぶことで節約につながる。
ただし、せっかくまとめ買いをしても、食べきれずに捨ててしまっては逆効果になる。特に、外食の予定が入りがちで食材を使い切れない人は、3日に1回程度の「プチまとめ買い」を取り入れると無駄を防ぎやすい。
また、単身者向けの2ドア冷蔵庫は容量が小さいため、買いすぎには注意が必要。
セール日には常温保存できる食材をメインに購入し、生鮮食品は3日ごとに買い足すなど、買い物のタイミングを工夫すると、食品ロスを減らしながら食費を抑えられる。
買い物は午前中に。半額シールなどの割引に惑わされない
スーパーで買い物をする際、「安くなっているから」「ついでに買っておこう」という感覚で値引き商品を手に取ってしまうことは多い。しかし、いくら値引きされていても、必要のないものを買えば結局はムダ遣いになる。
まずは、あらかじめ買うものをリスト化し、本当に必要なものだけを購入するのが大切だ。
すぐに使う予定の食材が割引されていたら活用してもよいが、生洋菓子などの嗜好品を安いからといって買ってしまうのはNG。
値引きシールに惑わされず、必要かどうかを冷静に判断する習慣をつけよう。
午前中の買い物をするメリット
買い物に行くなら、午前中がおすすめだ。理由は、午前中のスーパーには以下のようなメリットがあるから。
- 品揃えが豊富で、欲しい食材を確実に購入できる
- 広告の品や見切り品など、お得な商品が揃っている
- 集中力や判断力が高い時間帯のため、無駄遣いを防げる
夜の方が値引き率は高くなることが多いが、夜の値引き品は惣菜や弁当などの加工食品が中心となるため、自炊派には向いていない。
また、夜になると売り切れている商品が多く、必要なものを買えない可能性もある。
平日の午前中に行けない場合は?
平日の午前中に買い物に行けない人は、以下をルーティン化し、土曜日もしくは日曜日の午前中に行くことをおすすめする。特に日曜日は午前中限定のセールを行っているお店もあるので、チェックしておこう。
- まとめ買いをして、作り置きや冷凍保存を活用する
- 週末に下ごしらえを済ませ、平日は調理の手間を省く
この習慣を身につければ、食費の節約だけでなく、忙しい平日でも手軽に自炊できる環境を整えられる。
無駄遣いを防ぎつつ、効率的な買い物を習慣にしていこう。
食材の使いまわしを考えて購入する
食費を抑えるためには、 コスパの良い食材を選ぶだけでなく、食材をどう使いまわすかも重要なポイントになる。
たとえば、キャベツと豚こま肉を購入した場合、以下のように異なる料理に活用できる。
| 日数 | メニュー |
|---|---|
| 1日目 | 豚こま肉入りのお好み焼き |
| 2日目 | 豚こま肉とキャベツの味噌炒め(回鍋肉) |
| 3日目 | 豚こま肉の生姜焼き キャベツの千切り添え |
このように事前に使い道を決めておくと、無駄なく食材を消費できるだけでなく、食事のバリエーションも広がる。
特に「キャベツ+豚こま肉」の組み合わせは、お好み焼きや回鍋肉、生姜焼き、焼きそばなど、さまざまな料理に応用できるので、自炊初心者にもおすすめだ。
献立を考えるときは、使い切りたい食材を中心に考え、レパートリーが少ない場合はレシピサイトやYouTubeで検索し、その日の気分や調理時間に合わせて選ぶのがポイント。
また、忙しい日はフライパンでサッと炒める調理法がおすすめ。短時間で作れるため、時間がないときでも簡単に自炊できる。
食材を上手に使いまわすことで、無駄を減らしながら、食費の節約と時短を両立できるようになる。
「下味冷凍」や「冷凍貯金」をする
購入した食材を長持ちさせ、調理時に使いやすくするために、「下味冷凍」や「冷凍貯金」を活用するのがおすすめだ。
「下味冷凍」とは、カットした肉や玉ねぎを焼肉のたれなどで味付けし、ジッパー付きの保存袋に入れて揉み込み、冷凍しておく方法のこと。朝出勤前や前日の夜に、冷凍庫から冷蔵庫へ移しておけば、帰宅後にフライパンで加熱するだけで簡単におかずが一品作れる。
「冷凍貯金」とは、食材やおかずを冷凍しておくことで、忙しい日々に時間や心のゆとりを作る習慣だ。たとえば、特売で買ったきのこは、石づきを取ってバラし、保存袋に入れて冷凍する。凍ったまま取り出して、そのまま調理できるので便利だ。同様に、ブロッコリーは小房に分けたり、インゲンの筋を取ったり、小松菜をざく切りにして冷凍することもできる。
このような方法を活用すれば、食材の無駄を減らし、調理の手間も省ける。冷凍保存を上手に使うことで、時間・栄養・お金を貯め、家事の負担を軽減することができる。
その他にも知っておきたい節約術

ここまで、一人暮らしの食費を抑えるための具体的な方法を紹介してきたが、食費の節約は買い物や自炊の工夫だけではない。日々のちょっとした習慣や選択を見直すことで、さらに負担を軽減することができる。
ここでは、 買い物や外食時に活用できる以下6つの節約術を紹介するので、ぜひ日常生活に取り入れてみよう。
- 買い物しながらポイントを貯める
- 値引きシールが貼られる時間帯を狙う
- 格安なチェーン店を利用する
- クーポンを利用する
- ふるさと納税を活用する
- 家庭菜園にチャレンジする
買い物しながらポイントを貯める
食費を抑えるために、 ポイントサービスを活用するのも効果的だ。
ポイントは、実質的な値引きに相当するため、二重取り、三重取りやポイントアップを狙い、効率よく貯めたいところ。食材を購入しながらポイントを貯めれば、後日そのポイントを使って食材を購入することもできるし、外食費に充てるのも一つの方法だ。
たとえば、ポイントが貯まる決済サービスを利用すると、効率よくポイントが貯まる。QRコード決済や、特定のキャンペーンを活用することで、ポイント還元率をアップさせることができる場合もある。ポイントの付与条件や対象商品を確認し、賢く活用しよう。ただし、ポイントを貯めるために余計なものを買わないよう注意が必要だ。
おすすめの貯め方は、クレジットカードや携帯キャリア、QRコード決済など、ポイントが連携するサービスを統一することだ。特定の「ポイント経済圏」を決めて効率よく貯めると、ポイントが貯まりやすくなる。
貯まったポイントは、誕生日やクリスマスなどのイベント費用に充てる ことで、特別な支出を抑えるのにも役立つだろう。
値引きシールが貼られる時間帯を狙う
スーパーで弁当や総菜を購入するなら、 値引きシールが貼られる時間帯を狙うのが賢い方法だ。
値引きシールが貼られる時間帯は公表されているわけではないが、その日に売り切りたい商品は、閉店1時間前が狙い目になることが多い。また、夕方からの割引セールを実施している店舗もあり、何度か足を運ぶうちに、値引きが始まる時間帯の傾向がつかめてくるだろう。
最近では、食品ロス削減の取り組みとして、コンビニでも値引きシールが貼られるようになったが、そもそもの価格が高めなためスーパーほどのお得感は少ない。
ただし、値引きされているからといって買いすぎるのは本末転倒なので、あくまで必要な分だけを購入することを意識しよう。
格安なチェーン店を利用する
外食をするなら、格安なチェーン店を活用するのが基本だ。
具体的には、牛丼チェーンやうどん店、ハンバーガーショップなどのファストフード店が挙げられる。
また、職場や自宅周辺にワンコインランチなどを提供している店がある場合は、それらを上手に活用するのも一つの方法だ。
外食をしながら食費を抑えるなら、自身の行動範囲内でコスパの良い店を把握しておくことが重要。店舗によって異なるが、消費税の軽減税率制度の導入により、店内飲食は消費税10%、テイクアウトは8%となるため、できるだけテイクアウトを活用するのも節約のコツ。
テイクアウトした食事には、自宅で卵を加えたり、インスタントや味噌、顆粒だし、乾燥わかめを使った簡単なみそ汁を作ったりすることで、栄養バランスを整えつつコストを抑えることができる。
クーポンを利用する
飲食店の中には、自社のアプリやLINEでクーポンを配布しているところも多い。
外食での費用をなるべく抑えたいなら、こうしたクーポンを活用するのが賢い方法といえる。
ただし、クーポンには有効期限があるものも多いため、「期限内に使わなきゃ」と無理に外食の回数を増やしてしまうと、かえって食費がかさむことになりかねない。
あくまで必要なときに使うという意識を持ち、計画的に活用するのがポイントだ。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度。
寄付することで、住んでいる自治体の住民税の控除や所得税の還付を受けられる。
ただし、寄付の上限額は所得によって異なるため、ふるさと納税サイトなどで事前に確認する必要がある。
たとえば、3万円を寄付した場合、約1万円分の返礼品をもらえ、自己負担額の2000円を差し引いた2万8000円分の税金が還付または控除される。控除を受けるには、ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告をする必要がある。
ふるさと納税では、寄付金の約30%が返礼品として受け取れるため、お米や野菜などの食材を選べば、家計の負担を軽減しながら食費を節約することができる。
家庭菜園にチャレンジする
野菜の価格が高騰すると、食卓の彩りが少なくなり、どうしても見た目が茶色っぽくなりがちだ。
そんなときは、ネギ、大葉、パセリなど、比較的育てやすく彩りになる野菜を家庭で栽培するのも一つの方法。
100円ショップでは、2つで100円とリーズナブルな価格で種が手に入る。また、近隣にホームセンターがあるなら、種だけではなく、土とプランターも揃えると、長期間活用できる。
植物を育てるのが好きな人にとっては、節約しながら食卓を豊かにできるおすすめの方法といえるだろう。
一人暮らしの食費は工夫次第で無理なく節約できる
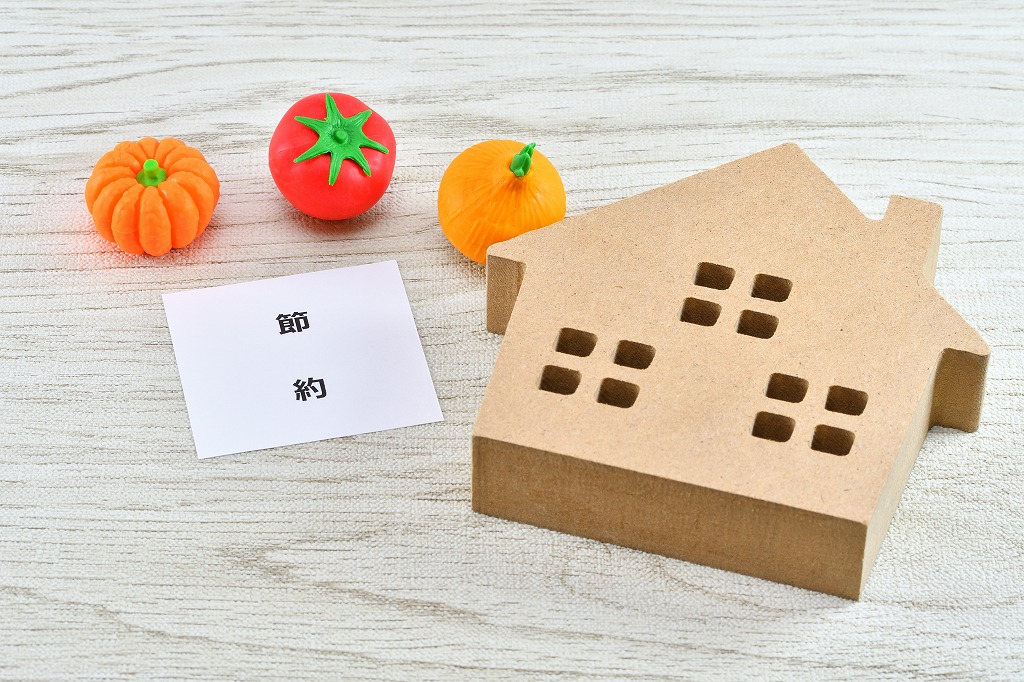
一人暮らしの食費は、平均すると4万円前後だが、工夫次第で節約することも可能だ。
しかし、節約ばかりを意識しすぎて無理をするのは禁物。住んでいるエリアや物価によって食費は変動するため、食費を抑えることよりも、無駄のない管理を意識することが大切だ。
今回紹介した食材の選び方や買い物の工夫、外食費の節約方法を取り入れることで、無理なく食費をコントロールできるようになるだろう。また、食費の節約が難しい場合は、固定費の見直しやポイント活用など、生活全体のコストを抑える方法も考えてみよう。
大切なのは、自分のライフスタイルに合った方法で、無理なく続けられる節約を実践すること。まずは、自分の支出を把握し、できる範囲で少しずつ工夫を取り入れていこう。