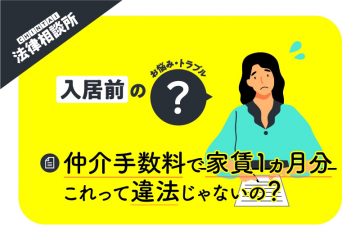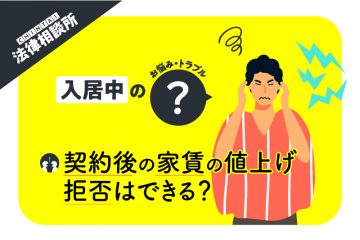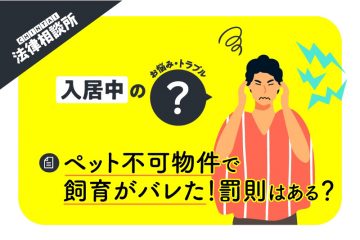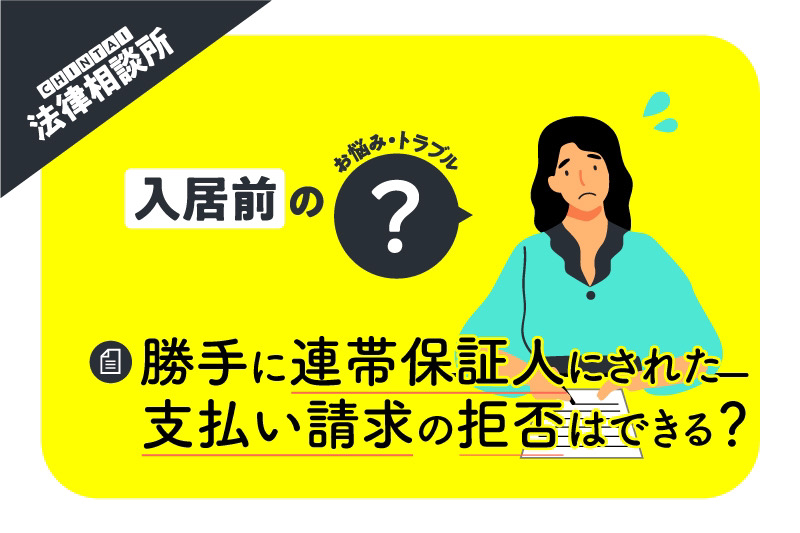
勝手に賃貸物件の連帯保証人にされていた場合、家賃の支払い請求を拒否できる?【CHINTAI法律相談所】
賃貸物件に関する疑問に弁護士がアドバイス
賃貸にまつわるトラブルや疑問について解説する【CHINTAI法律相談所】。
入居前から入居中、退去時まで、さまざまなタイミングで発生しやすい賃貸トラブル。その疑問や対応について、不動産トラブルに強い瀬戸仲男弁護士に聞いた。
賃貸トラブルは、いつ巻き込まれてしまうかわからない。現在トラブルにあっている人だけでなく、これから賃貸物件を借りる予定の人もぜひ参考にしてほしい。
このページの目次
Q.弟が勝手に私を賃貸物件の連帯保証人に指定! 滞納金を請求されているが、拒否できる?
不動産会社から「弟さんの賃貸物件の連帯保証人になっている」と連絡があり、滞納分の家賃を請求された。だけど、契約書を交わした記憶がない! 勝手に連帯保証人にされていたんだけど、滞納金の支払いを拒否できる?
A.勝手に連帯保証人にされた場合、滞納金を支払わなくてOK
勝手に連帯保証人にされた場合、基本的に返済する義務はない。まず連帯保証契約は民法446条2項によって書面でする必要があり、口約束で結べないと定められている。連帯保証契約の当事者でない弟さんが、大家さんあるいは管理会社と書面の契約はせずに口約束で契約を結んだ場合、滞納した家賃を支払う必要はない。
弟さんが勝手に印鑑を持ち出して契約書に捺印したケースでも同様だ。本人の許諾を得ず代理人として振舞う「無権代理」による連帯保証契約は、代理行為の効果が本人に及ばないこと(効果不帰属)とされる(民法113条)。
しかし無権代理による契約でも、後から契約を認めたり、滞納金の一部でも支払ったりしたら、事後承諾とみなされる。保証契約の効果が契約時に遡って保証人にさせられた本人に及び、契約内容の保証責任を負わなければならない。
このように法的に本人に効果が及ばない無権代理行為を認めることによって、遡及的に効果が及ぶようになることを「無権代理行為の追認」という(民法116条)。一度でも追認してしまうと、「契約の効果が及ばない(効果不帰属ゆえに責任を免れる)」ことを主張できなくなる。
もし相手から「少しでも支払って欲しい」と迫られても、決して応じないように。
相手にきちんと事情を説明し、理解してもらうことが大切
また、弟さんが勝手に連帯保証契約に捺印していたとしても、滞納金を支払わなければならないことがある。契約内容を理解していなくても、弟さんに対し「連帯保証人を承諾する」と認めていたケースなどは、弟さんに代理権を与えていたと考えられ、連帯保証契約が成立する恐れがある。
もちろん、保証契約の内容を全く知らされていないなら、弟さんに代理権を与えたことは確定的でない。そういった場合は、無権代理行為として保証契約を拒否しよう。印鑑や筆跡が自分のものと異なれば有力な証拠として扱えるため、代理権を与えていないと証明できるはずだ。
いずれにせよ勝手に連帯保証人にされたなら、請求を放置せず正しく対処することが重要だ。まずは弟さんや家族に話を聞き、当時の状況や経緯を把握しよう。
事実関係を調べたら大家さんや管理会社に事情を説明。やり取りを証拠として残すため、書面にまとめて内容証明郵便で送付すると良い。それでも相手が納得してくれなかったり、話がこじれそうだったりするなら弁護士への相談も検討しよう。
ここがポイント!
勝手に連帯保証契約の保証人にされていたなら、基本的には滞納金を支払う必要はありません。きちんと事情と説明し、連帯保証契約の不成立を主張しましょう。もし相手が引き下がらないようなら、証拠を集めて「自分が契約したわけではない」ことを証明しましょう。
覚えておきたい用語「連帯保証人」
一般的に「保証契約」と言うと「連帯保証契約」を指すことが多いが、単なる保証人と連帯保証人は厳密には異なる。
保証人とは「債務者が債務を履行できなかった場合に代わりに履行する義務を負う人」のこと。連帯保証人は、保証人が持つ「催告の抗弁権」(民法452条)、「検索の抗弁権」(民法453条)を有せず(民法454条)、「分別の利益」(民法456条)も持っていない。
民法452条
民法 – e-Gov法令検索
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
民法453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
民法456条
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定(分割債権債務の規定)を適用する。
賃貸借契約で言うと、連帯保証人が滞納家賃の請求をされた場合、「入居者(賃貸借契約の契約者)に先に請求すべき」と求める(催告の抗弁権)ことはできない。「入居者がお金を持っているからその者に先に請求・執行すべき」と訴える(検索の抗弁権)ことも難しい。加えて、連帯保証人が複数いても滞納金の分担(分別の利益)を認められず、各連帯保証人は全額を支払う義務を負担する。
そのため連帯保証人は、入居者がお金を持っている場合でも、大家さんや管理会社に支払いを求められたら拒否が不可能。通常の保証人より重い担保責任を負っているのだ。
取材・文=綱島剛(DOCUMENT)
【CHINTAI法律相談所】入居前のトラブルについての記事はこちら!
【CHINTAI法律相談所】契約のお悩みについての記事はこちら!