【参院選・衆院選】投票方法や選挙の仕組みを解説!候補者ってどう選ぶ?
知っておきたい選挙の基本③投票ってどうやるの?
- 住民票の住所宛に整理券が届く
- 不在者投票/期日前投票/投開票日のいつ投票に行くか決める
- 投票
日本国籍を持つ18歳以上の方は基本的に、この選挙に投票する権利があります(有権者と呼びます)。「引越したばかりで選挙権がない」という話をたまに耳にしますが、国内の引越しであれば、もともと住んでいた区市町村で投票することができます。
少し解説しますね。
基本的には「住民票のある場所」で投票できる

選挙の事務を担当する区市町村の選挙管理委員会は、区市町村の中で投票ができる人の名簿「選挙人名簿」を作成します。この名簿には転入届を提出したあと3ヶ月以上住み続けた人が掲載されます。
別の区市町村に引越してから3ヶ月以内の場合、引越した先の区市町村での投票はできませんが、今まで住んでいた区市町村で投票することができます。
また、住民票を実家など過去に住んでいた場所から移してしていない人も、住民票のある土地で投票することができます。(ただし、住民票は選挙だけでなく、確定申告や運転免許の更新など各種行政サービスにつながるだけでなく、住民基本台帳法という法律でも、引越しの際に住民票の異動を届け出ることは義務とされていますので、なるべく早めに手続きしておくことをお勧めします。)
選挙の時だけ実家に戻るのは大変!そんな時は「不在者投票」
とは言っても、投票期間中に実家や前住んでいた場所に、選挙のためだけに行く時間もお金も余裕がない!という人もいますよね。
そんな人のために「不在者投票」という制度が用意されています。
選挙人名簿に登録されている区市町村または、現在住んでいる区市町村の選挙管理委員会に問い合わせて、投票用紙を送ってもらい、最寄りの選挙管理委員会で投票して返送するという制度です。
投票日ギリギリになると郵送が間に合わず投票できない場合もあるので、余裕を持って早めに問い合わせてみましょう。
投票日は仕事がある!そんな時は「期日前投票」
今回の参議院議員選挙の投票日は2022年7月10日(日)ですが、仕事や家庭の都合などで日曜日に時間が取れない人もいます。
そんな人のために「期日前投票」という制度が用意されています。
選挙が公示された翌日の6月23日(木)から投票日の前日の7月9日(土)まで、各区市町村に設けられている期日前投票所で投票することができます。
投票所の設置場所については投票所入場整理券(封筒で送られてくるもの)や、区市町村の選挙管理委員会のウェブサイトをチェックしてみてください!
参考:不在者投票・期日前投票・在外者投票に関する政府の公式サイト
選挙期間に届いた「投票の封筒」は、なくしても投票できる!
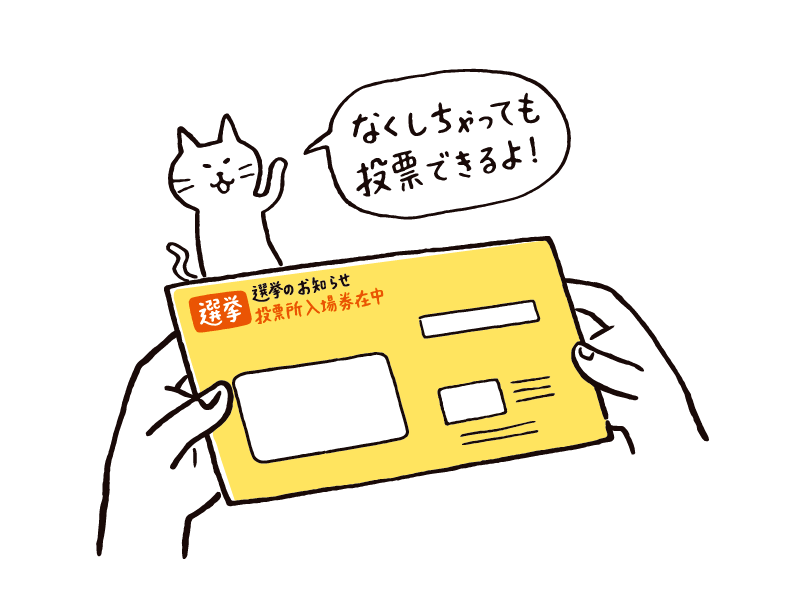
選挙が始まる前に届く封筒をなくしてしまったから棄権した、という話もよく聞きますが、実はこの封筒、なくても投票できるんです。
勘違いしている人が結構いるのですが、区市町村の選挙管理委員会から届くこの封筒は「投票券」ではなく、「投票所入場(整理)券」なんです。
なので、もし封筒をなくしてしまったとしても、投票することはできます。この場合、運転免許証など身分を証明するものがあると手続きがスムーズなので、準備をしていくといいでしょう。
投票所は人によって異なるので注意!
ただ、投票日にどの投票所に行ってもいい、というわけではありません。投票日ならあらかじめ自分が投票できる投票所を、投票日の前なら期日前投票所を区市町村のホームページなどで確認した上で足を運ぶようにしてください。
ちょっと人に話したくなる、選挙の豆知識
投票用紙に隠された意外な機能とは?
日本の選挙で使われている投票用紙は「ユポ紙」と呼ばれる特別な紙が使われています。
厳密には「紙」ではなく、樹脂でできた合成紙と呼ばれるもので、折り曲げてもすぐに元に戻る形状記憶の性質を持っています。折って入れても投票箱の中で開いた状態になるため、ユポ紙の導入後、開票作業が劇的に短縮されました。
また、ユポ紙は鉛筆での筆記に最適化されていて、文字がかきやすく、他の紙と擦れることがあっても文字が消えにくいという特性を持っています。
投票所に行ったらその書き味を体感して、投票箱に入れる前に二つ折りにして手を離し、元通りになるかどうか試してみては?
またこのユポ紙、汚れや水に強いので選挙用ポスターの素材としても人気があります。破れにくいので「敗れない」という縁起物としても政治家・候補者の皆さんに愛用されてるとか。
知っておきたい選挙の基本④投票先の選び方

選挙の意味と投票の仕方について確認したところで、「誰に投票していいのかよくわからない」という声もよく聞かれます。
日本の選挙は、誰が誰に投票したのかわからない「秘密投票」となっているので、誰に投票しても、誰からも咎められることはないのですが、納得のいく投票をするための材料をどうやって集めればいいのかについて確認してみましょう。
投票先を選ぶステップ
1.選挙区の確認
まずは、自分の住んでいる場所の選挙区の確認を。
まずは選挙区から確認しましょう。自分の選挙区は投票所入場(整理)券に記載されています。なくしてしまった、または届かなかった場合は選挙管理委員会に問い合わせるか、インターネットで確認してみましょう。
参議院選挙の選挙区は基本的に各都道府県が1つの選挙区になっていて、鳥取・島根と徳島・高知はそれぞれ2県で1つの選挙区になっています。
衆議院選挙の小選挙区は各都道府県が2〜25の選挙区に分割されています。
選挙区によって立候補者の顔ぶれが違うので、まずはそこから確認しましょう。住民票のある都道府県が自分の選挙区になります。
どの選挙区に投票できるのかがわかったら、いよいよ候補を比較していきましょう。
2.インターネットでの情報収集は、本人の発信もチェックしやすい
新聞社のウェブサイトなどにリストが掲載されているので、略歴はそこから確認できます。最近はそれぞれの候補者の公式ウェブサイトやSNS、YouTubeのアカウントなどにリンクされていることが多いので、それぞれの候補者の発信をチェックしてみるといいでしょう。
3.選挙公報で候補者を網羅的にチェック
それぞれの候補者の政策を新聞サイズまとめた「選挙公報」がこの選挙期間に発行されます。個人宅に投函される場合が多いですが、そうでない場合も、役所や出張所などで配布されていたり、都道府県の選挙管理委員会のウェブサイトからPDFファイルでダウンロードができるようになっています。選挙公報は全ての候補者に同じ大きさのスペースが与えられているので、政策や主張、プロフィールなどを見比べてチェックするのに便利です。
4.ネットで調べやすい「ボートマッチ」がおすすめ

新聞社や市民団体などが、候補者に対して行ったアンケートを元に作るWebサイトの「ボートマッチ」を利用してみるのもオススメです。いくつかの争点となっている政治課題について、賛成・反対など自分の意見を入力していくと、自分の意見に一番近い立候補者がわかる仕組みになっているので、候補者選びの参考にぜひ。
テレビ・ラジオの政見放送では全候補者のチェックはできない
テレビやラジオで候補者や政党の訴えを放送する「政見放送」というものもあります。ただし、これは放送する日時が決まっていて、インターネットでは視聴・聴取することができません。衆議院議員選挙の場合は無所属候補や既存の大きな政党以外にはこの機会を与えられていないので、注意が必要です。
上級者向け:情勢調査から考えてみよう
選挙が進むと、世論調査を元に報道各社から「情勢調査」が発表されます。これは、各選挙区の候補者のうち、誰が有利で誰が出遅れているのか、といった情報をまとめたものです。
例えば自分が一番応援している人は3番手で勝ち目がないので、候補者の中で2番目に当選してほしいと思っている人に投票することで、自分とは考え方が違う1番手の候補者の当選を阻止しようとする、といったような、自分の投票の価値を最大に高めようとする「戦略的投票」と呼ばれる投票行動をとる人もいます。
とはいえ、世論調査の数字が必ずしも正しいというわけではないので、悔いのない投票にするためには十分な情報収集が必要。上級者向けの考え方と言えるでしょう。
知っておきたい選挙の基本⑤選挙・投票はゴールじゃない

ここまで、選挙とは何か、という話から投票の方法についてお話をしてきました。最後に「選挙は手段であって目的ではない」というお話をしたいと思います。
私たち一人一人が議会に行って、議論を交わすことは物理的にも時間的にも不可能なので、私たちの代わりに意見を言って、ルールの制定や、税金の使い道などについて決めてくれる人=議員を選ぶのが、選挙のそもそもの目的です。
選ばれた国会議員をチェックしよう
応援していた候補者が当選しても、その人が国会議員として期待通りの仕事をしてくれる、という保証はありません。
逆に、たとえこの選挙で自分が応援した候補者が落選してしまったとしても、それで全てが終わってしまうわけでもありません。自分が投票しなかった人でも、この選挙で選ばれた人は私たちの代表であることにかわりないのです。
当選した人々が国会でどんな仕事をして、議員としてこの社会に貢献しているのかをチェックするのも、有権者が持つ責任のひとつと言えるかもしれません。
国会議員の仕事をチェックするにはどんな方法があるんでしょうか?
SNSやブログ、独自に発行している活動報告など議員から発信される情報のほか、新聞やテレビ・ラジオなどの報道番組を気にして見てみましょう。専門的な話が多く、わかりにくいこともありますが、半年に一度くらいは地元選出の国会議員の動向をチェックしてみる、くらいの意識を持っておくと、政治家側にも緊張感が生まれてより良い関係が築けるかもしれませんね。
選挙だけが政治じゃない!
選挙以外の政治への関わり方にも触れておきたいと思います。
選挙で意思を示すことができるのは数年に1回という機会ですが、私たちが政治に参加できるのは選挙の時だけではありません。
- 人数を集めてデモや集会をする
- 問題だと思うことについて署名を集めて議会や議員、政党に陳情する
- 具体的に政策をまとめて議員や政党に提言する
さまざまな方法があります。同じ地域に住んでいる人の会合に参加してみたり、地域を超えた同じ課題を考えるオンラインのコミュニティに加わってみるのもいいでしょう。
選挙に限らず身の回りの小さな政治に関わってみることで、自分たちの力で社会を変えることができることを実感すると、世界が少し明るく感じるかもしれません。
*
宮原さん、ありがとうございました!
参考サイト:
第26回参議院議員通常選挙 参院選2022 – 総務省






















