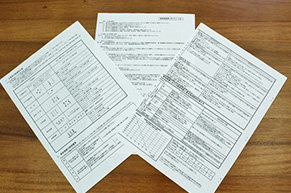耐震等級とは?等級1~3の基準や耐震基準との違いを建築・不動産のプロが解説

地震大国・日本で部屋探しをするなら「耐震等級」はチェックしておきたいキーワードになる。実際に賃貸物件を選ぶときにどのように参考にすればいいのだろうか。
本記事では「耐震等級」に関する基礎知識と「耐震基準」との違い、さらに建築・不動産のプロが語る「地震に強い物件の見極め方」を解説していこう。
この記事でわかること
耐震等級とはどういうものか、等級1~3の基準
耐震基準との違い
不動産のプロが教える「地震に強い物件の選び方」
このページの目次
耐震等級とは?
耐震等級とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が定める「住宅性能表示制度」に基づき、建物が地震にどれだけ強いかを等級で示したものである。建物の重さを支える柱や梁、横揺れに耐える耐力壁(※1)、基礎や床の強度などを総合的に評価して決められる。
※1 耐力壁とは:柱の間に設けられる筋交いや構造用合板(面材)などで、地震や強風などの力に抵抗する役割を持つ壁のことである。耐力壁の量が不十分だったり、バランス良く配置できていなかったりすると耐震性が弱まるため、耐震等級を判断するうえで重要な要素となる
耐震等級には1から3までの等級表示があり、数値が大きいほど地震への備えが強化されている。等級1は建築基準法レベルの耐震性能を満たすもの、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に耐えられる水準であり、等級3が最高レベルである。
耐震等級の数字を見ることで、「木造」や「RC造」といった建築構造の違いに関わらず、客観的に耐震性能を比較できるようになった。木造物件でも、最高レベルの等級3を取得することが可能だ。
1995年の阪神・淡路大震災で甚大な地震被害を受けたことをきっかけに、2000年の建築基準法において耐震基準が強化されました。
そして同年、新法である「品確法」が施行され、住宅性能評価を受けて性能表示制度を利用することで、建物の耐震性能のレベルを客観的に示す「耐震等級」の表示が可能となったのです。
耐震等級の考え方
耐震等級は、「倒壊等防止」と「損傷防止」という2つの観点による等級表示がある。
倒壊等防止(必須項目)
極めてまれに(数百年に一度程度)発生する地震(※2)による力に対して、構造躯体の倒壊・崩壊等のしにくさを評価するもの。住宅性能評価を受ける場合、必須項目となる。
※2 想定される地震の揺れの強さは地域によって異なるものの、東京の場合、震度6強から7程度の揺れに相当する
損傷防止(選択項目)
まれに(数十年に一度程度)発生する地震(※3)による力に対して、構造躯体の損傷(大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷)の生じにくさを評価するもの。住宅性能評価を受ける場合、選択項目となる。
※3 想定される地震の揺れの強さは地域によって異なるものの、東京の場合、震度5強の揺れに相当する
なお、建築基準法で定められた免震構造の建物(免震建築物)であることが確認された場合、「倒壊等防止」や「損傷防止」の評価は行われず、免震建造物であることが表示される。
耐震等級1~3の基準
耐震等級には1から3までの等級がある。ここでは、それぞれの等級がどのような水準を示しているのかを整理する。
耐震等級1とは
耐震等級1は、建築基準法レベルの耐震性能を満たす水準。
極めてまれに(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して、構造躯体が倒壊・崩壊等しない程度の耐震性能を持つ。
また、まれに(数十年に一度程度)発生する地震による力に対して、構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)が生じない程度の耐震性能を持つ。
耐震等級2とは
耐震等級2とは、等級1の1.25倍の地震の力に対して構造躯体が倒壊・崩壊等しないほどの耐震性能を持つ。
また、等級1の1.25倍の地震の力に対して構造躯体の損傷が生じない程度の耐震性能を持つ。「長期優良住宅」では、耐震等級2以上が認定の条件とされている。
耐震等級3とは
耐震等級3とは、等級1の1.5倍の地震の力に対して構造躯体が倒壊・崩壊等しないほどの耐久性能を持つ。
また、等級1の1.5倍の地震の力に対して構造躯体の損傷が生じない程度の耐震性能を持つ。耐震等級の最高レベルである。
住宅性能評価を受けることは任意であり、費用もかかるので、分譲マンションなどと比べると賃貸物件では耐震等級の表示をしているケースはあまり多くありません。
また、最高レベルの耐震等級3を満たすには、建築コストの増加も伴いがちです。そのため、耐震等級3の建物は、家賃が高めになっている可能性があります。
耐震等級を確認する方法
耐震等級を確認するには、物件の「住宅性能評価書」をチェックするのが基本。賃貸物件では、入居希望者が評価書を直接手に入れることはできないため、不動産会社や大家さんに問い合わせて確認してもらうのが確実だ。
耐震等級「相当」とは?
物件広告などに「耐震等級2相当」や「等級3相当」と書かれていることがある。これは、設計上その水準の耐震性能を持っているという意味で使われているようだ。しかし、正式に「耐震等級○」と表示できるのは、国土交通省が指定する第三者機関(登録住宅性能評価機関)による評価を受け、住宅性能評価書が交付された物件に限られる。
つまり「相当」とある場合でも、実際に等級2や3と同じ耐震性能がある可能性はあるものの、正式に品確法に基づいて客観的な評価を受けたものではない。
耐震等級と耐震基準の違い
耐震基準は、建物に住む人の命や財産を守るための最低限の基準である。建築基準法で定められたこの基準は、建物の倒壊・崩壊を防ぎ、人命を守ることを最優先としたものだ。
これに対し、耐震等級には住宅性能表示制度に基づき、建築基準法で定めていた耐震性能を等級1として、さらに大きな地震が発生した場合を想定した等級2と等級3がある。等級の数字が大きくなるほど耐震性能が高くなることを示しているので、その建物が持つ耐震性能レベルがわかりやすくなった。
耐震基準は大地震が起きるたびに以下の通り改正が重ねられ、厳格化してきた歴史を持つ。最新の耐震基準では震度6強から7程度の地震で倒壊しないことが義務付けられている。
1981年5月31日以前(旧耐震基準)
旧耐震基準(旧耐震)とは、1950年の建築基準法施行時に定められたもの。1981年(昭和56年)5月31日まで適用される。
1981年6月1日以降(新耐震基準)
新耐震基準(新耐震)とは、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標とした基準である。1981年(昭和56年)6月1日に建築基準法が改正され、その中で新耐震基準が定義された。
2000年6月1日以降(2000年基準)
2000年基準とは、1995年の阪神・淡路大震災の被害を受け、2000年(平成12年)6月1日から導入された基準。新耐震基準をベースに、特に被害の多かった木造住宅の耐震性を強化するため、下記を盛り込んで見直している。
- 地盤調査の実質的な義務化
- 基礎や土台、柱や梁等の接合部の強化
- 耐力壁のバランスのよい配置
過去の大きな地震を教訓として耐震基準は底上げされてきました。新たに賃貸物件を建てる際も、常に建築基準法で定められた最新の耐震基準を満たす必要があります。
建物を建てるには必ず建築確認を受ける必要があり、建築確認の日付をチェックすることで、どの耐震基準で建てたのかを知ることができます。
耐震基準について、詳しくはこちら
耐震等級について押さえておきたい3つのポイント
部屋探しで知っておきたい耐震等級のポイントを3つ紹介する。
ポイント1:住宅性能評価を受けていない物件もある
耐震等級が表示できるのは、国土交通省が指定する第三者機関(登録住宅性能評価機関)による評価を受け、住宅性能評価書が交付された物件に限られる。
また、住宅性能評価は任意の制度であり、評価を受けるにはコストがかかるため、必要がなければそもそも性能評価を受けていない物件も多い。物件の耐震等級が気になる人は、不動産会社や大家さんに確認しよう。
ポイント2:あえて高い耐震等級を目指さず、建築するケースもある
耐震等級を高めるためには、耐力壁の量を増やしたり、配置バランスの兼ね合いで設計が難しくなる場合がある。間取りやデザイン、コストなどのさまざまな要素を考慮して、あえて高い等級にこだわらない場合もある。
繰り返しになるが、等級1だから危険ということではなく、建築基準法を満たしている以上、人命を守るために必要な耐震性は備えている。
ポイント3:耐震等級3の賃貸物件はそれほど多くない
賃貸物件の場合、そもそも住宅性能評価を受けていない物件が多い。また、耐震等級2や3の物件は建築コストが高くなる場合があるため、家賃も高めになりやすい。
耐震等級が高いほど耐震性能は高いとされていますが、その分、間取りの自由度が損なわれる場合があります。
例えば、立地や周辺環境を活かして明く開放的な部屋にするため、壁一面に大きな窓を設けると耐力壁が減ってしまい、耐震性能は下がります。逆に耐震性能を上げるために、窓を減らして壁を増やすと開放感が失われたり、使い勝手があまりよくない部屋になったりしてしまうこともあります。
耐震性能と住み心地のバランスをどのように考えるかということも重要です。
建築・不動産のプロが教える!地震に強い物件の選び方
地震に強い部屋を選ぶときに、まず大切なのは立地や地形である。ハザードマップを確認し、その地域に地震や液状化、浸水のリスクなどがあるかを把握することが大切だ。
そして、窓の大きさや数にも注目すべきだ。窓が大きく連続し、外壁が少ない建物は耐力壁が少なくなりがちで、揺れに弱くなる傾向がある。窓などの開口部の両側や建物の角に耐力壁が配置されているかどうかも強度を保つポイントとなる。
また、上下階のバランスも重要だ。柱だけで上部を支えているピロティ構造や、壁が少なかったり、見た目にも上下や壁の配置のバランスが悪かったりする建物は、揺れに弱い傾向がある。
さらに築年数が古い物件では、過去の地震によって見えない部分で耐震強度が低下している可能性があるため注意が必要である。地震に強い物件に住みたいという人は、不動産会社に過去の耐震補強、耐震改修の有無を確認しよう。
耐震等級が気になる人は、不動産会社に確認を
耐震等級は、その建物がどのくらい地震に強いのかを数字で示す目安。等級1は建築基準法の耐震基準をクリアするレベルで、必要な安全性は確保されている。等級2は等級1の1.25倍、等級3は等級1の1.5倍の地震に耐えられる水準。
ただ、すべての物件が性能評価を受けているわけではない。また、「○等級相当」といった表記は正式な評価を受けていない場合もある。
築年数が経過している物件では特に、外装がきれいになっていても、外からは見えない構造躯体が過去の地震で傷んでいることがある。耐震性の高い部屋を選びたいなら、自分だけで判断せず、不動産会社に相談して情報を確認するのが安心への近道になる。
耐震基準について知りたい方はこちら
地震から建物を守る「耐震」「免震」「制震」構造の違いはこちら
監修、取材協力:藤浦 誠一(株式会社エイブル)
文:佐々木正孝(キッズファクトリー)