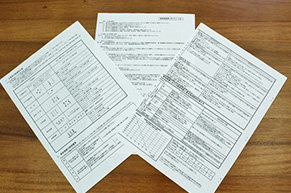耐震基準とは?新耐震はいつから?3つの基準と地震に強い物件選びを建築・不動産のプロが解説

日本では大地震が起こるたびに建築基準法が見直され、「耐震基準」が何度も改正・強化されてきた歴史がある。特に1981年の改正で導入された「新耐震基準」は、現在の建物の安全性を測る重要な目安だ。
では、いつ以降に建てられた建物なら新耐震基準を満たしているのか、旧耐震基準とどう違うのか。そして部屋探しの際に耐震基準をどう参考にすればよいのか。建築・不動産のプロに話を聞いた。
この記事でわかること
耐震基準とはどういうものか
「新耐震」と呼ばれる耐震基準は、いつからが対象か
不動産のプロが教える「地震に強い物件の選び方」
このページの目次
耐震基準とは? 3つの耐震基準を解説

耐震基準とは、建物が一定の強さの地震に耐えられるよう建築基準法で定められた、最低限クリアすべき基準である。大きな地震が発生するたびに見直され、改正・強化されてきた歴史を持つ。
耐震基準の目的は、まず第一に人命を守ることにある。そのため、一定の強さの地震に対して建物が容易に倒壊しない基準を定めている。しかし、地震後もそのまま安全に住み続けられることを保証するものではない点には注意が必要である。
建物は建った時が一番耐震性能が高く、築年数が経つにつれて劣化が進みます。大きな地震を何度も経験することで、耐震性能の低下は免れないことを理解しておきましょう。
旧耐震基準(旧耐震)とは
旧耐震基準(旧耐震)とは、1950年の建築基準法施行時に定められたもの。1981年(昭和56年)5月31日まで適用される。
新耐震基準(新耐震)とは
新耐震基準(新耐震)とは、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標とした基準である。1981年(昭和56年)6月1日に建築基準法が改正され、その中で新耐震基準が定義された。
現行の耐震基準「2000年基準」とは
2000年基準とは、1995年の阪神・淡路大震災の被害を受け、2000年(平成12年)6月1日から導入された基準である。現在、賃貸物件を新築する場合には、この2000年基準で建てられている。特に木造住宅の耐震性向上を目的とし、新耐震基準に加え、以下の3点が強化された。
強化ポイント①地盤に応じた基礎設計
地盤が弱いと建物が沈下したり、建物によっては基礎や構造躯体などにひび割れが生じたりするリスクがある。2000年基準では、設計時に地盤調査を行い、地盤の強さに応じて基礎の種類や仕様を決めることが義務化された。
強化ポイント②基礎や土台と柱の接合部への金具取り付け
地震の揺れによって柱や梁が抜けたりバラバラになったりしないよう、基礎や土台、柱や梁等の接合部に適切な金属製の接合金物を用いてしっかり固定することが求められるようになった。これにより、建物全体の剛性が高まり、倒壊リスクを大幅に減らすことができる。
強化ポイント③耐力壁のバランスのよい配置
耐力壁(建物を横揺れから守る壁)は、配置が偏ると地震時に建物がねじれるように変形して倒壊につながる恐れがある。2000年基準では、この「壁の偏り」を数値化し、適切な位置に必要な量の壁を配置することが義務づけられた。
旧耐震か新耐震かを確かめる方法
その建物が旧耐震基準で建てられたものか、新耐震基準で建てられたものか、築年数だけでは判断ができない。正確には「建築確認通知書」もしくは「建築確認済証」の日付を確認する必要がある。
建築確認とは、工事が始まる前に特定行政庁や指定確認検査機関へ申請し、建築基準法に適合していることを確認するプロセスのこと。「建築確認済通知書」の発行日が1981年6月1日以降なら新耐震基準で建てられていると判断できる。
建物の完成日は、申請から数か月〜1年以上ずれることもあるため、築年だけで判断すると正確さに欠ける。だからこそ「建築確認通知書」もしくは「建築確認済証」の日付が信頼できる判断材料になる。
ただし、賃貸の場合、建築確認済証を入居者が直接入手することができないため、不動産会社や大家さんに聞いて確認することとなる。
旧耐震の物件は避けたほうがいい?
1981年5月以前に着工された「旧耐震基準」の物件でも、その後に耐震診断を受けて耐震補強、耐震改修工事をしているケースがある。耐震診断の有無は、入居時の契約手続きの前に交付される「重要事項説明書」で確認できる。
重要事項説明書とは、不動産会社が入居者に物件の契約条件などを説明するための書類で、契約前に必ずチェックすることができる。
築年数が古い建物は、過去の地震で見えない部分の耐力が落ちている可能性もある。しかし、耐震補強・耐震改修工事には多額の費用がかかるため、実際には診断や補強が行われていない物件もある。安心して暮らすためには、旧耐震物件を検討する場合こそ、耐震補強や耐震改修の有無を慎重に確認することが大切だ。
特に築年数が古く、大きな地震を何度か経験している建物には、見た目ではわからないダメージが残っていることがあります。外壁にひび割れなどがなく、仕上げがきれいに見えても、内部では構造部分や接合部分が緩んだり、劣化が進んでいたりするケースがあるんです。
耐震基準と耐震等級の違い
耐震基準は、建物に住む人の命や財産を守るための最低限の基準である。建築基準法に定められたこの基準は、地震による倒壊や崩壊を防ぎ、人命を守ることを最優先としたものだ。
これに対し、耐震等級とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が定める「住宅性能表示制度」に基づき、建物が地震にどれだけ強いかを等級で示したものである。耐震等級には1から3までの等級があり、数値が大きいほど地震への備えが強化されている。
ただし、品確法に基づく住宅性能評価は任意の評価制度であることから、耐震等級の賃貸物件での利用はあまり多くない。
建築・不動産のプロが教える!地震に強い物件の選び方
地震に強い部屋を選ぶときに、まず大切なのは立地や地形である。ハザードマップを確認し、その地域に地震や液状化、浸水のリスクなどがあるかを把握することが大切だ。
そして、窓の大きさや数にも注目すべきだ。窓が大きく連続し、外壁が少ない建物は耐力壁が少なくなりがちで、揺れに弱くなる傾向がある。窓などの開口部の両側や建物の角に耐力壁が配置されているかどうかも強度を保つポイントとなる。
また、上下階のバランスも重要だ。柱だけで上部を支えているピロティ構造や、壁が少なかったり、見た目にも上下や壁の配置のバランスが悪かったりする建物は、揺れに弱い傾向がある。
さらに築年数が古い物件では、過去の地震によって見えない部分で耐震強度が低下している可能性があるため注意が必要である。地震に強い物件に住みたいという人は、不動産会社に過去の耐震補強、耐震改修の有無を確認しよう。
耐震性の高い部屋を選ぶなら、不動産会社に相談を
耐震基準は、建物が人の命や健康、財産を守るために定められたルールであり、大きな地震のたびにその内容が見直され、厳格化されてきた。
新耐震基準や2000年基準といった耐震基準を知っておくことや、気に入った物件がどの耐震基準で立てられているかを正確に確認しておくことが大切。お部屋探しの際には、不動産会社に「どの耐震基準を満たしているか」や耐震診断の有無、耐震改修・補強済の場合はその内容を確認するのが安心だ。
安全性をしっかり確かめながら、自分に合った住まいを選んでいこう。
2025年4月にも、建築基準法の大改正がありました。現在は、建築確認において、平屋の200㎡以下の建物を除く、ほぼ全ての建物について、構造の安全性のチェックが実施されています。
こうした法改正を通して、今後は、さらに耐震性や安全性が高く、品質の良い建物が増えてくることが期待されています。この記事をご覧の皆様にとっても、より安心して暮らせる住まいの選択肢が増えていくことでしょう。
「耐震等級」について知りたい方はこちら
地震から建物を守る「耐震」「制震」「免震」構造の違いはこちら
監修、取材協力:藤浦 誠一(株式会社エイブル)
文:佐々木正孝(キッズファクトリー)