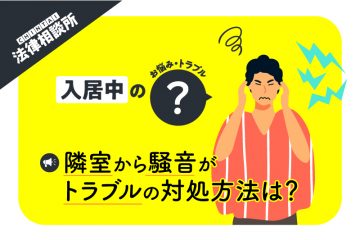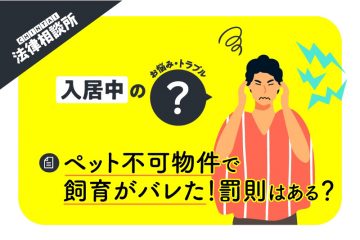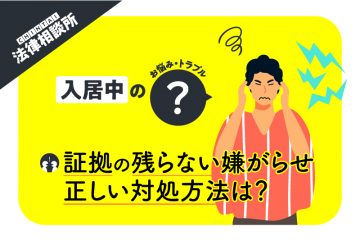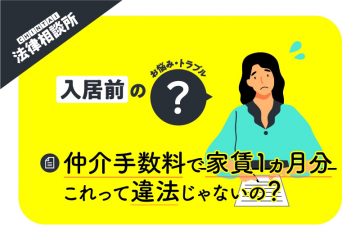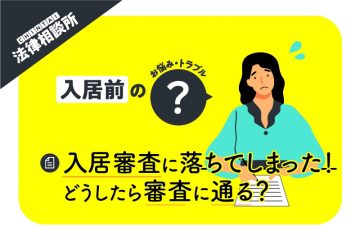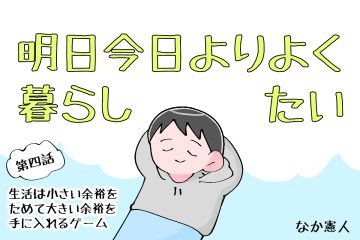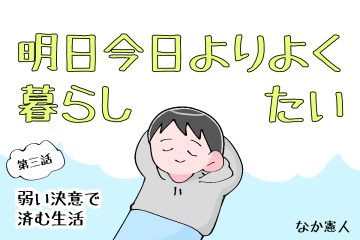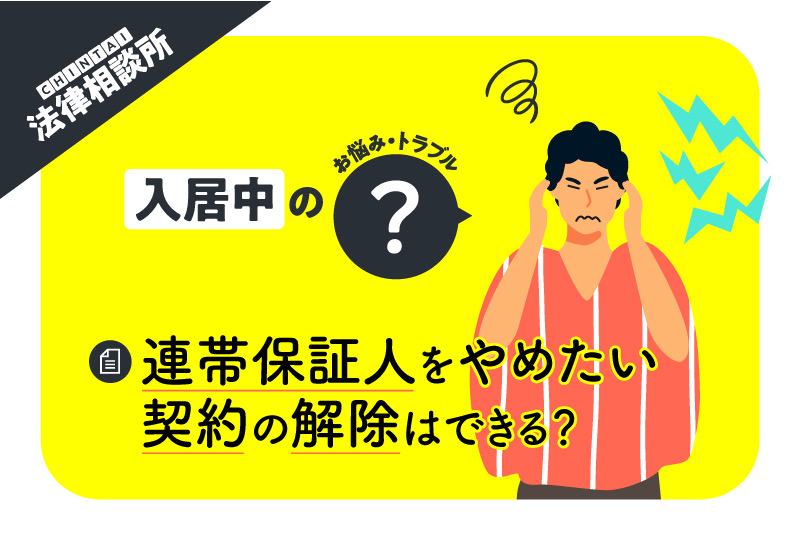
連帯保証人をやめたい! 契約の解除はできる? その方法は?【CHINTAI法律相談所】
賃貸物件に関する疑問に弁護士がアドバイス
賃貸にまつわるトラブルや疑問について解説する【CHINTAI法律相談所】。
入居前から入居中、退去時まで、さまざまなタイミングで発生しやすい賃貸トラブル。その疑問や対応について、不動産トラブルに強い瀬戸仲男弁護士に聞いた。
賃貸トラブルは、いつ巻き込まれてしまうかわからない。現在トラブルにあっている人だけでなく、これから賃貸物件を借りる予定の人もぜひ参考にしてほしい。
Q.連帯保証人をやめたいけど、契約って解除できる? 対処法を教えて!
友人に頼まれて、賃貸借契約の連帯保証人になった。だけど、やっぱりやめたい! 連帯保証人の契約って後から解除可能? できるのなら方法を教えて欲しい。
A.連帯保証人を解除するには大家さんの合意が必要
結論から言うと、連帯保証人を辞めることは難しい。連帯保証契約の「当事者」は「賃貸人」と「連帯保証人」であり、連帯保証契約の変更や解約には両者の合意が必要。当事者一方の都合で解除することはできない。
連帯保証人を辞めたいなら賃貸人、つまり大家さんの同意を得なければならない。
連帯保証契約の解除については法律で条件などが定められている訳ではなく、大家さんの判断に委ねられている。どのような条件なら合意してくれるかは大家さん次第となるが、最も妥当なのは別の連帯保証人を用意することだ。
大家さんに応じてもらうためには、より安心できる相手である人物であることが大前提。元の連帯保証人より資産や信用を有していることはもちろん(民法450条参照)、より関係性が深い相手の方が納得してくれやすいだろう。例えば、友人よりも入居者の親族の方が、大家さんも納得してくれやすいはずだ。
ただ、連帯保証契約は法的に強力な契約であるため、交渉によって解除は難しい傾向にある。代わりの連帯保証人を用意しても契約の解除に応じてくれない場合は弁護士や、「法テラス」などの専門機関に相談すると良いだろう。
詐欺や誤認で連帯保証契約を結んだ場合は契約を取り消すことができる
解除が難しい連帯保証契約だが、不成立を主張できる場合、あるいは取り消せる場合もある。例えば、無断で連帯保証人にされていた場合は、そもそも連帯保証契約は成立していない。
また、賃貸人に騙されて連帯保証人になった場合は、詐欺を理由に連帯保証契約の取り消しが可能。
賃借人に騙されて連帯保証契約を結んだ場合は「第三者による詐欺」(連帯保証契約の当事者である賃貸人と連帯保証人以外の者による詐欺)に該当する。そのため、賃貸人が詐欺の事実を知っている場合や、知ることができた場合、連帯保証契約を取り消すことができる。
誤認・勘違いで連帯保証契約をした場合も、錯誤を理由に取り消せることもある。取り消せば、連帯保証契約は無効となる。
さらに、特殊な事例として大家さんの対応を理由に解除できるケースもある。入居者が家賃を滞納しているにも関わらず連帯保証人に即連絡せず、数年分をまとめて請求した場合などは、保証の範囲が合理的な期間に限定され、連帯保証契約の解除も認められる。
これは「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」(民法第1条第2項)という“信義誠実の原則”に反するからだ。前述のように、大家さんが故意に滞納金を増やして回収することは決して誠実とは言えないため、契約解除が認められる可能性がある。
なお、大家さんの合意を得られた場合や、信義誠実の原則に反した場合でも、解除時点で発生している家賃滞納金などは支払わなければならないので要注意だ。
ここがポイント!
連帯保証契約は、契約者当事者の一方(保証人側)の都合だけでは解除できません。契約の解除もある意味で契約行為であり、相手の同意なしでは成り立たないのです。連帯保証契約を解除したいなら、大家さんと交渉する必要があるでしょう。そのためには、代わりの連帯保証人を用意するなど、相手が納得してくれる条件を提示することが肝心です。
覚えておきたい法律用語「連帯保証人」
連帯保証人は、入居者が家賃を滞納した場合に代わりに支払う義務を負う。その上で連帯保証人は、「催告の抗弁権」(民法452条)、「検索の抗弁権」(民法453条)を有せず(民法454条)、「分別の利益」(民法456条)も持たない。
民法第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。民法第453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。民法第456条
民法 – e-Gov法令検索
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
つまり、連帯保証人は家賃滞納金を請求されても「入居者(賃貸借契約の契約者)に先に請求すべき」と求める(催告の抗弁権)ことはできない。「入居者がお金を持っているから先に請求・執行すべき」と訴える(検索の抗弁権)ことも不可能。連帯保証人が複数いても滞納金の分担(分別の利益)を認められず、各連帯保証人は全額を支払う義務を負担する。
上記のように連帯保証人は、通常の保証人より重い担保責任を負っている。もちろん、これは大家さんの権利を守るための契約。そのため、連帯保証人の都合で解除を求める場合には、相応の代替案や交渉が必要となるケースが多い。
取材・文=綱島剛(DOCUMENT)
【CHINTAI法律相談所】入居中のトラブルについての記事はこちら!
【CHINTAI法律相談所】契約のお悩みについての記事はこちら!