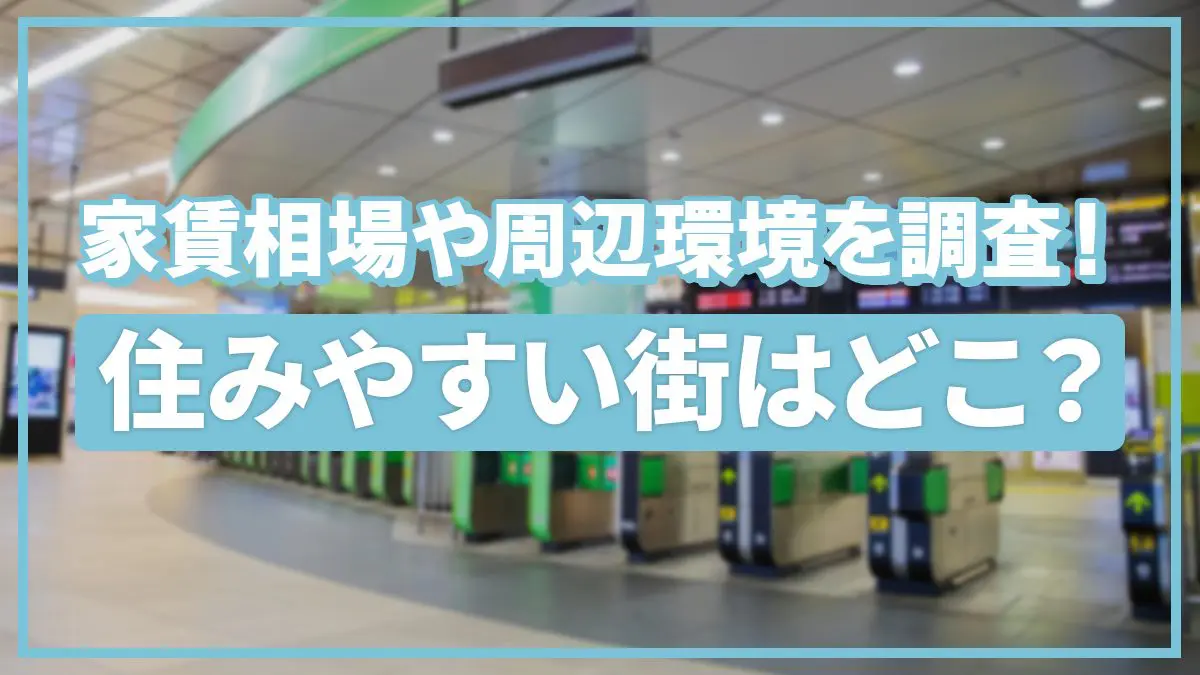賃貸物件における世帯主とは?同棲での決め方や変更手続きの方法を解説
この記事でわかること
賃貸アパートの世帯主は誰?一人暮らし・同棲での違い
そもそも世帯主とは?どうやって決まるの?
引越し後は住民票を移さないと罰金?
賃貸で一人暮らしする場合の世帯主は?
賃貸で同棲する場合の世帯主の決め方
同棲する際の世帯主の変更方法
友人との同居や「居候」の場合の世帯主はどう決める?
賃貸での世帯主の決め方を知って、スムーズに生活を始めよう
このページの目次 [表示]
賃貸アパートの世帯主は誰?一人暮らし・同棲での違い

一人暮らしや同棲を始める場合、新たに世帯主を決める必要がある。特に同棲カップルの場合、誰を世帯主にすべきなのかわからずに悩む人も多いだろう。
そこで今回は、世帯主の決め方・決まり方や変更方法などの情報を、引越しに合わせて住民票を移すべき理由と併せて解説していく。
▽関連記事はこちらもチェック!
そもそも世帯主とは?どうやって決まるの?
法律では明確に決まっていないが、世帯主の定義は基本的に、同じ住居に住む人の代表者と考えれば良いだろう。ただし、世帯主は誰でも自由になることができ、1つの家族に複数の世帯主がいても構わない。このように家族間で世帯を分けることを「世帯分離」と呼び、実際に親子で世帯分離しているケースも少なくはない。
ただし、夫婦の場合は民法に「協力・扶助」の義務があるため、世帯分離は原則として認められない。 夫婦の世帯分離を希望する場合、生計の実態が夫婦別々であることを証明するための手続きが必要だ。 手続きは住居の地域を管轄する市区町村役場で行える。
引越し後は住民票を移さないと罰金?
「住民基本台帳法」により、引越し後は14日以内に住民票を移すことが定められている。正当な理由なく届出をしなかった場合、5万円以下の過料に処される可能性がある。なお、「正当な理由」には以下のような内容が含まれる。
<住民票移動の延期が認められることが多い正当な理由>
- 転居先に住むのが一時的で、1年以内に元の住所に戻る見込みがある場合
- 定期的に実家に戻るなど、生活の拠点が変わらない場合
- 新型コロナウイルスの影響による外出自粛などで役所に足を運べない場合
正当な理由と認められずに住民票の移動を無視していると、過料のほかに選挙権を得られなかったり、運転免許証を更新できなかったりといった不都合が生じる。余計なトラブルに遭わないよう、引越し後はなるべく早く住民票移動の手続きを行うようにしよう。
次は、同棲をするときの世帯主の変更方法や「居候」の場合の世帯主の決め方をご紹介する。
賃貸で一人暮らしする場合の世帯主は?
大学生や単身赴任など、実家が別にあって一人暮らしをしている場合は、世帯主は「住民票を一人暮らしの賃貸物件」に移しているかどうかで決まる。住民票の扱いによって、世帯主はどうなるかを見ていこう。

住民票を賃貸アパートに移した場合は、本人が世帯主
一人暮らしを開始する際に住民票をアパートに移した場合、その物件には一人しか暮らしていないのだから世帯主は自分自身だ。公的書類などに「世帯主との続柄」を書く場合、「本人」と記載すればよい。
住民票を実家のままにしている場合は、世帯主も実家
一人暮らしをしていても、前述の「正当な理由」があり住民票を移さずに実家の住所のままにしている場合、実家の世帯主がそのアパートの世帯主となる。実家の住民票を見れば正確に確認できるが、実家で主に生計を支えている人、つまり収入が多い人が世帯主となっている場合が多い。
学生なら実家の父親や母親というケースが一般的だ。
また、単身赴任の社会人の場合も同様に住民票の記載に従うこととなり、世帯主は自分または配偶者となる場合が多いだろう。なお、書類に住所と世帯主を書く場合、親が世帯主なら世帯主との続柄は「長男」あるいは「長女」、配偶者が世帯主の場合は「夫」または「妻」となる。
賃貸で同棲する場合の世帯主の決め方
話が少し複雑になるのが、「同棲」、つまり、未婚のカップルが二人暮らしをする場合だ。世帯主には以下のパターンが考えられるので、順番に見ていきたい。
- 住民票を双方とも同棲するアパートに移し、二人とも世帯主となる
- 住民票を双方とも同棲するアパートに移し、一人を「未届の妻(夫)」または「同居人」とする

同棲カップルの世帯主パターン➀:二人とも世帯主となる
「1つの物件に2人の世帯主ってあり得るの?」と思うかもしれないが、これは可能だ。双方とも別々に住民票を作成し、自分を世帯主とすれば良い。
未婚カップルの同棲の場合、同じ物件に住んでいてもそれぞれに収入があり、生計は別という場合も多い。そのため、それぞれが独立した世帯主として考えることができるのだ。
この場合、お互いに一人だけの世帯を構成することになる。そのため、何らかの手続きの際に書く書類の世帯主の続柄欄には、二人とも「本人」と書けば良い。職場に住民票を提出するときに、同棲していることを職場の人に知られずに済むので、同棲していることを知られたくない方にとっては大きなメリットといえる。
ただし賃貸契約を行う場合、不動産会社には二人で暮らすことをきちんと伝えなければならない。賃貸契約の際に交わす重要事項説明書や契約書などの書類では、「入居者数は一人」「二人入居不可」などと明示されている場合が多い。一人で暮らすという契約にしておいて、こっそり二人で暮らすということになると契約違反となり、最悪の場合は退去を余儀なくされてしまう可能性もあるので十分注意したい。
なお、パターン①のカップルが賃貸契約を行う際には二人分の住民票を提出して契約することになる。
同棲カップルの世帯主パターン②:一人を「未届の妻(夫)」「同居人」とする
パターン①とは逆に、未婚の場合でも住民票を二人で1枚にすることは可能だ。この場合は、アパートの世帯主をどちらか一人にして、もう一人を「未届の妻(夫)」または「同居人」として届け出ることとなる。世帯主との続柄には、届出を行った内容のまま「未届の妻(夫)」または「同居人」とすれば良い。
住民票を1つにするメリットは主に2点。生計を一にしている証明となり、健康保険や公的年金の扶養対象にできることと、委任状なしでお互いの住民票を取得可能となることだ。
一方でデメリットもある。カップル関係の解消(やそれに伴う同棲の解消)をする場合、改めて住民票の異動届を出し、世帯を分けるという手間が発生する。
同棲する際の世帯主の変更方法
何らかの事情により、世帯主を変更したくなる場合もあるだろう。そのような場合、以下のような手順で手続きを行うことで世帯主を変更できる。
世帯主変更の手続きは誰が行う?
世帯主変更届を提出できるのは、原則世帯主もしくは世帯員のみ。ただし、世帯主か世帯員の委任状(代理人選任届)を持った代理人でも手続きを行うことができる。
委任状には、委任する世帯主か世帯員の住所・氏名・生年月日・捺印が必要となる。また、代理人自身の住所・氏名・生年月日を記入したうえで、世帯主変更届について委任する旨を記載しよう。
世帯主変更の届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類の原本
- 印鑑
- 世帯全員分の国民健康保険被保険者証
本人確認書類として、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートや健康保険証などを用意しよう。国民健康保険被保険者証は、国民健康保険に加入している場合のみなので、会社の健康保険組合に加入している場合は必要ない。
また、代理人が届け出る場合は、委任状と委任者の本人確認書類のコピーが別途必要となるので注意しよう。
世帯主変更を届け出るタイミング
世帯主変更届は、変更があった14日以内に届け出るよう心がけよう。前述の通り、住民基本台帳法という法律では、変更があった旨を14日以内に市町村長に届け出なければならないと定められているので、速やかに手続きを行う必要がある。
友人との同居や「居候」の場合の世帯主はどう決める?
友人との同居や「居候」の場合でも、ここまで説明してきた同棲カップルの考え方と同じだ。住民票を移す場合、それぞれ二人が世帯主となることも、友人を世帯主として自身は「同居人」として届け出ることも可能である。
どちらの場合も、友人宅の賃貸契約において二人以上の入居が認められているかどうかを必ず確認するようにしよう。

賃貸での世帯主の決め方を知って、スムーズに生活を始めよう
今回は、世帯主とは何なのか、どうやって決める・決まるのかについて詳しく解説した。世帯主は、一人だけでなく複数人にしても良い。同棲をスタートする際、あるいは友人と同居する場合には、それぞれの意思を確認したうえで世帯主を決定しよう。
また、世帯主は途中で変更することもできる。今回紹介した手順や必要書類等を参考にしながら、必要に応じて手続きを進めていただきたい。
文=墨染みすず
2023年10月加筆=CHINTAI情報局編集部