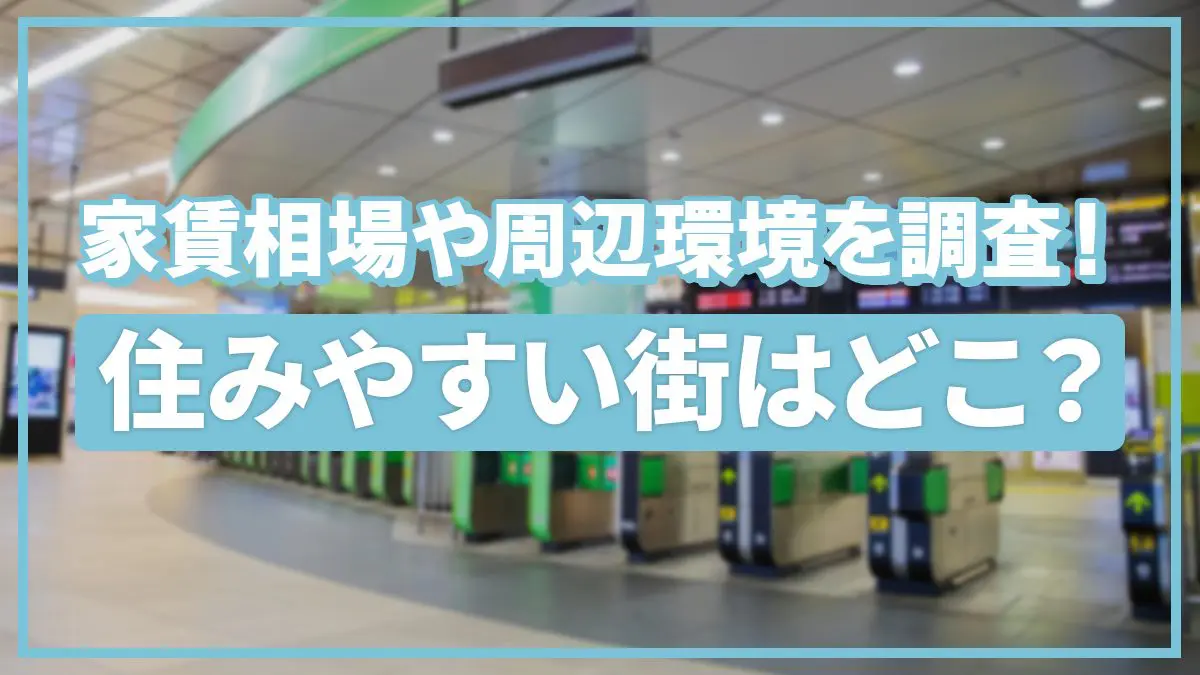子育てに優しい街10選!妊娠・出産・育児に対するサポートが手厚い自治体をご紹介
このページの目次 [表示]
子育てに優しい街が知りたい!妊娠・出産・育児に対するサポートとは?
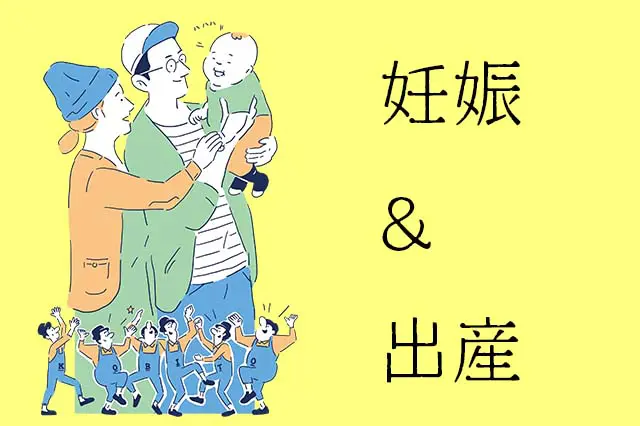
保護者の健康的・精神的な負担は、子育ての環境にかなり左右される。子どもを育てやすい街に住むことは、子育てにおいてかなり重要だといえるだろう。
近年、妊娠・出産・育児に対する支援を積極的に実施している街は多い。
今回は、その中でも特に妊娠・出産・育児のサポートが充実している自治体を選んで紹介していこう。
【子育てに優しい街】妊娠に対するサポートが手厚い3つの自治体
家族が増えることをきっかけに、妊娠のタイミングで引越しを考える人は多い。そのためか、妊婦さんの手助けをしてくれる特典のある自治体が近年急増している。
体力的にも経済的にも苦労が絶えない妊娠~出産期を手助けしてくれるのは、つわりで苦しい妊婦さんのための家事ヘルパー援助や、妊婦健診に通うためのタクシー代補助などの助成金制度だ。
また、妊娠健診費の助成は国で定められているが、助成額は地域によってさまざま。健診費だけでなく、超音波や各種検査の助成があるかなどもチェックしよう!

妊娠のサポートが手厚い街① :埼玉県 戸田市
格安の料金で家事ヘルパーを派遣
戸田市では、妊娠中から出産後1年未満の人を対象に、家事・育児のヘルパーを派遣している。
1ヶ月に12日(多胎児は15日)まで利用可能で、掃除や洗濯、食事の準備などのさまざまな家事を代行することで妊娠中の負担を軽減してくれる。利用料は1時間あたり900円。民間の家事代行業者を利用する場合の相場が、1時間あたり2,500円前後であることを考慮すると格安といえる。
※参考:戸田市ウェブサイト
妊娠のサポートが手厚い街②:千葉県 栄町
1時間520円で家事・育児をヘルパーが代行してくれる!
栄町では妊婦への支援事業として、1時間520円で家事・育児を代行してくれるヘルパー派遣のサポートがある。妊婦だけではなく、小学校就学前の子どもをもつ保護者も対象だ。
連続7日、1時間単位で1日4時間まで利用できる。買い物や料理、掃除、洗濯など、妊婦だと大変な家事を安価で任せることができる。親が遠く離れているなど、頼れる人が身近にいない家族にはうれしい。
※参考:栄町ウェブサイト
妊娠のサポートが手厚い街➂:埼玉県 越生町(おごせちょう)
タクシーの初乗り運賃を町が負担
越生町では、妊娠期の母体への負担及び経済的負担の軽減を目的に、妊婦が産婦人科への通院等の外出でタクシーを使用した際の初乗り料金相当額を助成してくれる。
※参考:越生町ウェブサイト
【子育てに優しい街】出産に対するサポートが手厚い3つの自治体
出産に対するサポートとして、住んでいる地域にかかわらず受けられる制度として「出産育児一時金」がある。
出産育児一時金は、入院・分娩費として妊娠4ヵ月以降の出産の場合、1人あたり42万円がもらえる制度。
健康保険に加入していれば誰でも受けられる。出産退院時に差額分だけを支払えば良いという仕組みになっている。
ただし、それでも平均8万円近い自己負担は手痛い出費。
さらに生まれてくる赤ちゃんの準備にもお金がかかる。
そんな時、自治体独自の出産サポート制度があれば有難い。それぞれの自治体の制度をチェックしてみよう!

出産のサポートが手厚い街①:東京都 渋谷区
1人の出産につき最大10万円を助成
渋谷区では「ハッピーマザー出産助成金」として、子ども1人の出産につき、最大10万円が助成される。誕生祝い品や子育て応援券といった金券など、出産時に特典を設けている自治体は多いが、その中でも1人の出産につき最大10万円の助成というのは一際目立つ。
また、第1子出産から助成を受けられるところにも注目したい。ただし、出産の3ヶ月前から申請日まで渋谷区に住民登録をしていることが条件となる。また、産後の子育てに関する講義をほぼ毎月行っているので、出産前に足を運んでみよう。
※参考:渋谷区ウェブサイト
出産のサポートが手厚い街②:東京都 練馬区
第3子以降の出産1人につき10万円を支給
練馬区では子育て家族の支援を目的に、第3子以降の出生1人につき「第3子誕生祝金」として10万円を支給している。第3子出産の1年以上前から練馬区に住民登録があり、引き続き練馬区に居住する意思があることなど条件があるので注意が必要。
独自制作の育児応援動画「赤ちゃんが来る!! もうすぐパパになるあなたへ」を配信するなど、妊娠期のパパを啓蒙する取り組みもある。小児科の多さや広い公園などで子育てのしやすい街として知られる練馬区。妊娠出産期の手厚い施策にも注目だ。
※参考:練馬区ウェブサイト
出産のサポートが手厚い街➂:埼玉県 久喜市
第5子以降の出産なら25万円の祝い金
久喜市では出産を奨励し地域社会を活性化することを目的に、第3子以降の出産に対して「すくすく出産祝金」を支給している。第3子出産で5万円、第4子出産なら10万円、そして第5子以降の出産には25万円の祝い金がそれぞれ贈られる、子だくさんの家族に大変優しい街だ。
ただし出産の1年以上前から住民登録されていることが条件。妊娠発覚後に引越しても対象外なので注意が必要だ。
※参考:久喜市ウェブサイト
▼合わせて読みたい!
埼玉県さいたま市が暮らしやすい理由を編集部が徹底調査を行った。
アクセス、おすすめポイント、賃貸物件、の観点からさいたま市の一人暮らしのしやすさを解説!
都内で一人暮らしを考えていた人も埼玉県の魅力に気付けるかも?
【子育てに優しい街】育児に対するサポートが手厚い4つの自治体
令和元年10月から、国立・公立・私立、すべての幼児教育・保育の無償化が開始された。基本的に3〜5歳児は収入制限なし、0〜2歳は非課税世帯で無償化の対象となっている。ただし、制度の対象となるには、保育の必要性の認定を受けなければならない。保護者が仕事をしていたり、妊娠や出産のためであったり、親族の介護をしていたりなど、なんらかの理由が必要だ。
また無償化といっても、給食費や教材費など一部の費用は有償のままとなる。
何かとお金のかかる子育てに対し、多くの助成金や特典がもらえる街を4つ紹介する。

育児のサポートが手厚い街①:千葉県 松戸市
託児機能付きのコワーキングスペースを無料で利用できる
2021年、共働きで子育てしやすい街ランキング(日経xwoman・日経新聞発表)において1位を獲得した千葉県松戸市。千葉県内初となる「託児機能付きのコワーキングスペース」を設置している。乳幼児の一時預かりは1時間で500円と格安。一時預かり利用者は併設したコワーキングスペースやカフェスペースの利用が無料だ。子どもの近くで様子を見ながら仕事ができるのは安心だ。首都圏の自治体としては保育所の定員にも余裕があり、保育所の園庭保有率も80%と高い。
※参考:松戸市ウェブサイト
育児のサポートが手厚い街②:東京都 葛飾区
補助金・助成金制度が充実している
東京都葛飾区では、私立幼稚園の入園補助金が最大8万円、さらに給食費も日額375円が支給される(園に直接助成)という太っ腹な制度がある。また、新制度の私立幼稚園・認定こども園であれば、保育料以外に徴収される負担金も月額5,300円まで助成される。
独自支援として「三人乗り自転車購入助成金」というおもしろい制度もあり、自転車の購入金額の2分の1、上限3万円まで支給される。事前申請が必要なので区の支援課に確認しておこう。
さらに、葛飾区では3歳未満の子どもをもつ母親の健康診断を無料で実施している。後回しになりがちなママの健康に配慮されたうれしい制度だ。
駅周辺の繁華街を離れれば閑静な住宅地が並ぶ葛飾区。治安は良く子育てに向いている街といえるだろう。
※参考:葛飾区ウェブサイト
育児のサポートが手厚い街➂:東京都 豊島区
保育所・学童に入りやすく、医療費負担のサポートが手厚い
豊島区は需要を見越した保育所拡充施策により、2017年度から毎年待機児童ゼロを達成している。保育所の入りやすさで子育て世帯に魅力ある街といえるだろう。
さらに小学校6年生までの希望者全員が待機することなく学童に入ることができる。保護者の弁当作りの負担を軽減するために、宅配弁当を導入しているのもうれしい。
また、中学校3年修了前まで子どもの医療費の自己負担分はすべて無料になる。薬も無料なので、安心して病院に連れていくことができそうだ。
※参考:豊島区ウェブサイト
育児のサポートが手厚い街④:埼玉県 さいたま市
独自の優待カードでさまざまな特典を受けられる
さいたま市では、妊娠中〜小学校6年生まで1時間1,000円で家事と育児のサポートを受けられる。ただし1歳から小学校6年生までは保護者の体調不良など、家事が困難な場合に限る。
また、さいたま市でも中学校卒業前までの子どもの医療費を全額助成する制度がある。何かとお金がかかる子育て中の医療費無料化はうれしい施策だ。
また、妊婦と18歳以下の子育て世帯を対象として「パパ・ママ応援ショップ優待カード」が配布される。この優待カードを協賛店舗で提示すると各店舗によって、さまざまな特典を受けられる。
妊娠・出産・子育てに優しい街を知って、安心して子どもを迎えよう!
今回は、妊娠・出産・子育てにおいてサポートの手厚い自治体を厳選して紹介した。
子育て支援のサポートは、実は街によってかなりの差があるのだ。これらの制度を知らないままだと、子どもが成人するまでにかかる費用や、精神的な負担がかなり違ってくる可能性もある。
妊娠中や育児中の街選びは保護者にとってとても大事な選択だ。
妊婦さんやパパママに優しい街に住んで、妊娠中や育児中のストレスを軽減し、すてきな子育てライフを送ろう。
2022年2月加筆=CHINTAI情報局編集部