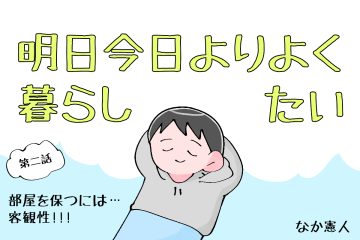本当に役立つ防災リュックの備え方を防災士が解説!自分や家族に合う中身を準備しよう

地震は、地下で起きる岩盤(プレート)のズレによって発生する。日本周辺には複数のプレートによって複雑な力がかかっているため、日本は世界でも有数の地震多発地帯である(※1)。また、位置だけでなく地形や地質、気象などの条件から、台風や豪雨、土砂災害や火山噴火などによる災害が発生しやすい(※2)。
災害への備えには、個人が取り組む「自助」、地域や身近な人と取り組む「共助」、国や自治体による「公助」の3種類がある。中でも基本となるのは「自助」。災害に備え、一人ひとりが命や身の安全を守る対策をすることが重要だ。
自助のための備えとして一人ひとり用意したいのが「防災リュック(非常用持ち出し袋)」。今回は熊本地震を経験された防災士の松永りえさんに、「本当に役立つ防災リュックの備え方と中身」について、お伺いした。
※1 出典:地震発生のしくみ|気象庁
※2 出典:災害を受けやすい日本の国土|内閣府 防災情報のページ
このページの目次
非常時に持ち出す「防災リュック」が必要なワケ
「防災リュック(非常用持ち出し袋)」は、地震が発生してから1~2日を生き抜くために最低限必要な水や食料、衛生用品や日用品を詰めたもの。家族一人ひとりが、各自1つを用意するのが原則だ。
「防災リュック」と聞くと、「本当に必要?」「避難所に行けば水や食料を受け取れるのでは?」という疑問を持つ人もいる。編集部でも実際に用意している人は少なかった。
まず、防災リュックが活用できる場面を紹介する。
- 「近くの川が氾濫しそう」「住んでいる街で津波警報が出た」など自宅が危険な状態で避難所に行く場合
- 自分の家や、同じ建物内、近所の家が火事になった場合
- 地震などで家に閉じ込められた場合
このような有事の際、防災リュックは活用できる。背負って逃げるだけでなく、それがあれば1~2日命をつなぐことができる「安心感の塊」なのだ。
防災リュックは災害時に使える、「お守り」であり「相棒」。本当に役立つリュックを一緒に用意しましょう。
既製品を買うだけじゃダメ? 本当に役立つ防災リュックの備え方

松永さんは「一般的に販売されている防災リュックでもいいが、完璧なものは存在しない」と語る。既製品に、自分に必要なものを足したり引いたりしてカスタマイズすることで、本当に役立つ防災リュックになるそうだ。
市販の防災リュックは多くの人が使えるようにするため、「最大公約数」でみんなが必要だと想定される中身を揃えている。そのため「余分なモノが入っており、重くて背負えない」「自分に必要なもの(メガネや持病の薬など)が入っていない」など、不具合も出てくる。
重くて背負えないなら、必要最低限のモノに減らす必要がある。また自分に必要なアイテムはもちろん「推し活グッズ」や「お気に入りのアロマ」などを入れるのも有効だ。
「これがあれば勇気づけられる」「心が落ち着く」といったアイテムは、災害時にも元気を与えてくれます。
既存の防災リュックが役に立たないことも
買ったまま置いておいた防災リュックが、「いざという時に使えなかった!」ということも起こり得る。下記のようなケースがあるという。
- 持病の薬や眼鏡など、自分に必要なモノが入っていなかった
- 水や携帯用トイレの数が足りない
- 非常食の消費期限が大幅に過ぎていた
- ウエットティッシュや除菌シートなどが乾いていた
- ペットの備えを用意できていなかった
- 防災ラジオ用の電池が入っていなかった
- 使い方がわからない防災用品があった
- 夏に被災したのに防寒グッズばかりが入っている
防災リュックは買ったらたらおしまいではなく、中身や使い方を確認しよう。最低でも季節が変わる半年に1回は見直し、常に今の自分に必要なモノに合わせてアップデートするとよい。
自分でつくる!本当に役立つ防災リュックづくりのポイント

ここからは、松永さんに教えてもらった「自分で防災リュックをつくるときのポイント」を紹介していく。
1.使わなくなったリュックでオリジナル防災リュックを作ってみる
既製品の防災リュックを買って、自分に必要な中身にカスタマイズするのも良いが、せっかくなら馴染みのあるリュッを使って自分だけの防災リュックを作ってみるのも◎。
ただし、容量の大きい登山用などのリュックは、詰め込みすぎて持ち運べなくなる可能性もあるので、無理なく背負って歩けるサイズのものがよい。
災害時のことを想像して、「自分に必要なものは何か」「どんな場面が想定できるか」を考えることが防災の第一歩になります。命をつないでくれる「お守り」を、自分の手でつくってみましょう。
2.状況に合わせた防災リュックを1人1つ用意する
例えば、妊娠中の方や乳幼児がいるなら母子手帳、高齢者なら介護用品、ペットがいるならペットシーツやフードなど、必要なものは各自違う。
また、子どもが自分でリュックを背負えるようになったら、子ども用の防災リュックをつくってあげよう。お菓子やおもちゃなど、無理なく持てる範囲でOK。親子で一緒に中身を考えることで立派な防災訓練になる。
3.災害直後、すぐに使うものから優先的に入れる
そもそも防災リュックには、災害が起こってから1~2日を生き抜くために必要最低限のものを入れる。誰しも必要な「水・食料・携帯トイレ」は最優先で入れよう。それ以外で入れるとよいアイテムは後ほど紹介する。
必要な量は人それぞれですが、私は水を500mlペットボトルで3L以上、携帯トイレを10回分、食料を2日分入れています。断水時、給水所には長蛇の列ができるので水は最優先で準備したいです。
4.種類ごとにパッキング
「衛生用品」「食料」「充電器やケーブル」など、ジャンルごとにジッパー式のビニール袋に小分けしてリュックに詰めるとよい。ジッパー式のビニール袋は防水になり、避難所生活でも役立つ場面がある。袋に入れる際は空気を抜き、防災リュックがパンパンにならないようにすること。
5.リュックは持ち運べるサイズ感と重量に
松永さんによると、熊本地震の際は重くて運べず、避難所までの間に防災リュックの中身を捨てる人もいたという。
災害時、避難所までの距離を急いで移動できる程度の重量に抑えよう。
政府広報オンラインでは「非常用持ち出し袋(防災リュック)で持ち出せる重量は、成人男性15kg、成人女性10kg、子ども・高齢者6kg」という目安が示されている(※3)。しかし、体力は人それぞれ。身の安全を守りながら10kgの荷物を背負って運ぶのはなかなかきつい。
※3 出典:災害に事前に備える|政府広報オンライン
防災リュックをつくったら、まずは背負ってみて、できれば「指定緊急避難場所」(※4)まで歩いてみよう。指定緊急避難場所と避難経路の確認方法は、国土地理院のホームページで確認できる。
避難場所の確認と経路を調べる|地理院地図の使い方 – 国土地理院
※4 指定緊急避難場所とは:災害の危機から命を守るために緊急的に避難する場所
6.閉じ込められた時の対策・防犯対策も肝心
防災ホイッスルは、閉じ込められた時などに居場所を知らせる役目があるが、災害時に増えてしまう犯罪対策にも使える。リュックのファスナーの持ち手に付けたり、前方のポケットに入れたり、すぐに使えるようにしておこう。
また、防犯ブザーや小型のライトなども、防犯に役立つのですぐ取り出せる場所に入れておきたい。
7.中身は買ったらすぐ動作確認して、年2回見直しを
防災リュックの見直しのポイント(出典:松永りえ Instagram)
使える防災リュックにするために、ラジオや懐中電灯などを購入したらまずは動作確認をしよう。そして年に2回は、食料の消費期限が過ぎていないか、電池は入っているかなど見直しをしよう。
今はおいしく食べられる非常食がたくさん発売されてるので、食指が動くもの・季節に合ったものをローリングストックする(古いものから食べ、食べた分を買い足す)とよい。
また、冬に向かうなら防寒用具を多めに入れる、夏ならネッククーラーや瞬間冷却パックなどの暑さ対策を万全にするなど、季節ごとの入れ替えも大切。
「完璧な防災リュック」を目指して、私の家では半年に1回(3月11日と9月1日ごろに)情報とアイテムをアップデートしています。
8.「好きなモノ」を入れておく
先にも触れたが、避難所で生活するようになるとイライラしたり、精神的に追い詰めらたりすることもある。そんな時に役立つのが、「好きなお菓子」や「推し活グッズ」などの自分にとって癒やしになる・テンションを上げてくれるアイテム。
重さや必需品などとのバランスを考えて自分の好きなモノ、心が落ち着くモノを入れておくとよい。
本当に役立つ防災リュックの中身とは

ここからは、松永さんがおすすめする防災リュックの中身を紹介していく。
防災リュックに必ず入れるのは、「水・食料・携帯トイレ」
水
1~2日分の水、約3L以上を500mのペットボトルで用意する。空腹はある程度我慢できても、のどの渇きは耐え難い。最優先で準備しよう。
食料
1~2日を乗り切れる量を準備する。必要な量も好みも人それぞれなので、自分に合った量や種類を用意すればOK。食べ慣れたお菓子や、唾液が出る飴などもおすすめ。
携帯トイレ
トイレの回数は人それぞれだが、松永さんは1日あたり5回分 × 2日分で10個の携帯トイレをリュックに入れているという。「トイレは避難所にあるのでは?」と考える人もいるが、トイレはどこも長蛇の列で、すぐに詰まって使えなくなるので、安心はできない。
衛生品
避難所では集団生活を送ることになるため、なるべく清潔な状態を保って病気を予防したい。また、水はふんだんに使えないため、水なしで使えるアイテムを優先して準備したい。
- マスク(10枚ほど。感染症や粉塵対策)
- 救急セット(絆創膏や消毒液、ガーゼなど)
- タオル
- 歯みがきシート(歯ブラシやマウスウォッシュでも)
- 使い捨ての手袋
- ウエットティッシュ
- 除菌シート
- トイレットペーパー(備えつけの紙はすぐなくなる。潰して入れるといい)
- (女性の場合)生理用品
- サバイバルシート(エマージェンシーシートとも。緊急時に体温を保持するための薄い保温シート。シャカシャカ音がしにくいタイプを選ぶと避難所でも気になりづらい)
万能アイテム
必要最低限のモノにおさえたい防災リュックには、1つで何役にもなるアイテムを入れておこう。
- ごみ袋(防寒具や布団にも使える。着替えやトイレの目隠しになるので黒くて容量の大きいものを複数枚入れよう)
- レインコート(100均のものでもOK。防寒具にもなる)
情報と安全を得るためのグッズ
災害時、情報は自分で取りにいく必要がある。ラジオや災害・危機管理情報に関する首相官邸のXアカウントなどで得られる公的な情報以外にも、ご近所のコミュニティなど、つながりを駆使して信頼できる情報を入手しよう。
ご近所のコミュニティに所属しておくと「あの公園に給水車が来ている」「○○で炊き出しが始まった」などリアルタイムの情報が早く得られる可能性がある。
- 財布と通帳、マイナンバーカードなどの貴重品(パスポートケースなどにまとめるとよい)
- 家族の連絡先や身分証明書のコピーなどをまとめたファイル
- 大容量のモバイルバッテリー(ソーラーバッテリー付きだとさらに便利)
- 充電コード
- 懐中電灯やネックライト
- 小銭(人によるが5000円分程度、食料や水などを購入する分や交通費など)
- 電池式のラジオと乾電池
- 防犯ブザーまたは防災ホイッスル
救助や復旧作業に役立つアイテム
防災リュックには、救助や復旧作業を安全に行うためのアイテムを入れておくとことも有効。
- 布製ガムテープ(貼って名前を書いたり、応急処置やモノの固定にも使える)
- レジャーシート
- 油性マジック
- 軍手
- 万能ナイフ
- 踏み抜き防止インソール(釘やガラスなどから足を守ってくれる)
ゴミ袋やレインコートなどの消耗品は100均でも揃えられます。懐中電灯や防災ラジオなどは、信頼できるメーカーのものが安心です。
家の備蓄品も忘れずに用意を!
なお、防災リュックに入れるモノとは別に、家に備蓄しておくべきものについても用意しよう。東京都防災HP「東京備蓄ナビ」を参照するとよい。カンタンな質問に答えて自分や家族に合う備蓄がわかるツールもある
参考サイト:自分に合った備蓄を調べてみよう | 東京備蓄ナビ
防災リュックは用意するだけで意識が変わる!
自分や家族にぴったりな防災リュックを準備すると、「自分は普段どんな暮らしをしているか」「災害時は自分に何が必要か」を考えることになり、結果的に防災意識がより高まる。
そして防災リュックはすぐに持ち出せるように、玄関近くや玄関収納の中など、避難経路の途中に置くのがおすすめ。一度防災リュックを準備するとそのままにしがちだが、中身は季節が変わる半年に1回見直し、動作確認なども行おう。
防災リュックは、災害時の命を守るための「安心感の塊」であり「お守り」でもある。水や食料、衛生品などの必需品だけでなく、お気に入りのお菓子や心が落ち着く・テンションが上がるアイテムを入れて、楽しみながら自分だけの防災リュックを用意しよう。
監修・取材協力:松永りえ
参考書籍:松永りえ『地震に強い収納のきほん』
取材・文:元井朋子
賃貸物件でできる地震対策についてまとめた記事はこちら