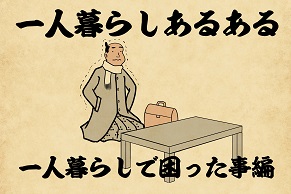【解説】映画『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』が示す“ゲームが人生にもたらす影響”
このページの目次
映画『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』の魅力を解説

ゲーム『バイオハザード』シリーズの大ファンであるアナウンサーの鈴木史朗氏は、2008年にこのような言葉を残している。
「一つの出来事、小さいことを達成していくことによって、人間って成長するわけですよね。ゲームを悪く言う人もいますけど、辛抱する心、恐怖に耐える心、苦痛に耐える心をゲームが与えてくれる」
この言葉通り、ゲームは楽しい娯楽だけにとどまらず、時には人間としての成長も促してくれるのかもしれない。2020年現在では、eスポーツ業界では多数のプロゲーマーが活躍し、知育ゲームや自宅で気軽にフィットネスができるゲームなどが人気を博し、その有用性や教育的価値への認識がさらに高まりを見せているのは周知の通りだ。
そして、本日1月10日に金曜ロードSHOW!で地上波放送される映画『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』も、はっきりとゲームを通じた人間の成長を描いた、“娯楽でありながら実は教育的でもある”素晴らしい映画である。その魅力を、以下に解説していこう。
※以下からは大きなネタバレのないように書いているが、一部の展開や設定については触れている。予備知識なく本編を観たいという方は注意してほしい。
ゲームを通じて他者と向き合い自分を知ることに意義がある!名作青春映画『ブレックファスト・クラブ』との共通点とは?

本作のあらすじは、それぞれ学校で問題行動を起こした4人の高校生が居残りを命じられ、その罰として地下室の掃除をしていると、正体不明のゲーム“ジュマンジ”を見つける。いざプレイしようとすると、4人はテレビ画面の中に吸い込まれ、それぞれのアバター(ゲーム内のキャラクター)に変貌していた……というものだ。
当然、そこには次々にあらわれる困難なステージをクリアーしていくという、まさにゲームそのものの面白さがある。随所に“ゲームあるある”なギャグも盛り込まれており、決まりきった言動しか口にしないNPC(ノン・プレイヤー・キャラクター)が登場するシーンでは、名作マンガ『レベルE』や『ハンター×ハンター』のグリードアイランド編を思い出す方もいるだろう。
さらに、『転校生』や『君の名は。』にも通じる“その人の中身が入れ替わっている”様も愉快で仕方がない。キャストには豪華な芸達者が揃っており、特に筋肉ムキムキのドウェイン・ジョンソンがイケテないオタク少年を“ヘタクソなキス”を含めて見事に演じきり、髭面で小太りのジャック・ブラックに今時のスマホ依存症の少女が“憑依”している様には、笑いを超えて感動を覚えたという方も少なくはずだ。
そんなわけで、難しいことを何も考えなくても、誰もがケラケラと笑って楽しく観られる『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』なのだが、重要なのは「自身に問題を抱えた生徒たちが放課後に居残りをする」ことが物語の発端になっているということだ。ここは、名作とされる1985年の青春映画『ブレックファスト・クラブ』が明らかに下敷きになっている。
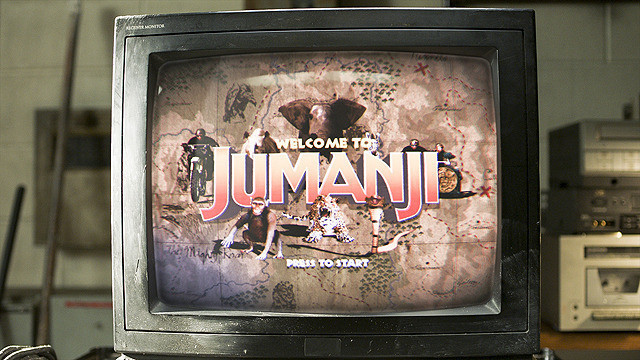
『ブレックファスト・クラブ』のあらすじは、懲罰登校および“自分とは何か”をテーマにした作文を課された5人の高校生たちが、休日に図書室でそれぞれの自分の胸の内をさらけ出していく……というものだ。この『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』でも、それぞれにアバターになった4人の高校生たちが共にゲームクリアを目指しつつ“本当の自分”を見つめていくことになる。乱暴に言えば、ほとんどが会話劇だった『ブレックファスト・クラブ』の内容を、ゲームの世界で置き換えたのが、『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』なのである。
そして、どちらの作品でも、若者たちが「他者と向き合いながらも自分を知る」過程が描かれている。『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』で本来の姿とは違うゲームのアバターになっているというのも、実は本質的な自分の内面を知る上でもプラスに働いている。オタク少年が屈強な肉体を持つ大男になっても、インスタ映えを気にする女子高生が髭面のおじさんになっても、冴えない地味女子がイケイケの美女になっても、その“中身は変わらない”。しかし、そのアバターの姿を通す(自信が出てきて)ことにより、本来の自分の魅力に気づくことができる。そして、ゲームのおける数々の試練および、他者と結託し共にそれを乗り越える過程があってこそ、彼らは確実に成長していくのである。
これこそ、ゲームの面白さであり魅力そのものではないか。現実の人間がゲーム内のキャラクターに自己を投影し、仲間(現代であれば協力型のオンラインゲームで繋がる友達)と共に目標に向けて挑戦を繰り返し、難題を乗り越えていく。学校の授業やつまらないお説教などよりも、ゲームは前述した鈴木史朗氏の言葉通り、人間としての成長を促し、他者と向き合う喜びをも教えてくれる。そして自身の本当の魅力を知り、他者に何かをしてあげられる存在に(現実でもそのきっかけに)なることができるだろう。
実際に、この『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』の冒頭では、学校の先生からの(正しい言葉だが)つまらないお説教がある。そのお説教を後半ではあるキャラクターがそのまま反芻するのだが、ゲームを通じてこその言葉はつまらないものではなく、真に迫ったものに転換している。ここに大きな感動を覚えるのだ。若者たちの悩みが、他者と交わることで解決したり“一歩先に進む”という普遍的な事実は、1985年の『ブレックファスト・クラブ』の頃から変わっていない。そして、2018年(日本公開年)の『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』はゲームを通じての他者との交わりの1つの理想形を提示してくれる。実に、現代に作られる意義がある映画ではないか!
余談であるが、映画の冒頭ではオタク少年が、ブツブツと喋りながら格闘ゲームをプレイしており、勝利寸前になったもの、友人(というよりこの時はレポートの代筆を強要してきた相手)から届いたスマホのメッセージ見てしまったせいで、「You Lose」と言われてしまうシーンがある。これはつまらないゲームの遊び方をデフォルメして見せたシーンだろう。レポートの代筆という現実から逃避するように“事務的”にゲームをプレイしていて、それでいて現実の出来事にジャマされてしまう。ゲームを遊ぶ時は、心から楽しむために、現実を忘れて(ただの逃避が目的ではなく)没頭したいものである。

さらに余談であるが、『ブレックファスト・クラブ』の引用およびオマージュは最近のハリウッド映画の一種のトレンドのようで、日本の戦隊ものが元となっている2017年のスーパーヒーロー映画『パワーレンジャー』でも、同様にそれぞれ問題を抱えた5人の高校生たちが出会い成長していく過程が描かれていた。さらに、『トランスフォーマー』シリーズのスピンオフである2019年のアクション映画『バンブルビー』でも、『ブレックファスト・クラブ』のとあるシーンが引用されていたりする。それも、『ブレックファスト・クラブ』で描かれた若者の悩みや、他者と交わることでの自己の成長というテーマが決して古臭くない、現代に通じる普遍的な題材であることの証明だろう。
前作『ジュマンジ』にあった“親の不理解と抑圧”の悩みとは

この『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』は、1995年の映画『ジュマンジ』の事実上の続編である(物語のつながりはないがプロットが似ている“精神的続編”に2005年の『ザスーラ』もある)。
『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』はその前作『ジュマンジ』から20年後を舞台に繰り広げられ、ストーリーの“つながり”が示唆されたオープニングから始まり、“あの場所に掘られていたある名前”といった、前作を見ていると気づく小ネタもいくつかある。さらに、“長い時間を取り残された者”の存在がまた大きなドラマと感動を呼ぶことも共通していた。故に、この両者を合わせて観ると、より楽しむことができるだろう。
その『ジュマンジ』もまた子供から大人まで万人が楽しめる娯楽作でありながら、やはり現実的な悩みが描かれていた。それは“親の不理解と抑圧”だ。こちらでは冒頭で、主人公の少年がいじめっ子から逃れるために工場にいる社長の父親のところに行き「一緒に帰ってもいい?」と聞くのだが、当の父親は「お前は逃げてばかりだ。いいか、男なら怖いものには立ち向かって闘うんだ。勇気を持って」と言ってしまう。さらに、父親は息子の悩みをしっかり聞いてやることなく、勝手な中学の転校までもを告げるのだ。
子供は親の愛情と“自分を理解してくれること”を求めているが、親は子供への愛情があってもその理解が及ばないこともある。それどころか、親の一方的な教育方針や勝手な指示に子供が抑圧された状態になってしまうこともある。『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』の問題行動を起こしてしまう高校生たちの悩みと同様に、この『ジュマンジ』での親子関係もまた世界中にある普遍的な問題だ。
また、主人公はただ親の愛情を得られないかわいそうな存在というだけなく、工場の従業員が開発した靴をダメにしてしまったことを謝っていなかったり、友人の少女がいじめられっ子に奪われた自転車を持ってきてくれても感謝も告げていなかったりと、精神的な意味でも子供でもある。26年の時が経ち見た目は大人になっても、彼が父親と同じように他人の子供に自分の価値観を押し付けてしまうというシーンで、ハッと気づかされる人は多いだろう。親だけでなく、子供のほうも、お互いを認め合い、少しだけでも“大人になる”必要があるのだ。
それでいて、『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』での先生からのつまらないお説教がゲームを通じて真に迫っていたものへ転換したように、この『ジュマンジ』でも前述した「お前は逃げてばかりだ。いいか、男なら怖いものには立ち向かって闘うんだ。勇気を持って」という父親の教えが、やがて大きな意味を持つようになる。その時点では響かなかったメッセージが、人生の局面で役立つことにもなりうる。これもまた普遍的な事実であることに気づかされるのだ。
なお、『ジュマンジ』においては、冷酷非道な老齢のハンターであるヴァン・ペルト(『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』でも同じ名前の敵がいる)というキャラクターが登場するのだが、彼を演じている俳優は主人公の父親と同じジョナサン・ハイドだったりもする。自身の父親と、自身を執拗に追いかけ回す存在が同じ顔をしている……これも、“親からの抑圧”を暗に示していたのかもしれない。
公開中のさらなる続編『ジュマンジ/ネクスト・レベル』の面白みは“おじいちゃんのゲームあるある”にあり?

現在、劇場ではさらなる続編『ジュマンジ/ネクスト・レベル』が公開されている。『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』のキャストたちがそのまま続投しており、今回は2人の“おじいちゃん”もゲームに参加してしまうというのが大きな面白みにつながっている。
何しろ、「若者がおじいちゃんにゲームのルールを教えようとするんだけどなかなか理解してくれないし説明が超めんどくさい」という、これまた“ゲームあるある”がギャグになっていたのだ。いや、ゲームでなくても、お年を召した方に「いや!もう!わかってくれよ!」と何かの説明に(尊敬をしつつも)イライラしてしまった経験はないだろうか。そうであれば共感および大笑いしてしまうこと必至だ。
さらに、芸達者な俳優たちがノリノリで“見た目と中身が違う人物”を演じている楽しさもレベルアップしている。ネタバレになってしまうので詳細は秘密にしておくが、「演じている人が楽しいと観客も楽しい」ということを改めて思い知らされる、とだけ言っておこう。今回からの新キャラを演じた、アジア系女優でありラッパーでもあるオークワフィナがまた素晴らしいハジけた演技を披露しており、彼女が先日の第77回ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した『フェアウェル』(2020年4月日本公開予定)も楽しみで仕方がない。
それでいて、『ジュマンジ』シリーズらしい現実の悩みを描いた、ちょっとビターなテイストももちろん健在だ。老年にさしかかかった男たちの友情、祖父と孫の微妙なすれ違いなどは、やはり共感を呼ぶ。個人的には、終盤のある登場人物の選択に納得できなかった……という不満もあるのだが、前作の楽しさをしっかり継承しつつ、それでいて二番煎じにならないような新たなギミックと新鮮さを提示した、優秀な続編と言えるだろう。ぜひ、テレビで『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』を楽しんだ方は、(上映回数は少なくなっているが)劇場に足を運んでほしい。

参考記事:
フリーアナ鈴木史朗69歳 「神業」ゲームテクに感動、絶賛 : J-CASTニュース
全国の人気駅から賃貸物件を探す
札幌駅 大阪駅 京都駅 渋谷駅 釧路駅 帯広駅 津田沼駅 神戸駅 姫路駅 静岡駅
全国の人気沿線から賃貸物件を探す
ゆりかもめ 京急大師線 仙石線 大阪環状線 東武野田線 阪急今津線 相模線 西武多摩川線 東海道本線 内房線