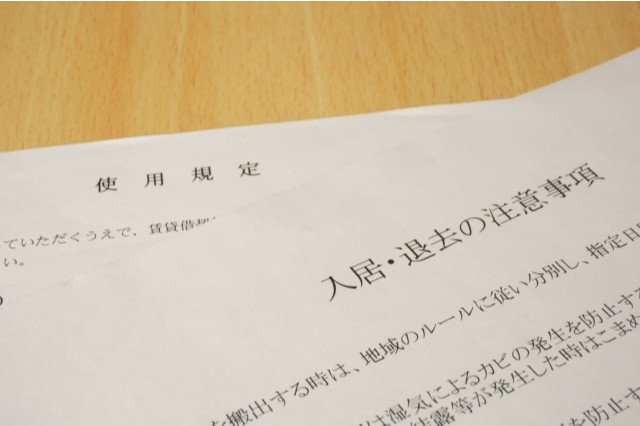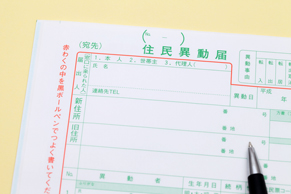賃貸契約で違約金が発生するケースをプロが解説!途中解約やすぐ退去する場合は?

賃貸物件では、更新までの期間が2年に設定されていることが一般的だ。また、居住用の賃貸借契約の場合、借主(入居者)からであれば契約期間中も途中で解約できるようになっている。
ただし、中途解約の仕方によっては金銭の支払いが発生することから、解約方法には注意したい。
入居時に締結する賃貸借契約書の中では違約金という言葉が明記されていないことが多いため、契約書を読み込んでどういう場合に支払いが発生するかを理解する必要がある。
この記事では、契約期間満了前の退去を検討している人向けに「賃貸の違約金」について解説していこう。
このページの目次
賃貸借契約書を中途解約する場合、違約金は必須?
結論から言うと、入居後に借主側から賃貸借契約を中途解約する場合、契約書に記載されている手続きを行うことで、違約金を発生させずに解約することが可能だ。
多くの賃貸借契約(普通借家契約)は、更新までの期間が2年と設定されている場合がほとんど。その期間内に中途解約する際は、まずは賃貸借契約書の「解約条項」を確認しておきたい。賃貸借契約では借主は「乙」と表現されていることが多い。「乙からの解約」という部分が借主からの解約について条件を定めた条項ということになる。
借主からの中途解約方法は、「予告解約」と「即時解約」の2つの方法が記されていることが一般的だ。予告解約とは、定められた期限までに退去を予告して解約する方法である。
実際の契約書の文面を見てみよう
賃貸借契約書に記載されている解約条項は、一般的に下記のように記されていることが多い。
1.乙(借主)は、甲(貸主)に対して30日前(もしくは1か月前)までに解約の申入れを行うことにより本契約を解約することができる。
2.前項の規定に関わらず、乙(借主)は解約申入れの日から30日分(もしくは1ヵ月分)の賃料相当額を甲(貸主)に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
違約金が発生するケース/しないケース
「予告解約」では、前述の通り違約金は発生しないことが一般的だ。上記の契約書の場合、第一項(1.)が予告解約に相当する(以下抜粋)。
1.乙(借主)は、甲(貸主)に対して30日前(もしくは1か月前)までに解約の申入れを行うことにより本契約を解約することができる。
アパートなどの居住用の賃貸物件では、解約の申し入れをおこなう「予告期限」は30日前もしくは1ヵ月前と定められている物件が多い。一般的には、30日前までに予告すれば違約金を発生させずに解約ができるということだ。
もう一つの「即時解約」とは、予告期限までに退去を予告せずに解約する方法のことである。たとえば、予告期限が1ヶ月の物件を1週間前に解約したい場合などを指す。
即時解約では、違約金に相当する金額の支払いが発生することが一般的だ。上記の解約条項では、第二項(2.)が即時解約に相当する(以下抜粋)。
2.前項の規定に関わらず、乙(借主)は解約申入れの日から30日分(もしくは1ヵ月分)の賃料相当額を甲(貸主)に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
アパートなどの居住用の賃貸物件では、一般的に30日分もしくは1ヵ月分の賃料相当額を支払うことで、即時に解約できることが多い。
解約条項とは
解約条項とは、解約によって貸主が被る経済的損失を和らげる意図で設定されている。
たとえば、入居予定だった借主から急に解約されてしまった場合、貸主は次の入居者が決まるまで一定期間は賃料が入ってこないことになる。そのため、解約条項には予告解約や即時解約の制度が設けられている。
予告解約の予告期限は1ヵ月前、即時解約の違約金は家賃の1ヵ月分としている契約書が多いが、場合によっては2ヵ月と定めている契約書も存在する。
中途解約をする場合には、必ず賃貸借契約書の解約条項を見直すことが適切だ。
入居前でも「中途解約」になる?
入居前であっても、賃貸借契約締結後のキャンセルは「中途解約」扱い
賃貸借契約成立後のキャンセルは、通常の中途解約扱いと同様となることも知っておきたい。賃貸借契約にはクーリングオフ制度もないため、賃貸借契約は内容を十分に理解したうえで締結しよう。
入居後すぐの解約には「短期解約違約金」が設けられているケースも
「短期解約違約金(短期契約違約金)」とは、短期間に借主が契約を解約した場合に支払わなければならない違約金のことである。
短期解約違約金の定めは全ての賃貸借契約に存在するわけではないが、フリーレント物件やゼロゼロ物件などでは定められているケースが存在する。「フリーレント物件」とは、入居後、数ヵ月間の賃料が免除される物件のことである。一方の「ゼロゼロ物件」とは、入居時の敷金と礼金がゼロ円の物件のことを指す。
短期解約違約金の条項がある物件では、短期間のうちに解約すると家賃の1~2ヵ月分程度の違約金が発生することが一般的だ。「短期」の定義は契約書にもよるが、契約から1~2年未満を短期としているケースが多い。
短期解約違約金の定めがある物件では、賃貸借契約を締結する前の重要事項説明において不動産会社から契約内容の説明を受けている。
借主は重要事項説明を受けて納得したうえで契約しているという前提であるため、短期解約に該当した場合には契約書に従って違約金を支払わなければならない。
フリーレント物件やゼロゼロ物件などの一般の物件よりも(借主にとって)有利な条件の物件を借りている場合には、賃貸借契約書で短期解約違約金の定めの有無を再確認することが望ましいといえる。
賃貸借契約契約前の申し込み段階では違約金は発生しない
ちなみに、賃貸借契約を締結する前の申込段階では、キャンセルしても違約金は発生しない。
仮に契約前に「申込金」が発生する場合でも、同様に違約金は発生しない。また、申込金は契約が不成立になったときも返還されるべき金銭であるため、キャンセルした場合でも違約金として没収されることはない。
賃貸借契約の種類:定期借家契約と普通借家契約
賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」との2種類が存在する。
普通借家契約とは更新の制度がある契約のことを指し、定期借家契約とは更新の概念のない契約のことを指す。
一般的な賃貸住宅であれば、普通借家契約となっていることが多い。
一方で、シェアハウスや、貸主が一時的に貸している物件(海外への転勤期間中)などでは、定期借家契約となっていることが多い。
定期借家契約は、原則として中途解約できないことになっている。
ただし、「やむを得ない事情があれば」借主から契約解除できるルールがある。たとえば、転勤や療養、親族の介護などは認められる可能性が高い(借地借家法第三十八条七項)。
また、床面積が200平米未満の居住用物件の定期借家契約の場合、「乙(借主)からの解約」条項は前述の条文と同じであるケースが多い。
解約の方法としては、普通借家契約と同じく予告解約と即時解約の2つの方法が定められており、予告解約の予告期限は1ヵ月前、即時解約の場合は家賃の1ヵ月分の支払いを必要としている契約書が一般的だ。
早期の引越しで補助金がもらえるサービスも
「CHINTAI安心パック」は、引越し前に加入しておけば、引越し後、早期で住み替えをすることになっても補助金を受け取ることができるサービス。契約開始日から3ヵ月間、どんな理由の住み替えでも対象だ。補助金額は最大一律30万円。住み替えの理由にかかわらず補償金額が一律なのも嬉しいポイントだろう。新生活の際のお守りのようなこのサービスに加入するためには、賃貸借契約始期日までの申込が必要だ。詳しくはCHINTAI安心パック商品ページ・利用規約を確認しよう。

違約金が発生するか確認する方法
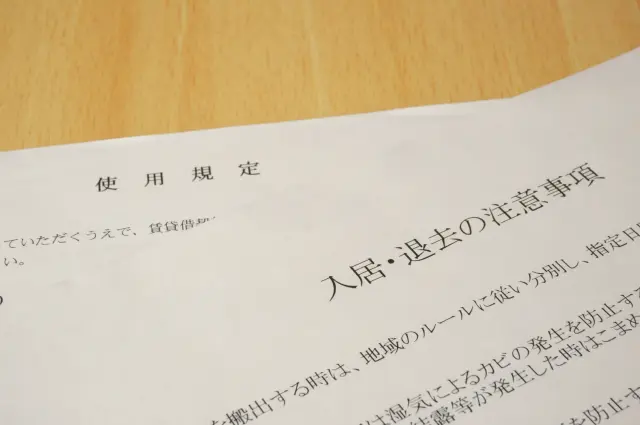
入居後に、中途解約による違約金の有無を確認するには、賃貸借契約書を再確認することが最も確実な方法である。
冒頭にも記載したが、賃貸借契約書には違約金という言葉は登場してこないのが通常だ。たとえば、即時解約では「解約申入れの日から30日分の賃料相当額を支払う」などの表現となっており、違約金という言葉は一切登場しない。
そのため、違約金という言葉はなくても、条項をしっかりと読み込んで金銭の支払いが発生することを理解することが必要だ。
また、賃貸借契約書の中では、本文だけでなく末尾に特約条項を定めているケースもある。特約条項では一般的な賃貸借契約書には存在しない違約金の定めがあることもあるため、特約条項についてもしっかりと確認しておきたい。
賃貸借契約書の他に、「重要事項説明書」も交付されるケースも多いと思われるが、重要事項説明書に記載がなくても、賃貸借契約書に記載があれば賃貸借契約書に拘束されるため、必ず賃貸借契約書を確認しよう。
賃貸借契約書の読み方についてもっと知りたい人はこちら!
契約締結後に違約金の交渉はできる?
契約締結後の違約金の交渉は、基本的には難しい。
借主は契約書の内容を理解したうえで契約を締結している前提になっているからだ。初めて賃貸借契約を締結する人にとっては契約内容を理解することは難しいかもしれないが、理解不足のままでの契約締結を避けるため、不動産会社には「重要事項説明」という対応が法律で義務付けられている。
解約条項や違約金については、契約前にしっかり確認を
「重要事項説明」は賃貸借契約の締結前に行われるものであり、重要事項説明を受けたうえで納得がいかなければ契約しなくても良いことになっている。
重要事項説明という制度は借主を守ることが目的であるため、きちんと重要事項説明を受けたうえで契約している限り、借主は契約内容を理解したうえで契約していることになる。
そのため、後から「こんなことは聞いていなかった」と主張することは難しく、金額の交渉は実質的にできないことが多い。
退去理由が自分のせいじゃなくても、違約金はかかる?
退去理由が不可抗力による場合には、違約金は発生しないことが通常である。
たとえば、地震や火災などによって建物が使用できなくなり、居住の目的を果たせなくなった場合(法的には「建物一部が滅失その他の事由により」と定義されている)には、借主は契約を解除することができる、というようなもの。貸主には借主に対して目的物(=建物・部屋)を使用させる義務があることから、貸主がその義務を果たせなくなった場合には契約は解除され、借主には違約金も発生しない。
契約違反やルール違反があった場合、別の支払いが発生する場合も
違約金とは趣旨が若干異なるが、退去時には借主に「原状回復費用」が発生する場合がある。
原状回復とは「借主の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意(わざと)・過失(うっかり)、善管注意義務(※)違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」を指す。
※善管注意義務とは:社会通念に基づく注意を払い、借りている部屋を使用すること。また、通常の清掃や適切な管理を行い、不注意による損傷を防ぐこと
借主の故意や過失などによる損傷が対象であるため、契約に違反したことで発生した損傷などが借主の費用負担による復旧の対象となる。
たとえば、禁煙物件にもかかわらず喫煙したことで生じたヤニ跡や、ペット不可物件にもかかわらずペットを飼ったことで生じた傷などが原状回復の対象に相当する。
借主が負担すべき原状回復費用が発生した場合には、退去時に貸主から修繕費用が徴収されることになる。禁止事項に関しても賃貸借契約書で改めて確認しておきたい。
こういった費用面以外でも、契約解除事由に該当する重大な契約違反が発生した場合には、契約期間内であっても貸主から契約が解除されてしまい、退去を求められる可能性があることは覚えておこう。
たとえば、入居者が貸主の許可を得ずに部屋を友人に貸したり、民泊を運営する行為は「無断転貸(又貸し)」といい、民法第612条と賃貸借契約で禁止されている。即解約となってしまう事例自体は限られるものの、解約条項に限らず契約書の記載事項はきちんと理解し、知らず知らずであっても違反に該当するようなことは避けておきたい。
賃貸契約の中途解約で違約金が発生するかは、契約書を確認しよう
賃貸借契約を入居者から中途解約する際、あらかじめ定められている「解約条項」などにのっとり、予告解約を行った場合には違約金は発生しない。一方で、退去を予告しなかったり、定められた予告期限を過ぎてから解約する場合には金銭の支払いが発生することが通常である。
即時解約の違約金の相場は賃料の1ヵ月分であるが、物件によっては異なることもあるため、賃貸借契約書を確認することが望ましい。その際は本文にある「解約条項」や末尾の「特約条項」部分をチェックしよう。
賃貸借契約を締結した後や入居後に中途解約を検討し始めたときは、まずは契約した不動産会社への早めの相談をおすすめする。