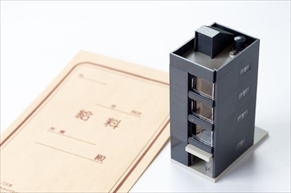【衣類害虫・ダニ】布団やタンスなど収納の虫対策!場所別のおすすめ防虫剤の選び方
一人暮らしで気になる防虫対策。衣類や布団におすすめの防虫剤とは?

一人暮らしで気になるのは衣類や布団などの防虫対策。皆さんはどのような防虫剤をお使いだろうか。防虫剤は製品によって薬剤が異なり、使える場所も異なってくる。防虫剤の使い方を間違うと効果が半減してしまうこともある。
そこで今回は、衣類や布団の防虫対策や、場所別の防虫剤の選び方などを紹介しよう。衣替えして、お気に入りのセーターに穴が空いていたなんてことがないようにぜひ参考にしてほしい。
衣類用防虫剤の種類と特徴
衣類の害虫は主に4種類。
・ヒメカツオブシムシ(幼虫7〜10mm)
・ヒメマルカツオブシムシ(幼虫4〜5mm)
・イガ(幼虫5〜6mm)
・コイガ(幼虫6〜7mm)
これら衣類害虫は窓などから侵入して衣類に卵を産み付ける。そして孵化した幼虫が繊維を食べることにより、衣類に穴が空いてしまうのだ。
衣類害虫の幼虫は、湿気のあるジメジメした場所やホコリが大好物なので、湿気のこもりやすいクローゼットなどは居心地が良いのだ。しっかり対策をしないと、被害が広がってしまう。そうならないためにも、防虫剤の使い方をしっかり理解して防虫対策をしよう。
衣類害虫に効果のある防虫剤は大きく4つある。使い方によっては、衣類をダメにしてしまったり、健康被害が出たりする恐れもある。それぞれの特徴を紹介していくので、しっかり使い分けてほしい。
防虫剤の種類①:ピレスロイド系
ピレスロイド系の防虫剤の特徴は以下の4つ。
・無臭
・効果が高い
・他の種類と併用しても大丈夫
・長持ちする
防虫菊に含まれる有効成分の総称で、いろいろな殺虫剤として利用されている。蚊取り線香などもピレスロイド系が主流だ。衣類に臭いが付かないので、毎日使用する服などに適している。また、虫には効果は高いが、人への害が低く安全性の高い防虫剤と言える。
ただし、真鍮や銅などの金属のボタンが付いた服には使用できない。殺虫成分が化学反応を起こしてしまい、金属の色が変わってしまう恐れがあるので注意が必要だ。
防虫剤の種類②:パラジクロルベンゼン
パラジクロルベンゼン防虫剤の特徴は以下の4つ。
・臭いが強い
・即効性があるが、消耗が早い
・プラスチックや塩ビ、樹脂を変性させてしまったり、溶けてしまったりする恐れがある
・高濃度では人への健康被害の恐れがある
4種類の防虫剤の中では最も臭いが強い防虫剤。害虫に即効性があり効き目が高い一方で、効果が長続きしないというデメリットもある。また、融点が低く夏場だと溶けてしまう可能性がある。さらに、プラスチックや塩ビ、樹脂などには使用できないので注意が必要だ。
防虫剤の種類③:ナフタリン
ナフタリン防虫剤の特徴は以下の4つ。
・臭いが強い
・即効性はないが効果が長続きする
・直接肌に触れると炎症を起こす
・金属などへの影響がない
防虫効果はそれほど強くないが、ゆっくりと効きはじめ、効果が持続するのが特徴。金属や金箔などの素材へ影響が少ないことから、五月人形やお雛様などを保管する際の防虫剤として使用されることも多い。しかし、直接肌に触れると炎症を起こしたり、誤飲による健康被害の恐れもあったりするので注意が必要だ。
防虫剤の種類④:しょうのう
しょうのう防虫剤の特徴は以下の4つ。
・天然植物由来
・ハッカのような自然な香り
・誤飲すると健康被害の恐れがある
・プラスチックや塩ビに反応する恐れがある
衣類の防虫剤としては古くから使用されてきたのが、しょうのう。クスノキの葉や枝を蒸留して抽出したものが原料で、天然植物由来の防虫剤だ。しかし、天然植物由来とはいえ、しょうのう自体は有毒。万が一誤飲してしまった場合は、すぐに病院に行く必要がある。
防虫剤の注意点
ピレスロイド系の防虫剤以外は、2種類以上を併用して使用してはいけない。異なる成分の防虫剤を併用することで、化学反応が起きてガスが発生する恐れがある。衣類に油性のシミなどが付いてしまう恐れがあるので注意が必要だ。
有効期限が切れた防虫剤を取り出し忘れて、別の防虫剤を入れてしまわないよう、タンスや収納ケースを定期的にチェックしよう。
衣類におすすめの防虫剤の選び方とは?
4種類の防虫剤は、どのように使い分けたら良いのだろうか。保管スペースや利用シーン別に紹介していこう。
毎日着る服など
防虫剤と言えば、衣替えでオフシーズンの衣類をしまう時に使用するイメージがあるが、オンシーズンで使用している服にも防虫対策が必要。その際は、毎日着るので臭いが付かない、ピレスロイド系の防虫剤がおすすめ。
また、ピレスロイド系の防虫剤は、大きさやサイズなどの種類が豊富。引き出し・衣装ケース用、クローゼットに吊り下げるタイプ、カバータイプ、シートタイプなどさまざま。それぞれ収納空間によって防虫剤の適正量が違うので、商品説明をチェックして使用すると良い。

¥902/エステー
虫の付きやすい服
虫が最も付きやすいのは、ウールや絹製品。そのため、ウールや絹製品などには、即効性のあるパラジクロルベンゼン製剤の防虫剤が最適。消耗が早いので、3ヶ月ほどを目安に補充すると良い。

¥645/エステー
和服や毛皮など
頻繁に着ることがない和服や毛皮などを保存する場合、効果が長持ちするナフタリンや、穏やかな効き目で衣類にやさしい、しょうのうがおすすめだ。

¥1,980/白元
防虫剤を入れているのに効果がない場合
防虫剤を入れているのに、虫にくわれてしまったということも。その場合には考えられることは3つ。
・密閉されていなかった
・有効期限が切れていた。
・防虫成分が行き渡っていなかった
防虫剤は密閉された空間で効果が発揮する。クローゼットの扉がないなど、オープンな空間の場合は、カバータイプなどで密閉することをおすすめする。また、有効期限が切れた場合は防虫剤の効果がなくなってしまう。事前に商品説明をしっかり読んで交換時期をチェックしたり、おとりかえサインがあったりする商品を選ぼう。
そして、防虫成分が行き渡っていないと効果が発揮しない。防虫成分は空気より重いので、引き出しや衣装ケースの場合、防虫剤を下に入れると上の衣類まで防虫成分が行き渡らない可能性がある。また、衣類を詰め込みすぎた場合も効果が半減するので注意が必要だ。
布団用防虫剤の種類と特徴

衣類の防虫対策と並んで気になるのが、布団の防虫対策。布団の防虫対策は主にダニだが、布団には1年を通して生息していると言われている。ダニの死骸やフンなどは、体の不調を起こしたり、アレルギーの原因にもなったりするのだ。
布団に多く生息しているのが「ヒョウダニ」というダニ。肉眼で確認するのが難しいほど小さく気づかないことがほとんど。ヒョウダニは、髪の毛やフケ、アカや食べカスなどを好むため、布団はヒョウダニにとって、とても居心地が良いのだ。
そして繁殖性が高く、1組のつがいが2ヶ月後には約3,000匹、4ヶ月後には約450万匹にも増えると言われている。ダニ対策をしないと、すぐにダニだらけとなってしまうのだ。
布団用防虫剤の種類①:敷くタイプのシート
布団の下に敷くことでダニを寄せ付けない効果がある。殺虫剤成分を使用していないものが多く、布団など肌が接触するような場所に最適。

¥717/UYEKI
布団用防虫剤の種類②:置き型シート
ダニは生きたまま捕獲して捨てることが重要。なぜなら、ダニは死骸もアレルギーなどの原因になるからだ。そのため生きたまま捕獲して閉じ込める置き型シートがおすすめ。

¥1,680/日革研究所
布団用防虫剤の種類③:防虫圧縮袋
布団を収納する際に気になるダニ対策には、防虫圧縮袋がおすすめ。布団を充分に乾燥させてから収納することで、ダニの繁殖を防いでくれるのがポイント。

¥990/バルサン
布団におすすめの防虫剤の選び方とは?
布団全体に防ダニ効果を発揮したい場合は、布団やシーツの下に敷くことができるシートタイプや、ダニを引き寄せて捕獲するタイプもおすすめだ。毎日のケアには、薬剤を散布するスプレーも効果的。部屋全体的にダニを退治したい場合は、くん煙や霧などで空間処理ができるタイプもおすすめだ。

¥795/KINCHO
![【第2類医薬品】アースレッドW [ゴキブリ・ダニ・ノミ用 6-8畳用 10g]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Gd+zMrcXL.jpg)
¥601/アース製薬
用途に合わせて正しく防虫剤を選ぼう!
今回は、衣類や布団の防虫対策や、場所別による防虫剤の選び方などを紹介した。防虫剤にはさまざまな種類がある。使い方を間違えると効果が半減したり、健康被害を及ぼしたりする恐れもある。用途に合わせて正しく防虫剤を選ぼう!
※この記事は2021年3月10日現在の情報をもとに制作しております
東京の人気駅から賃貸物件を探す
池袋駅 中野駅 北千住駅 赤羽駅 笹塚駅 三鷹駅 清澄白河駅 八王子駅 新宿駅 祐天寺駅
東京の人気市区町村から賃貸物件を探す
港区 文京区 江戸川区 練馬区 杉並区 中野区 板橋区 渋谷区 目黒区 台東区