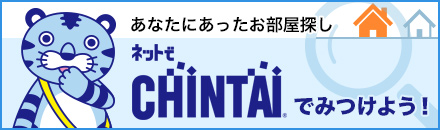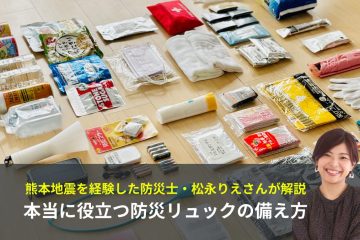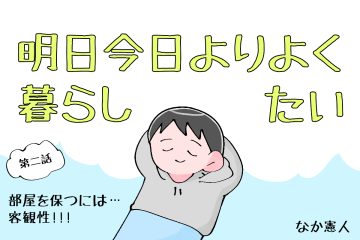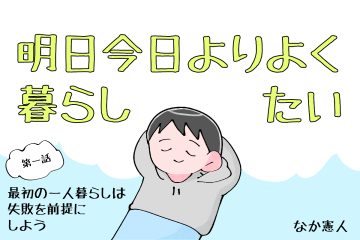ユニークなDIY可賃貸物件の「やわらかな内装システム」から生まれる個性的な2部屋を訪問
DIYビギナーでも安心な合板貼りワンルームで気楽に個性を出せる!
壁と床に合板を貼りめぐらし、釘やビスの打ち付けからペンキでの加工もOKというスタイリッシュで自由な賃貸住宅「キタノアパート」。DIYに挑戦したい人はもちろん、他にはないおしゃれなキッチンに惹かれて契約をする人も多いのだとか。
そんなキタノアパートに住む沼田さんと南林さんに、それぞれ個性的なお部屋づくりのコツやDIY住宅の楽しみ方をお聞きした。

シンプルにまとまっているがアイディアが詰まったお部屋!
物件情報
所在地:東京都八王子市
間取り:ワンルーム(6畳)
家賃:42,000円(共益費3,000円含む)
築年数:27年
このページの目次
ユニークなDIY歓迎賃貸「キタノアパート」ってどんなところ?
学生向けのワンルームが多く立ち並ぶ八王子近辺は、大学の都心回帰が進み、賃貸物件のデフレ化が進む地域。そんななか、キタノアパートではユニークなDIY賃貸を採用し、多くの「自由な」人たちから人気を集めている。
なにがユニークかというと…壁と床にはホームセンターで売られている合板がびっしりと張り巡らされ、この部分であればどこでもDIYが可能という点。この合板は入居者の持ち物になるので、穴を開けても釘を打っても、ペンキを塗るのも自由。合板は入居時にラワンやシナ、MDFなど5種類の合板から好きなものを選べ、入居途中で別の合板に変えたければ、ホームセンターなどで好みの規格合板を買ってきて替えることも可能だ。

一番人気のラワン合板の部屋。入居者入れ替え時も合板を替えればいいので大家さんの負担も軽減される
ちなみにキタノアパートには、自由に使える共有工具や余った材料が集められた共有スペースもある。大型の家具などが作りたければ、駐車場の片隅を使ってもいい。カーシェア用の車もあるので、ホームセンターへの買い出しも気軽だという。こんな好条件が揃った物件も珍しいだろう。

建物内にある作業スペースには共有工具と余った材料も置いてある
なかでも人気なのは、ステンレスのキッチンとそこに付随した木の作業台。いわゆるワンルームの簡易キッチンにはない、おしゃれでスッキリしたデザインが特徴で、DIYよりもこのキッチンが気に入って契約する人もいるほどだという。

ステンレスのキッチンは、普通のユニットキッチンにはない魅力がある
これらの特徴はキタノアパート全てに共通しているが、さすがDIY歓迎の物件だけあって、それぞれの部屋が驚くほど個性的で楽しい。2人の入居者の部屋を見せてもらった。
CASE01.「木や緑を感じられる自然体の部屋」― 沼田さんの場合
プロフィール
名前:沼田さん
職業:デザイナー
年齢:20代

観葉植物やドライフラワーに囲まれ、ほっこりした雰囲気の沼田さんの部屋
最初にお邪魔したのは、キタノアパート最初の入居者・沼田さんのお部屋。
キタノアパートの企画運営をしているスタッフと知り合いだったこともあり、プロモーター兼入居者の取りまとめ役として白羽の矢が当たった。
学生時代は建築を学び、高性能なタイニーハウス(小屋・身軽な住まい)をキット化してセルフビルドする「断熱タイニーハウスプロジェクト」のリーダーでもある沼田さん。さぞかしDIYの部屋づくりに傾倒しているのかと思いきや…「根っからの面倒くさがり屋で、そもそもDIY大好きというタイプではないんです」と申し訳なさそうに語った。
それでも手作りの棚やオープンシェルフ、パーテーションと、自力で作った家具たちに囲まれた部屋は居心地がよさそうだ。部屋づくりのテーマは特に設定していないが、「木や緑が大好きなので、イメージは自然な雰囲気。全体的に濃い色味に揃えたくて、契約して最初にしたのは床を濃いブラウンのワックスを塗ったこと」だったいう。
合板の床は傷もつきやすいので、ワックス塗布は大正解だった。濃いブラウンに仕上げたこともあり、部屋全体が落ち着いた雰囲気に変身した。

日当たりのよい窓際でたくましく育つゴムの木。床はBRIWAXのブラウンでマットに仕上げた
棚もパーテーションも思い立ったらすぐ作り・動かせるメリット
「壁も床も打ち付けOKなのですが、私は模様替えや配置換えをしやすいように、あえて家具を固定していません。飽きたらすぐ場所を移動したり、テーブルが欲しいと思えば天板を買ってきて作ったり、思い立ったらすぐ行動に移せるところがキタノアパートの楽しいところ」と話す。
使い勝手のよさそうなオープンシェルフも、もちろん手作り。「ホームセンターで材料を切ってもらい、自分でヤスリをかけて色を塗り、ビスで留めただけ」と言うが、調味料からコーヒーセット、化粧品、アクセサリーまで、生活に必要なものを集約できるお役立ちな一角だ。
「最初は一段だけを作って、少しずつ増やしました。以前は横に長くつなげて使っていたんですが、パーテーションを取り付けたので、今は距離を縮めて重ねています。とにかく家具も棚も収納も変幻自在に変えられるので、6畳の部屋でも全然飽きません」と沼田さん。

手作りの棚は高さも長さも好みに合わせられて便利
角材と合板で作ったパーテーションで、部屋の表情に変化もつけた。布団スペースと生活スペースがなんとなく分かれて、ワンルームらしからぬ雰囲気に。またパーテーションにはフックや棚で様々なものも引っ掛けられて、ディスプレイかつ収納の役割も果たしている。
「このパーテーションも角材を2本立てて合板を両面に貼っただけなので、全部で2,000円くらいでできました。とにかく“お好きにどうぞ”と言われている部屋なので、創作意欲は掻き立てられますね。この私でもこれだけ楽しんでいるので、好きな人だったらお部屋の作り込みは無限大で、本当に楽しいと思います」と沼田さん。
釘やビスを打てるというだけで、部屋の自由度は驚くほど上がる。壁に照明器具を取り付けてもよし、季節ごとに壁を塗り替えるもよし、クリエイティブな人たちの感性は刺激されっぱなしだろう。

1日で簡単にできたパーテーションで部屋の雰囲気もガラリと変わった
次に挑戦したいDIYを聞くと、「壁を濃いグレーに塗ってみたいですね。もし失敗しても合板を裏返しにすればいいだけなので冒険ができます(笑)。そのあたりの自由さ・ハードルの低さは他の賃貸にはない特徴ですよね」と沼田さん。
CASE02.「サボテン&多肉植物と暮らす画家のアトリエ」― 南林さんの場合
プロフィール
名前:南林さん
職業:画家
年齢:20代

壁一面に広がる描きかけの油彩。汚れを気にせず制作に集中できるのは大きなメリットだという
このキタノアパートで、日々絵画の制作に没頭するアーティストもいる。南林さんは秋田県の美大を卒業し、「コンペなどの直接搬入に便利」という理由で上京した。
「最初は生活のための安い部屋とアトリエ用の部屋を2つ借りようと思っていましたが、なかなかぴったりの物件がなくて…そんな時にキタノアパートが見つかり即決しました」と話す。
DIYも歓迎なら、ペンキや絵具で汚すのもOKというキタノアパートの懐の大きさはありがたいという。
「シナ合板の壁を選んだのは、ペンキで塗った時にヤニが出ず色に影響しないから。入居1ヶ月前から家賃を支払い、まずは壁と床をペンキで塗りました。絵具の白が見えづらくなるので、オリジナルで混色した少しグレーがかった白にしました」とアーティストとしてのこだわりを覗かせた。

絵具や工具類はワゴンにまとめている。これ自体がすでにモダンアートのよう
いた絵を少しでも引いて客観的に見るために、作りつけの家具は置かず、スペースを確保しているという南林さん。DIY歓迎の部屋にあって、比較的入居当時のまま住んでいる方だろう。
唯一作ったのが、ガチャレールで高さを自在に変えられる机と棚だ。
「本の重みで棚がたわんできたので、真ん中に柱を入れようかと考え中です。次にやりたいのは、オーディオと足元に重なった画集を整理して入れられる棚づくり。でもなかなか時間がなくて…」と悩ましい。

唯一のワークスペースである手作りのデスク。棚を増やしたり高さを変えるのも自由にできるガチャレールは便利
一緒に暮らすのは、「意思を表明するサボテン」
そんな南林さんを癒してくれるのが、窓際のサボテンと多肉植物たち。和菓子のように美しい日本原産の菊章玉や、インド産の柱サボテンが陽の光を浴びてすくすくと育っている。
「水が足りない時、日当たりがほしい時など、それぞれ違う意思表示の仕方で訴えてくるから面白いですね。根の形に合った鉢や、見た目に似合う鉢を選ぶのが一番楽しい瞬間です」と、まるで我が子に向けるような温かい目で見つめる。

植物が大好きという南林さんに愛されて育つサボテンたち
「キタノアパートに住む人たちは、適度な距離感と親しさがあって付き合いやすいんです。誰かが風邪をひいて寝込んだら、ポカリと食べ物をそっとドアノブに掛けて立ち去る…みたいな温かいけどズケズケ入り込まない関係が保てるので、安心かつ居心地がいい」(南林さん)
来年の個展に向けて、今は打ち合わせと制作に忙しいという南林さん。将来的には友人と一軒家を借りて、シェアアトリエ兼住居にしたいと夢を語った。

個展が決まってからは、月1回のペースで打ち合わせのために都心にも足を運ぶという
自分好みの部屋を作って、自由な暮らしをデザインしよう!
DIYができるのは合板部分のみと自由度が高過ぎず、DIYをしてもしなくてもいいというフレキシブルなワンルーム賃貸のキタノアパート。
ゴリゴリに手作りしたい派から、ちょっぴりユニークな部屋に住みたい人まで、幅広い入居者に開かれた懐の深い部屋が気になる人は、今すぐチェックしてみよう!
文=元井朋子
写真=編集部