賃貸物件の連帯保証人とは?リスクや条件、立てられない場合の対処法を解説
賃貸物件の連帯保証人ってなに?みんな誰にお願いしてる?

賃貸物件を契約するときに立てなければいけないのが連帯保証人。
日本特有ともいわれるこの制度だが、みんなは誰にお願いしているのだろうか?
このページの目次
賃貸物件の連帯保証人とは
連帯保証人とは、借主が家賃を支払わなかったときや設備を壊してしまい弁償できないなど、何らかの問題を起こした場合、本人に代わって支払いをする人のことを指す。連帯保証人という制度は民法で定められており、契約した時点で法的な効力が発生する。
連帯保証人は、借主と同等の責任を負うことになるため、非常に重い役目だといえるだろう。
賃貸物件の連帯保証人はなぜ必要なのか
家を貸す側の立場で考えると連帯保証人の必要性はわかりやすい。貸す側からすれば家賃を滞納されるリスクや、物件に傷をつけられるおそれもある。連帯保証人がいれば、借主がトラブルを起こした際、家賃や修繕費用を回収できるため、連帯保証人を必須にしている物件が多いのだ。
賃貸物件の「連帯保証人」と「保証人」の違い
保証人と連帯保証人では、負う責任の重さが違う。
保証人は、借主がどうしても支払いができない場合だけ支払う義務を負う。このため、大家さんから支払いを請求された場合、まずは借主本人に請求を行うよう求めることができる。
一方、連帯保証人は借主と同じ義務を負う。このため、仮に借主に支払い能力があったとしても、連帯保証人は大家さんから支払いを請求されたら拒む権利がない。
賃貸物件の連帯保証人が負う3つのリスク
賃貸物件の連帯保証人が抱える責任は重大だ。以下のようなトラブルが発生した際は、すべての責任を背負わなければならない。
連帯保証人が負う3つのリスクを具体的に見ていこう。
賃貸物件の連帯保証人が負うリスク①:借主が家賃を滞納した場合、請求される可能性がある
借主が家賃を滞納し、この費用の請求に応じなかった場合、滞納している家賃の全額が連帯保証人に請求される可能性がある。仮に家賃が10万円で、滞納期間が6ヶ月だとすれば、連帯保証人には60万円を支払う義務が生じてしまう。
なお、2020年4月に行われた民法改正によって、連帯保証人が保証しなければならない金額の限度(極度額)が賃貸借契約書に明記されることとなった。これは、連帯保証人が想定外の債務を負うことを防ぐために、新たに設けられたルールだ。
賃貸物件の連帯保証人が負うリスク②:物件の原状回復費や損害賠償費用を請求される可能性がある
原状回復費とは、経年劣化等の正当な理由を除き、借主の故意・過失などによって発生した傷や・破損を修復するための費用だ。原状回復費は借主に請求されるが、請求のタイミングが退去後ということもあり、借主が支払いをすっぽかしてしまいやすい。こういった場合の責任を取るのも連帯保証人の役目である。
賃貸物件の連帯保証人が負うリスク③:連帯保証人は途中で辞めることができない
賃貸借契約は、貸主と借主の間で取り決められる契約だ。連帯保証人は契約の当事者ではないため、自分の意思だけでその立場を辞めたり、契約から外れることはできない。賃貸借契約を終了させるには、契約当事者間の合意が必要であり、連帯保証人の意思だけでは変更できないのだ。
また、連帯保証人が死亡した場合、その地位は相続人に引き継がれる。相続放棄によって連帯保証人から外れることは可能だが、この場合は預貯金や不動産といった他の財産も一緒に放棄しなければならない。連帯保証人になるということは、自分だけでなく、子どもや親族の人生にも影響を及ぼす可能性があることを覚えておこう。
賃貸物件の連帯保証人になれるのはどんな人?関係性と条件
連帯保証人について理解することができたが、連帯保証人になる人はどのような条件を満たしていなければならないのだろうか。
賃貸物件の連帯保証人になれる人
連帯保証人は借主に代わって支払いをすることが求められるため、相応の支払い能力が必要だ。単に収入があれば良いというわけではなく、借主が借りている物件の家賃に見合う支払い能力が求められる。定期的に安定した金額の収入がある人であれば連帯保証人として認めてもらえる可能性が高い。
連帯保証人と借主の関係性については、法律上特に取り決めはない。親や兄弟、子どもといった親族にお願いするケースが多いが、血縁関係のない友人・知人であっても構わない。
連帯保証人になるための条件・審査内容
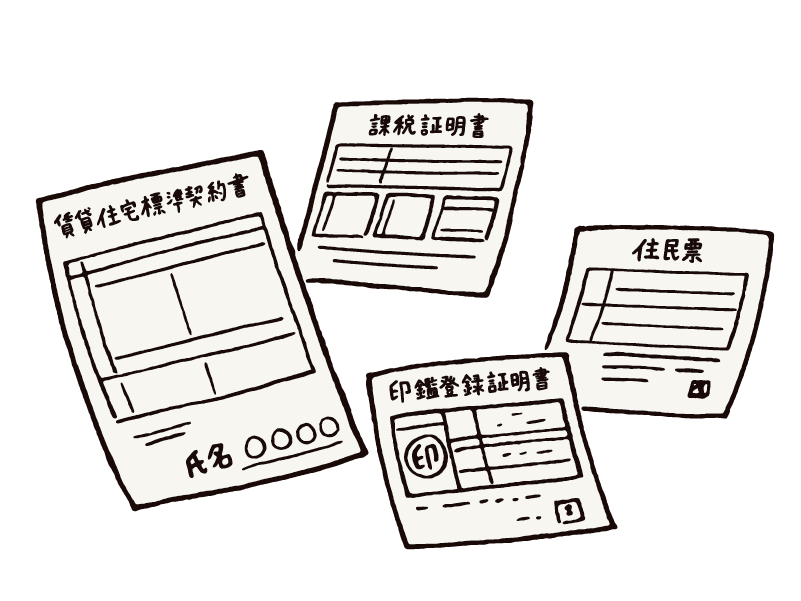
前述のとおり、賃貸の連帯保証人になるためには、支払い能力があるかが重要な条件となる。このため、連帯保証人の年齢や勤務先、年収などを書類に記入してもらう必要があるほか、それらを証明する書類も提出しなければならない。場合によっては、月収や貯蓄額まで確認されることもある。
支払い能力について問題ないと判断された場合、賃貸借契約書の所定の欄と承諾書に署名・捺印をしてもらえば手続きは完了だ。不動産会社によっては本籍地や勤務先、収入証明、住民票、印鑑証明といった書類・情報の提供が追加で必要になる場合もある。
必要書類は連帯保証人となる人本人に署名・捺印してもらう必要があり、代筆はできない。郵送でも手続きできるが、不備があった場合は再提出を求められる。念のため、時間に余裕をもって書類を準備するように依頼しよう。
賃貸物件の連帯保証人に連絡が入り、支払いが発生するまでの流れ
考えたくない話だが、なんらかのトラブルが発生した際は連帯保証人が責任を負うことになる。この項目では、賃貸物件の連帯保証人に貸主からの連絡が入るまでの流れを解説しよう。
①借主に電話や郵送で連絡が入る
滞納等のトラブルが発生した場合、まずは貸主が借主に連絡を取る。
支払いをうっかり忘れていたという事情であれば、この段階で解決できるため、連帯保証人に連絡が行くことはない。
②内容証明が届く
借主が電話や郵送の連絡を無視していたり、支払いに応じなかったりした場合、借主に対して貸主が内容証明を発送する。
一般的に内容証明には、特定の期日までに滞納額等を支払うことが記載されており、併せて期日を超過した場合は連帯保証人に請求することなども記されていることが多い。
③連帯保証人に連絡が入る
借主が内容証明にも反応しなかった場合、貸主から連帯保証人に連絡が入る。ここで事情が説明され、滞納額や支払い期日が伝えられるという流れだ。連帯保証人は借主と同じ責任を背負うことになるため、貸主からの請求には応じなければならない。
次は、現在賃貸生活をしている人が「連帯保証人」を誰にお願いしているかのアンケート結果をご紹介。また保証人が立てられない場合の対処法についても解説しているので、ぜひチェックしてみよう。
みんなは、賃貸物件の連帯保証人を誰にお願いしているの?事例をご紹介

「あまり深く考えずに、親にお願いしています。ほかに頼める人もいないし、頼もうとも思ったことがないです。ちなみにバイクのローンの保証人も父親です」
(男性・20代)
「学生の頃から、当たり前のように親に頼んでいます。地方の実家から収入証明などの書類を送ってもらうのが面倒ですが……」
(女性・30代)
「親が定年退職したので、兄弟に頼んだり、頼まれたり、という感じです。やや面倒に感じ、保証人不要の物件にも住んだこともあります」
(男性・30代)
「仙台から上京して早10年。一人暮らし向けの賃貸マンションの連帯保証人はずっと父親です。父は数年前にリタイアしていて、現在は無所得ですが、大家にはまだ伝えていません」
(男性・40代)
「以前、ストーカーが近所に引越してきて、怖い思いをしました。賃貸マンションで万が一事故、事件、トラブルが起きた場合、親族が一番力になってくると思います。そういうことも考えると親族にお願いするのが一番安心ですね」
(女性・30代)
やはり両親や親族に連帯保証人を頼んでいる人が多い。今回のアンケートでは、友達に連帯保証人を依頼している人はいなかった。デリケートな話題なだけに、友人関係にヒビが入らぬように依頼を避けている人が多いのだろう。
※連帯保証人についてのアンケート調査(CHINTAI調べ 2017年8月)
賃貸物件の連帯保証人が立てられない場合は保証人不要の物件を選ぼう
連帯保証人は誰でも良いというわけではなく、審査を通過しなければならない。大きな責任を負わせることになるため、引き受けてくれる人がいない場合や、親や親戚にも頼みづらいというケースも考えられる。
賃貸物件の連帯保証人が立てられない場合、保証会社を利用しよう

このように連帯保証人を立てにくいケースもあるため、最近では連帯保証人を代行する「家賃保証会社」の利用が定着している。ただし、家賃保証会社に加入すれば必ずしも「保証人が完全に不要」になるとは限らない。物件によっては、保証会社の利用に加えて別途保証人が必要になるケースや、保証会社への加入自体に保証人が必要となるケースもある。
家賃保証会社は、入居者が保証料を支払うことで連帯保証人の役割を担ってくれる仕組みだ。契約時に入居希望者が保証会社へ申し込み、審査に通過すれば保証契約が成立し、保証料を支払う。保証料の支払い方法は会社によって異なり、契約時にまとめて支払う形式や、更新時・月額で発生する形式などがある。
借主が家賃を滞納した場合、貸主は家賃保証会社から立て替えで家賃を受け取ることができ、督促や回収も保証会社が対応してくれる。借主は連帯保証人を頼まなくても契約でき、貸主は家賃未納のリスクを回避できるという双方にメリットのある制度だ。
このような背景から、近年では「連帯保証人ではなく家賃保証会社の利用が必須」とされている物件も増えている。
昔ながらの連帯保証人の制度が採用されている物件もあれば、家賃保証会社の利用が必須とされる物件もある。入居者側が自由に選べるわけではなく、物件や貸主によって条件が異なるため、自分のライフスタイルや事情に合った条件の物件を選ぶことが大切だ。
家賃保証会社を利用した「保証人不要」物件の仕組み

物件情報の条件欄に「保証人不要」と書かれた物件を見かけたことがある人もいるだろう。前述のとおり、連帯保証人を立てたくても身近なところで候補者を見つけられず、賃貸借契約を結べないというケースが増えている。そういった問題を解決するために登場したのが「保証人不要」という条件の物件だ。
ほとんどの場合、「保証人不要」の物件では家賃保証会社の利用が必須とされている。連帯保証人を頼める人が見つからず困っている人は、「保証人不要」の条件で検索したり、不動産会社の担当者へ相談したりしてみると良いだろう。
注意点:家賃保証会社と連帯保証人の利用、両方が必要な物件もある
大家さんの方針によっては、家賃保証会社と連帯保証人の両方が必要という厳しい条件の物件もある。
また、家賃保証会社の利用に際して「連帯保証人はいらないけれど、保証人は必要」とされるケースも存在する。これは、保証会社の対応範囲が「家賃の滞納」に限られ、原状回復費用や損害賠償などへの保証が含まれない場合があるからだ。
保証会社を利用すれば誰でも保証人なしで借りられるとは限らないため、事前に契約条件をよく確認しておこう。
正しく理解したうえで賃貸物件の連帯保証人をお願いしよう・引き受けよう!
賃貸物件を借りるときに探さなければならなかった連帯保証人だが、責任が重すぎるため親戚や友達に気軽に頼めるものではない。連帯保証人のリスクを正しく理解したうえでお願いすることや、引き受けることが大切だ。
CHINTAIでは物件を探すときに、「家賃保証会社必須・利用可」「保証人不要」を条件として検索することができる。連帯保証人を立てられない場合でも借りられる部屋は多くあるので、あきらめずにお気に入りの物件を探してみてはいかがだろうか。
文=B面ばなな+ノオト
イラスト=キタハラケンタ
2022年2月加筆=CHINTAI情報局編集部




























