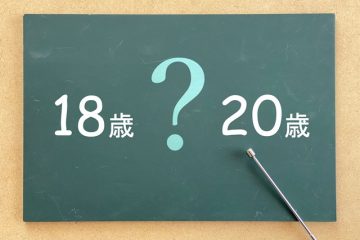2022年5月に賃貸物件の電子契約が解禁! 知っておきたい入居者のメリットも解説
「賃貸物件の電子契約解禁」について徹底解説!
賃貸物件や暮らしに関するニュースを深掘り。賃貸ユーザーが知って得する情報をお届けする。
今回は「賃貸物件の電子契約」をピックアップ。賃貸契約はどう変わるのか? 賃貸ユーザーのメリットは? 気になるポイントを解説する。
このページの目次
【ニュース】法改正が施行されて電子契約が全面解禁

2022年5月中旬までに賃貸物件の電子契約が解禁される。電子データにインターネット上で署名することで賃貸契約が可能となり、オンライン上でお部屋探しが完結できるようになる。
今までの宅建業法(宅地建物取引業法)では、賃貸契約を結ぶ際は紙の書面による署名・捺印が義務だった。そのため、賃貸物件を借りる際は入居申込後、必ず一度は不動産店舗を訪問しなければならなかった。
しかし、去る2021年5月、デジタル改革関連法(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律)が成立。宅建業法が改正され、重要事項説明書と不動産賃貸借契約書の書面による交付義務がなくなった。
ただし、この法改正は「2021年5月19日の公布日から1年以内」の施行とされたため、2022年4月まで未実施。今までもオンラインでの重要事項説明(IT重説)や賃貸物件の更新契約は可能だったが、賃貸物件の新規契約はできなかった。それが、遅くとも2022年5月18日までに解禁される予定だ。
賃貸物件の電子契約=契約書の電子化+オンライン上での署名・捺印
そもそも電子契約とは「インターネット上で電子ファイルを交換して電子署名を捺印することで契約を結ぶ」こと。電子媒体だが、従来の紙と判子と同様に法的な効力が認められる。
賃貸物件の電子契約の場合、重要事項説明書と重要事項説明書を電子ファイル化する。メールで送信したり、クラウド上にあるファイルにアクセスしたりして契約内容を確認。押印は基本的に電子署名あるいは電子印を利用する。
入居審査に受かったら重要事項説明を行い、そのまま重要事項説明書と不動産賃貸借契約書に署名・捺印をする。それら一連の流れをすべてインターネット上で行うようになる。
【深掘り】賃貸物件の電子契約が与える影響とは?

賃貸契約の電子契約は、不動産会社と賃貸ユーザーにどのような影響を与えるのか? 国土交通省は「重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験」を行い、307社の事業者(不動産会社)が参加。賃貸取引に関する実験は、2019年10月から開始された。
実験の検証は事業者と一般ユーザーへのアンケートで行われたが、否定的な意見は少なかった。電子書面交付によるトラブルは事業者側の98%、ユーザー側の95%が「なかった」と回答。起こったトラブルもネット接続や操作に関するものが主で、再接続や設定の変更により対応できると考えられている。
電子書面交付のメリットは事業者の場合、「書類の管理が楽になる」が28%、「契約のスピーディさ」が40%、「特にない」が51%。ユーザーの場合は「契約のスピーディさ」が76 %で、「特にない」は9%に留まった。
デメリットは事業者側の場合、「紙と比較して全体像が把握しにくい」が20%、「閲覧に電子機器を必要とする」が20%、「特にない」が61%。ユーザーの場合は「紙と比較して全体像が把握しにくい」が36%、「操作方法がわかりにくい」が28%、「特にない」が38%だった。
プラスの効果を見出せる事業者は半数程度にとどまったのは、事業者もユーザーもデジタルに不慣れな人には効果が実感しづらかったからだろう。逆に、価値を見出した人にとっては、賃貸契約に関わる手間が削減されることを利点と感じていたと推測される。
※参考:国土交通省 「重要要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験【結果報告】」
「電子契約は選択肢の一つとして普及する」と予測

同社会実験に参加した、三井のリハウスを展開する三井不動産リアルティに電子契約の効果について質問した。同社は、電子契約による手続きの軽減を実感。「電子契約とIT重説の導入によって、契約書類を郵送する手間が軽減。郵券費も削減できました」と話す。
国交省が実施したアンケート結果と近しい答えだが、それはトラブルの有無についても同様だった。オンラインでの手続き中にユーザーから操作に関する問い合わせがあったが、事前にガイドブックを提示することで以降のトラブルを減らすことができたそうだ。
そんな同社では、電子契約を望まれる賃貸ユーザーへの「サービスの一つ」として導入を検討している。
電子契約を導入しても書面での手続きはなくしませんし、通信環境が用意できないお客様には書面でお手続きいたします。もちろん、デジタルの操作に不慣れなお客様が電子契約を利用する場合には、戸惑われないよう丁寧にご案内いたします
一方で、気になるのは賃貸物件で電子契約が普及するかどうか。同社に尋ねると「法改正が進むことで電子契約は普及すると認識しています」と回答。さらに「現状の課題は、保証会社への加入など関連する手続きは電子化されないことです。しかし、賃貸物件の電子契約が普及すれば、それらも加速度的に解決に向かうと予測しています」と期待を滲ませた。
【ポイント】電子契約で賃貸ユーザーの物理的・経済的が削減

社会実験の反応から想像するに、賃貸物件の電子契約は多くの会社で導入されるはず。となると、気になるのはユーザーが得られるメリットだ。三井不動産リアルティ社に聞くと「オンライン上で手続きを進められることが、様々な利点を生んでいます」と言う。
お客様の感染リスクが少ないですし、時間の制約も少なくなります。お客様からも好評で『来店する手間を省けた』『締結書類が届くスピードに驚いた』との声をいただいています
電子契約の導入は義務ではないため、不動産会社によっては利用できないのは注意点だが、電子契約の実現によって賃貸契約に関わるさまざまなコスト削減が期待される。具体的には下記のようなメリットが想定されている。
メリット1:スキマ時間に契約ができる
店舗に足を運ぶ必要がなくなるので、仕事や学校の休憩時間などに契約の締結が可能。時短できるだけでなく、契約日を調整しやすくなる。引越しのダンドリが組みやすくなるのもポイントだ。
メリット2:お部屋探しの費用を節約できる
電子契約なら、必要書類の郵送料や店舗までの交通費を浮かすことができる。大学進学や転勤などで遠方に引っ越す場合は、かなりの節約となる。
メリット3:契約書の作成が楽になる
氏名や住所などを何枚もの必要書類に手書きせずに済む。書き間違えても簡単に修正できるし、提出後にミスが発覚してもオンライン上ですぐに手直し可能。書類作成に係る手間や時間を大きく省ける。
メリット4:審査がスムーズになる
オンライン上で必要書類を確認できるため、入居審査にかかる時間も短くなる。特に、紙の契約書では記入ミスがあった場合に書類の書き直しや受け渡しに時間がかかっていたが、電子契約ならユーザーの修正も大家さんの再確認もスムーズに行える。
メリット5:重要書類を保管しやすくなる
重要事項説明書と不動産賃貸借契約書をPCやスマホで保管でき、破損したり紛失したりするリスクがなくなる。入居や退去などの規約を確認する際も、検索機能で容易に見つけられる。
【まとめ】電子契約で賃貸物件がより借りやすくなるかも!

電子契約のメリットは、今後さらに拡大するだろう。不動産会社のペーパーレス化が進んでコストがさらに削減できれば、その余力分サービスが向上する可能性があるからだ。
三井不動産リアルティに業務改善で節約できたコストや時間をどのように活用したいか聞いてみたところ、「契約だけでなく手続き全般の効率化に活用したい」と回答。さらに「その結果として、さらに付加価値が高いサービスを創出できると考えています」と教えてくれた。
同社のような会社が増えれば、賃貸ユーザーによってうれしいサービスも増えるはず。将来的には仲介料の値下げやお得なキャンペーンの実施などで、付加価値を生み出す不動産会社も現れるかもしれない。賃貸ユーザーとしても、電子契約の普及に期待したい。
取材・文=綱島剛(DOCUMENT)