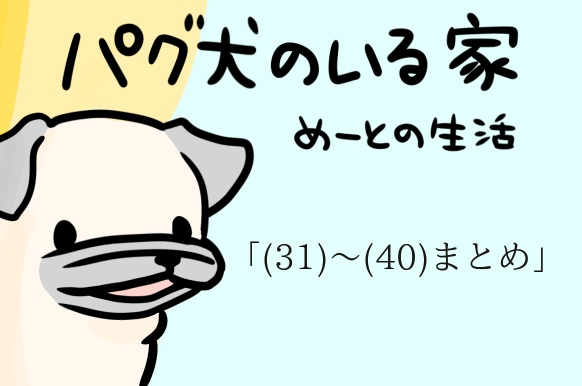洗濯したタオルや洋服の生乾き臭が気になる!原因や消す方法、防ぐためのポイントを解説
部屋干ししたタオルや洋服は生乾き臭が気になる!

湿度が高く、ジメジメとした雨の日。部屋干しをすると洗濯物がカラッと乾かず、いざ着るときになって洋服の「生乾き臭」が気になる人も多いのでは?
そこで今回は、洗濯物のイヤなニオイ、生乾き臭につながる菌の繁殖を抑える方法、早く乾かす干し方のコツを徹底解説!簡単にできる対処法で洗濯物の生乾き臭を抑えて、梅雨を乗り切ろう。
部屋干しのコツを詳しく解説した記事はこちら!
このページの目次
洗濯物の生乾き臭は「菌」の繁殖によるもの
生乾きの洗濯物からニオイが発生する主な原因は「菌」である。湿度が高い状態では衣類やタオルにカビや菌が繁殖しやすく、これがイヤなニオイを発生する原因といわれている。
ただし、菌そのものがニオイを発生させるわけではない。菌が洗濯物に付着・増殖し、フンのような排泄物を出す。その排泄物が生乾き臭の原因といわれているのだ。
いずれにせよ、悪臭を消すには菌やカビの繁殖を防ぐことが必要といえる。
生乾き臭=菌が発生する原因とは

生乾き臭の原因となる菌が増殖してニオイを発生させるには、いくつかの原因がある。
菌が発生する原因①:汚れた衣類を長時間放置していた
洗濯方法に目がいきがちだが、実は洗う前の保管方法も大切。汚れた衣類や湿ったタオルには、汗や皮脂汚れ、食べこぼしなどが付着しており、菌が繁殖しやすい環境だ。すぐに洗濯しない場合、湿った衣類は少し乾燥させたり、乾いた衣類洗濯物とは分けておいたりするなどの工夫が必要になる。
菌が発生する原因②:洗濯後すぐ干さずに放置していた
菌は水分によって活性化するため、洗濯後はなるべく早く乾かす必要がある。また、洗濯槽に入れっぱなしの状態では洗濯槽自体にも菌が繁殖してしまう。
洗濯後に湿った状態で放置してしまうという方もいるだろう。しかし、菌が繁殖した洗濯槽から大事な衣類に菌が移ることもあるので、洗い上がったら洗濯機から出し、早めに乾かすクセをつけてほしい。
菌が発生する原因③:干してから乾くまでに時間がかかった
生乾き臭を予防するために大切なのは、洗濯物が乾くまでにかかる時間だ。生乾き臭の原因菌は5時間経ったころから増殖するといわれているため、洗濯後5時間以内に乾かすのがベスト。ただ、雨の日や梅雨の時期はどうしても部屋干しが多くなり、乾くまでの時間がかかりがちだ。
生乾き臭は、梅雨の時期特有の現象と思われがちだが、秋~冬の雨の日でも多く見られる。日照時間が短く気温も下がるため、洗濯物が乾きにくくなるためだ。
部屋干しは生乾き臭が発生しやすい
生乾き臭の原因となる菌を増殖させやすいのは高温多湿の環境だ。具体的な条件としては、室温20〜30℃、湿度が60%を超えるとカビ・菌が増殖しやすいといわれている。
特に、梅雨や秋の長雨の時期は気温・湿度ともに高くなるため、この条件に当てはまりやすいので注意が必要だ。
時間がないときはコレ!洗濯物の生乾き臭をすぐ改善する2つの応急処置

着るときに生乾きのニオイに気づいたときは、スチームアイロンや消臭スプレーなどを活用しよう。応急措置とはいえ、イヤなニオイを抑えられる。具体的な使い方は以下のとおりだ。
生乾き臭の応急処置①:スチームアイロンを使う
まずはスチームアイロンだ。生乾き臭の原因菌は60℃以上の高温に弱い。このため、スチームの高温と、噴射する勢いで悪臭を除去できる。ただし、かけムラのほか、温度設定が低いとニオイが復活する可能性があるので注意しよう。なお、威力は弱いが、ドライヤーでも代用できる。
生乾き臭の応急処置②:消臭スプレーを使う
サッと簡単に応急処置できる消臭スプレーも活用できる。香りをプラスするファブリックスプレー等ではなく、消臭効果が期待できる製品を使おう。外出先でも使うことができるので便利。
洗濯物の生乾き臭を消す4つの方法
一度ついてしまった生乾き臭を消すには、通常の洗濯ではなく一工夫加える必要がある。ニオイの原因ともいわれる菌は熱に弱いという特性があり、60℃以上のお湯につければ約20分で死滅するといわれている。
ここでは生乾き臭を消す方法をご紹介するので、自分に合ったものを選んで試してみてほしい。
生乾き臭を消す方法➀:石鹸や重曹を使い、煮沸する
タオルにおすすめの方法がこちら。大きな鍋でお湯を沸かし、そこに洗濯用の石鹸と衣類を入れて20〜30分ほど煮沸する。もし石鹸がない場合、掃除の際に使う重曹でも代用できる。
鍋の大きさについては特にルールはないが、アルミ製の鍋は使用できないため注意が必要だ。石鹸や重曹はアルカリ製で、アルミを腐食させる力がある。何度も使用すると穴が開いてしまう可能性があるため、アルミ製ではなくステンレス製の鍋等を使用しよう。
生乾き臭を消す方法②:コインランドリーの乾燥機を使う
家庭用の洗濯機にも乾燥機能が付いている場合はあるが、生乾き臭を抑えるにはコインランドリーの乾燥機が効果的だ。家庭用乾燥機の温度は最大で60℃ほどであるのに対し、コインランドリーの乾燥機は80〜120℃の温度である場合が多く、より高い殺菌効果が期待できる。また、コインランドリーであれば自宅では洗いにくいベッドシーツ等も洗えるため、特に汗をかきやすい夏場に活用できる。
生乾き臭を消す方法➂:電子レンジを使う
手を拭くハンカチやタオルなど、小さめのアイテムのニオイが気になるときは、電子レンジの使用もおすすめだ。ニオイを消したいタオルやハンカチを水に濡らしてラップで包み、500Wで約1分加熱しよう。取り出した後は少し冷まし、いつも通り洗濯すれば完了だ。
ただし、取り出すときは高温になっているためやけどに注意しよう。さらに、化学繊維は電子レンジに対応していないため、この方法は素材が綿100%のもの、装飾のないものだけにしよう。
生乾き臭を消す方法④:クリーニング店に持ち込む
デリケートな素材の洋服は上記に挙げた方法が使えない場合が多い。このため、クリーニング店に持ち込むことになる。ただし汗などの水溶性のニオイは、クリーニング店で一般的に行われるドライクリーニングでは落とすことができない。
そこで有効なのが「ウェットクリーニング」だ。ウェットクリーニングとは、水で洗えない衣類を特殊な洗剤を使用して水洗いするクリーニング方法だ。自宅で洗濯しにくいものの生乾き臭にはぜひ試してみてほしい。
【洗濯編】生乾き臭を予防する6つの方法・ポイント

ここまでは、洗濯物を部屋干ししたときのイヤなニオイ、生乾き臭のメカニズムについて解説した。ここからは、具体的な対策方法をご紹介する。まずは、部屋干し臭・生乾き臭の原因となる菌の繁殖を抑えるための対策をチェックしていこう。
➀洗濯槽を洗浄する
生乾き臭は、洗濯槽に潜む菌が衣類に付着することで発生することもある。実際、長年使っている洗濯槽には知らずのうちにカビが生えていることも……!
菌の繁殖やニオイの発生を防ぐためにも、洗濯槽のお手入れは必要不可欠。最低でも2ヶ月に一度は洗濯槽クリーナーで洗浄しよう。なお、後述する衣類用の酸素系漂白剤も、洗濯槽の掃除に使用することができる。
また洗濯槽のカビ・菌繁殖を予防するために、毎回の洗濯後には蓋を開けておき、洗濯槽をしっかり乾かすようにしよう。
②衣類を詰め込みすぎない
洗濯では「洗濯量」と「乾燥容量」をチェックしておこう。1回の洗濯量が多いと洗剤成分が衣類の隅々まで行き届かず、汚れやニオイが残ってしまう可能性がある。
洗濯機に入れる量は、洗濯量・乾燥容量それぞれの7割程度が目安といわれている。また、洗濯で乾燥機能を使う場合、洗濯量よりも乾燥容量の方が少ないため、乾燥容量に合わせて洗濯しよう。
➂洗濯前に「酸素系漂白剤」でつけ置きする
酸素系漂白剤には洗濯物の汚れをしっかり分解して落としやすくする効果があり、また除菌・殺菌力もある。洗濯機で洗う前に、衣類向けの酸素系漂白剤でつけ置きしておくことで、生乾き臭を予防することができる。
酸素系漂白剤の主成分は「過炭酸ナトリウム」。水に溶けると水と酸素を発生させ、その際、洗浄・除菌・漂白効果を発揮するという仕組みだ。
ちなみに、漂白剤には主に「塩素系」と「酸素系」の2種類がある。塩素系の方が漂白力・殺菌力は強いが、ツンとしたニオイが特徴で色柄物の衣類には使用できない。間違えないように注意しよう。
④すすぎに残り湯を使わない
節水のため、お風呂の残り湯を使ってすすぎをする方も多いだろう。しかし、お風呂の残り湯は菌が多く含まれており、生乾き臭を発生させる原因のひとつともいわれている。もし残り湯を使用するときは、「洗い」は残り湯を、「すすぎ」は水道水を使うようにすると生乾き臭を予防できる。
⑤脱水は2回に設定する
干す前にしっかり脱水することで、洗濯物が乾くまでの時間を短縮できる。洗濯機の設定で脱水が1回の設定になっている場合は、洗濯機から洗濯物を取り出す前に再度脱水をかけよう。ただし注意点として、シワや型崩れが気になる洋服は2回目の脱水を行う前に取り出しておくのがポイントだ。
⑥洗濯物は風通しの良い場所に、すぐに干す!
洗濯物を干すタイミングと場所に注意してほしい。洗濯物に水分が多く含まれる生乾き状態は、菌にとって繁殖しやすい絶好のチャンス。洗濯物を濡れた状態で放置すればするほど、菌は増殖するのだ。
そのため、洗い終わった洗濯物は放置しないのが鉄則!洗濯後は洗濯機に長時間放置せず、すぐに干すようにしよう。また少しでも洗濯物が速く乾くよう、風通しの良い場所に干すなどの工夫を。
【干し方編】生乾き臭を予防する4つの方法・ポイント
菌対策に加えて、部屋干し臭を防ぐうえで重要なのが、洗濯物を素早く乾かすこと。洗濯物を早く乾かすには、一般的に日照・気温・湿度・風という4つの要素が必要といわれている。これらをふまえて、衣類を素早く乾かす4つの対策法を見ていこう。
生乾き臭を防ぐ干し方①:間隔を空けて洗濯物を干す
1つ目の対策法は、間隔を空けて洗濯物を干すこと。洗濯物の間から風が通るようになり、効率よく洗濯物を乾かせる。
室内干しの場合は干せるスペースも限られるため、洗濯物は溜め込まず、一度に洗濯する量はほどほどに抑えるのがポイント。物干し竿にかけた際、ある程度のすき間ができる量を目安に洗濯しよう。
ちなみに、タオルや靴下などを吊るす「ピンチハンガー」に干す際は、両端に長い衣類、内側に短い衣類と、アーチ状に吊るすのが正解!こうすることで通気性が高まり、洗濯物がより早く乾く。
生乾き臭を防ぐ干し方②:扇風機などで洗濯物に風を当てる
2つ目の対策法は、扇風機やサーキュレーターを使って洗濯物に風を当てること。雨の日の部屋干しでは、窓を開けるのが難しい。そこで、扇風機やサーキュレーターを活用しよう。
ポイントは、扇風機の首振り機能を使って洗濯物全体に風を送ること。もしエアコンからも風を当てられる場合は、エアコンとは別方向に扇風機を設置することで、さらに効率的な乾燥が可能になる。
生乾き臭を防ぐ干し方③:エアコン・除湿機で除湿する
3つ目の対策法は、エアコンや除湿機で除湿すること。ジメジメとした湿度の高い室内では、洗濯物がなかなか乾かず、菌がどんどん繁殖してしまうことに。部屋干しする際は、エアコンの除湿機能(ドライ機能)を使って湿度を下げる工夫を心がけよう。
エアコン以外に、除湿機の活用もおすすめだ。最近の除湿機には、衣類乾燥機能や送風機能がついているものも多く、よりスピーディーな乾燥が可能!部屋干しすることが多い人は、ぜひ1台取り入れてみては。
生乾き臭を防ぐ干し方④:浴室乾燥機・洗濯乾燥機の活用も◎

もし自宅に浴室乾燥機・洗濯乾燥機があるなら、梅雨時には積極的に活用したいところ!ただし、それぞれ注意点があるのでおさらいしておこう。
浴室乾燥機を活用
数時間で効率よく洗濯物を乾燥させてくれる「浴室乾燥機」。浴室乾燥機を使う際は、浴室内に水分が残っていない状態で使うのがポイント!浴室内に水分や湿気が残っていると乾燥に時間がかかり、結果的に生乾きになってしまうことも……。
入浴後であれば床や壁を拭く、部屋干しをする前に浴室乾燥機を回しておくなど、ある程度浴室内の湿度を下げておくようにしよう。
洗濯乾燥機を活用
生乾き臭の悩みを解消してくれるのはもちろん、部屋干しする手間すらなくしてくれる「洗濯乾燥機」。ドラム式洗濯乾燥機を使うときには、乾燥運転のたびにフィルターのお手入れが必要だ。
乾燥フィルターが目詰まりすると、乾燥ムラや乾燥時間が長くなる原因になり、結果的に生乾きになってしまうことも。必ず毎回、フィルターのホコリや糸くずを取り除くようにしよう。
併せて、基準の重量を守ることも大切だ。ちなみに素材によっては洋服が縮んでしまうこともあるので、衣類表示のチェックは忘れずに!
部屋干しでも臭わない!少しの工夫で生乾き臭は防げる

つい憂鬱になってしまう雨の日の洗濯物。それでも、生乾き臭の原因や菌対策、干し方のコツを知って洗濯物をカラッと乾かすことができれば、少しは気持ちがラクになるかも……!?
まずは手軽にできることから、生乾き臭対策や部屋干しのコツを実践してみては?
※参考
・松永 聡,(2005)「日常生活における洗濯衣料の部屋干し臭とその抑制」
・兵庫県立生活科学究所,(2006)「洗濯物の室内干し」
文=編集部
2022年4月加筆=CHINTAI情報局編集部