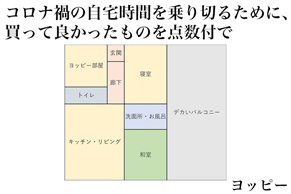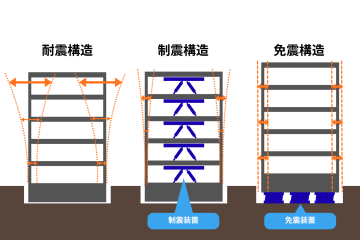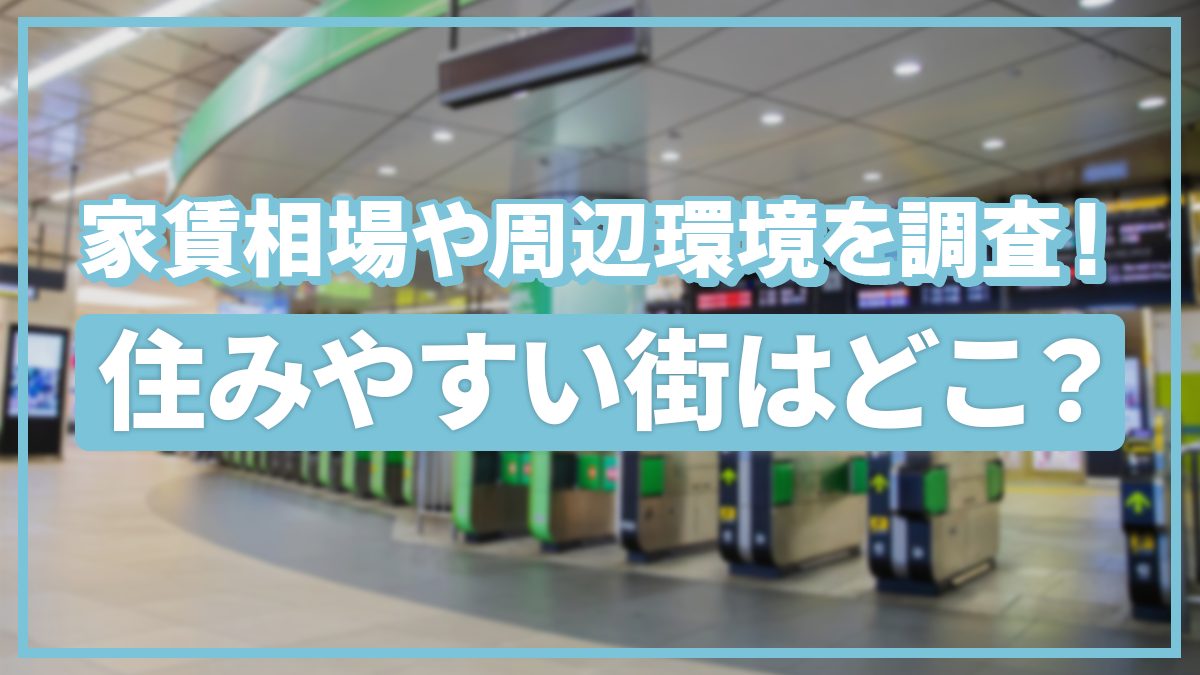【おもいでの部屋】南町田での、救われない一人暮らし|夏生さえり
きっと、だれにでもある思い出の部屋
住んだ部屋には人それぞれ、そして様々な思い出がある。そんな部屋の思い出を覗いてみたくはないだろうか?
忘れられないあの部屋で起こったこと、あの部屋で過ごした大切な時間、「おもいでの部屋」についてリレー形式で綴ってもらうこのコラム。
第1回は、フリーライターの夏生さえり(@N908Sa)さんのエピソードをお届け。

救われない暮らしの断片
「ねえ、なんで泣いてんの?」
彼氏と喧嘩をして街でうずくまって泣いていると、声をかけられた。そこにいたのは彼氏でも友人でもなく、知らない男の子たち。6人くらいいただろうか。いわゆる“ヤンキー”という風貌で、顔はまだあどけなく、おそらく高校生であるのにタバコを吸って酒を持っていた。ピアスを山ほどつけている子もいれば、サイヤ人のように金髪を逆立てている子もいた。
上京して最初に住んでいた「南町田駅(2019年に南町田グランベリーパーク駅という名称に変わっている)」と学校をつなぐ間にある、「町田駅」での出来事である。
おそらく0時ごろで、本当なら怖がってもいいはずなのに、わたしは怖がるどころか喧嘩の詳細を彼らに話していた。話すというか、溢れるとかいうか。誰に話していいかわからないような瑣末な出来事を、それでも誰かに聞いて欲しかったのだ。切実に。
「今、電話で、彼氏と喧嘩して。今から、女の子がたくさんいる飲み会に行くんだって。来て〜って呼ばれたからって。どうしてそんなことわざわざわたしに言うの?って喧嘩になって。それにこの前もね……」
知らない人に、しかも“ヤンキー”に、くだらない喧嘩の愚痴を言うなんて馬鹿げているよなとわかっているのに止められない。
「そっかー。彼氏、ひどくね? 彼氏、俺らより頭はいいかもしんないけど、俺らのほうが人の気持ちはわかってっから。女を不安にさせる男は、全員クソだよ」
途中で何人かはわたしの話に興味を失って、少し離れてタバコを吸っていたけれど、最後まで聞いてくれた眼鏡をかけた男の子がそう励ましてくれて、隣にいた男の子も「それな」と言って、わたしは笑った。ヤンキーの男の子って本当に情にアツいんだ。一度、頭の冷めた部分で思うと、笑えて笑えて仕方がなくて、泣き笑いすると彼らも笑った。夜の町田が涙で滲んで、ゆらゆら光った。
「おっ、元気になったの?」と少し離れていた、リーダー格っぽい男の子が戻ってきて「声かけたのが俺らでよかったけど、あぶねーから帰りな」と励まして、住んでいる「南町田駅」まで何人かが送ってくれて、その途中で、人生ではじめての補導もされた。
別れ際に、「で、なんでその男のこと好きなの?」と改めて聞かれて、少し悩んで、素直に答えた。「好きっていうか、寂しいから一緒にいてほしいの」。男の子はキュッと難しい顔になって「他にも一緒にいてくれるやつはいるだろ。ダチでもいいしさ」と言って、わたしは(そうかなぁ)と力なく笑うに留めた。
大学1年生の“間違いだらけの日々”の中でも、色濃く残る出来事である。
最後まで好きになれなかった、はじめての部屋

酒に弱いくせに飲んでいた頃
上京して、最初の間違いは「はじめての部屋探し」であった。
「南町田駅」は学校まで一度乗り換えなくてはならず、不便に違いないのに、わたしは「絶対に友達が入り浸るような部屋にはしたくない」と断固言い張って、わざわざ遠い駅にした。今ならこうアドバイスする。「友達が入り浸ってくださるように、学校の近くに住みなさい」。
部屋探しの基本がわからないから、母が言うことすべてが正しいような気がして、母が「いいじゃん」と言うから「いいのかも」と思って決めた。4階建のマンションで、8畳の1K、6万3000円。窓からは線路と工場だけが見える、特徴もない無機質な家。リビングは絨毯張りだったが、母は「フローリング風のビニールマットを敷けば、防音・防寒で、むしろフローリングよりもいいかもよ」なんて言うから、これまた「いいのかも」とそそのかされた。
けれど、ビニールマットを敷き詰めた時まではよかった見栄えも、わがままを言って買ったアイアンのベッド(金属なので重たい)や、外置きのクローゼット、テレビやローテーブルなんかをおけば局所的に沈んで、そのせいでぶよぶよと床全体が歪んで見えるようになった。
時空が歪んでいるみたい。
部屋を眺めながら、泣きながらそう思った。時計の音はカチカチとなり続けるが、ほとんど時間が進んでいないような気がする。もう友達には一通り電話をかけたし、彼氏とは喧嘩をしたし、街に人はいないし、朝を待つしかないのにまだ3時。記憶の中で、わたしはいつもそんな風に部屋で途方に暮れて泣いている。寝転んで、ぽっこり歪んだビニールマットを指で撫でて、パタパタと涙を落とす。
なにをどうすればこの孤独から逃げられるかわからずに、精神科に行ったこともある。
「彼氏とうまくいかないし、さみしいし、つらくて」とか言ったんだろう。医者はなんて言っていたか、何も思い出せない。
上京して丸々2年間、わたしはこの部屋で、とにかく危なっかしい日々を過ごした。
みんなどうやって自分の「好き」を知るのだろう。最初から一人暮らしが楽しくて仕方がない人は、いつの間に自分の「楽しい」を知ったのだろう。
わたしは、自分が一体なにが好きで、なにが嫌いで、どんな家に住みたくて、どんなものが欲しくて、どうなりたいのか、なにひとつわからなかった。それどころか、自分の輪郭さえぶよぶよと心許ない状態で、他人と自分の感情に簡単に侵食されては泣いて、東京の空気の中で立ち尽くしていたように思う。
町田駅で知らない人に慰めてもらう

誰かに囲まれた写真をできるだけ撮りたかった
ひとりぼっちで泣きたい時は南町田駅で、すこしは人の気配が欲しい時は町田駅で泣いた。今考えれば泣く場所を選ぶ程度には、冷静だったのだろう。むしろ定期的にデトックスに出かけるような気持ちだったのではないか。
ひとりで泣いてすっきりする晩もあれば、余計に虚しくなる晩もある。時には友達がかけつけてくれたり、冒頭のようにヤンキーの男の子たちが声をかけてくれたり、前歯がまるっと4本抜けたキャバクラのキャッチのお兄さんが慰めてくれたりした。
歯のないお兄さんは「だいじょーぶ?」と聞いて「彼氏と喧嘩―?」と、語尾をやたらと伸ばして聞く。人混みのすぐ脇でしゃがみこんでいるわたしの横にしゃがんで、ぼーっと人混みを眺めていた。怖い人かもしれないと一応は身構えたが、しつこいわけでもなく、ただただそばにいてくれる。だんだんと安心して、ちらりと顔をあげると、腕に「ERI」とガタガタの文字で掘られているのが目に入った。
「エリ」
小さく言うと「え?何?」と聞く。
あごでクイクイとお兄さんの腕を指すと、お兄さんは「あぁ、これか 」と笑う。
「元カノ。自分で掘ったの。別れちゃったけど。一生大事な女だから 」。お兄さんはスカスカの前歯で笑った。
そこから1週間も経たずして、同じ場所で泣いていたら駅前のシンガーソングライターが「いろいろあるけど、明日は元気になるよ」という趣旨の歌を歌ってくれた。歯のないお兄さんは、その日いなくて、すこしだけがっかりした。
友人や知らない人の優しさを分けてもらっても、寂しさは癒えなかった。夜中に彼氏を呼び出しても、なお寂しくなるだけだった。それもそのはずだ。孤独にもいろいろな種類がある。誰かといることで癒えるものと、自分の輪郭を持たないせいで起こるもの。わたしの場合は、後者だったのだ。穴のあいた器には、愛も楽しさも優しさも溜めることはできない。
間違いだとわかっていても。

「そんなこともありましたが、南町田の部屋を引っ越すころにはわたしは人生が楽しくなっていたのでした」と締めくくれたら、どれだけいいだろう。残念なことに、人生は、うまい具合にはできていない。わたしの南町田での思い出は、空虚でダサくて寂しくて泣いている姿のまま、ぷっつりと途絶えている。
それでも「思い入れのある部屋は?」と聞かれると、南町田の部屋を思い出してしまうのは、なぜだろう。好きな部屋ではない。輝かしい瞬間もない。大きな成長も変化もなかった。
あの頃のことを思えば、やっぱり今でも「間違っていた」と思う。
けれど、何度時間を巻き戻しても同じ間違いをするだろう。あの部屋を選び、ヤンキーの男の子や歯のないお兄さんの優しさに甘えて、好きでもない部屋へ帰って泣くだろう。そうする時間の中でしか、自分の「好き」を知り、自分の「欲しい」を知り、自分の輪郭をつくっていくことはできないと、今では痛いほどにわかるから。
結局、わたしが心の底から好きな人と、好きな家で暮らせるようになったのは、そこから10年もあとの話になる。10年間、進んだり止まったりくじけたり間違えたりしながら、よろよろと前進した。認めたくはないが、考えれば考えるほどあの南町田の部屋は、わたしの出発点としてものすごく相応しいような気がする。いつか最高になるわたしの、最低の出発の地。そう思えば、苦く笑いながらもこの部屋について書くしかないような、そんな気持ちになるのだった。