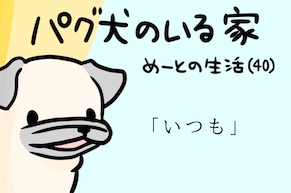鉄骨造の防音性はどう?防音性を確かめる方法、プロの防音対策を紹介

木造よりも耐震性があり、鉄筋コンクリート造より家賃相場が安くて人気な鉄骨造の物件。しかし、防音という観点ではどうだろう。鉄骨造の防音性や鉄骨造の物件のメリット・デメリットとともに、内見時に防音性を確かめる方法を紹介する。
また、株式会社ピアリビングの防音コーディネーター かぶちゃん(梶原 栄二さん)に鉄骨造の賃貸物件でもできる防音対策を教えてもらった。
鉄骨造(S造)とは
鉄骨造とは、柱や梁などの骨組みに鉄骨(鋼材)を使った構造のこと。鉄=Steelの頭文字を取って「S造」と表記されることもある。木造と比べると耐震性が高いうえ、建設コストが低いため、近い条件の鉄筋コンクリート造の物件に比べると家賃が安い傾向にある。
鉄骨造は「鉄筋コンクリート造」ではないため、壁をつくる際にコンクリートは使用しない。隣室との仕切りには石膏ボードが使われることが多く、コンクリート造よりも音が響きやすい。
軽量鉄骨造の特徴
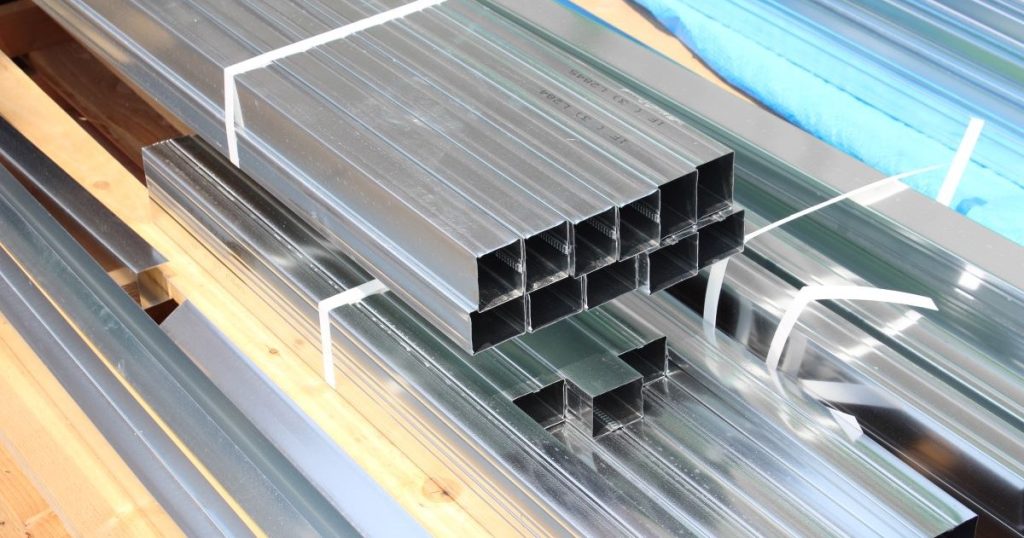
軽量鉄骨造は、厚さ6mm未満の鋼材を使用している鉄骨造を指す。工場で生産された建材を現場で組み立てる「プレハブ工法」を採用していることが一般的で、建物の形は画一的になりやすいが、建設コストは低い。戸建てやアパートに採用されることが多い。
また、鋼材が薄いため、耐震性や耐久性を高めるために複雑な構造になりやすいという特徴もある。柱と柱の間に斜めの「ブレース(トラス)」と呼ばれる金属製の補強材で補強することが一般的だ。
重量鉄骨造の特徴

重量鉄骨造は、厚さ6mm以上の鋼材を使用している鉄骨造を指す。軽量鉄骨造と同様、工場で生産された鋼材を使用し、現場では溶接といった組み立て作業だけを行うのが一般的だ。マンションや高層ビル、工場や体育館などの広い空間に採用されることが多い。
鋼材が厚く変形しにくいため、鉄骨の本数を減らした筋交いなしの「ラーメン構造」を採用するのが基本(ラーメンはドイツ語で「枠」を表す)。骨の数が少ない分軽量鉄骨造や木造よりも間取りの自由度が高く、すっきりとしたシンプルな構造に仕上がるという特徴がある。
軽量鉄骨造の物件の防音性は、あまり高くない
軽量鉄骨造は音を響かせにくい鋼材が入っている分、木造よりやや防音性が高い。しかし、骨組みの素材が異なるだけで、つくりは木造とあまり変わらないため、そこまで大きな差はない。部屋と部屋の仕切りには木造と同じ石膏ボードが用いられているため壁自体の防音性は木造と大きくは変わらない。
重量鉄骨造の物件は、軽量鉄骨造の物件と比べると防音性が高い
重量鉄骨造は、軽量鉄骨造や木造よりも防音性に優れている。重量鉄骨造は柱が太いため、その分壁も厚くなり、防音性も高くなる。ただし、軽量鉄骨造と同じく、密度の高いコンクリートの壁があるわけではないため、鉄筋コンクリート造と比較すると防音性は低い。
鉄骨造の物件の防音性を確かめる6つの方法
気になる賃貸物件が鉄骨造だった場合、どのようなことに気をつけて内見をするといいのだろうか。6つの方法を紹介しよう。
①静かな室内で周囲の音を確認する
防音性を確かめるために「壁に耳をあてる」という人は多いが、遮音性が高い部屋でもさまざまな音が聞こえるので、あまりおすすめではないそう。
不動産会社の担当者に席を外してもらい、静かな部屋の中の環境音に耳を澄ませてみるとよい。会話中には気がつかなかった音が聞こえるかもしれない。
②室内の壁やドアをノックする
内見に同行する不動産会社の担当者に許可を取り、隣の部屋と面する壁を軽くノックしてみよう。「コンコン」と軽い音が響くのであれば、壁の内側には石膏ボードしか貼られていない、防音性の低い壁である可能性が高い。
一方「ゴンゴン」と低い音が響いたり振動が抑えられていると感じたりする場合は、壁材が厚いもしくはコンクリートの可能性が高いので、防音性が高いと考えられる。
同じ面の壁でもノックする場所によって「コンコン」「ゴンゴン」と異なる音がする場合、「GL工法」といってコンクリートの壁に団子状のボンドを付けて石膏ボードを貼り付ける施工でできた壁なので、遮音性が低い。

また、同じような構造で二重壁工法というものがある。見極めが難しいが、二重壁工法の壁は、GL工法のようにコンクリートとつながっていないため、音が伝わりづらく遮音性は高くなる。

③窓を閉めた部屋で手を叩く
窓を閉めた室内で、強めに手を叩いてみよう。あまり反響しなかった場合は、壁などの隙間から音が漏れており防音性は低い可能性がある。
④ドアや窓枠に隙間がないか確認
音は隙間からも出入りする。ドアや窓枠の建付けを確認して、隙間がないかどうかを確認しよう。
特に築年数の古い物件は、経年劣化によってドアや窓枠の建付けに隙間が生じている可能性がある。またドアは重量があるほど遮音性に優れている。防音性を気にする方は、軽いドアの物件は避けたほうがいいだろう。
⑤窓のつくりをチェック
窓ガラスは壁よりも薄いことが大半なので音を通しやすい。ただし、二重サッシが採用されている物件は防音性が高い。最近は、幹線道路沿いや線路の近くの物件に二重サッシが使われているケースがある。
⑥間取りと部屋の位置をチェック
隣の居室とのあいだに収納スペースや水回りがあれば、緩衝地帯が発生し生活音は伝わりにくくなる。間取り図を見たり、不動産会社の担当者に話を聞いたりして確認しよう。
集合住宅内における部屋の位置も重要だ。角部屋であれば、隣の住戸と接する面が片方だけになるため騒音リスクを減らすことができる。子どもの足音など振動や騒音を出してしまう心配がある人は1階や下が駐車場になっている部屋を選ぶといい。
防音のプロが伝授! 鉄骨造の物件でできるカンタンな防音対策

鉄骨造の物件にすでに入居していても、防音性を高めることができる。賃貸物件でも可能な防音施策を株式会社ピアリビングの防音コーディネーター かぶちゃん(梶原 栄二さん)に教えてもらった。
カーテンを使った窓の防音対策
窓ガラスは壁よりも薄いため音が侵入しやすい。外の騒音だけでなく、隣の部屋の声なども窓を通して入ってくることがある。防音カーテンを取り付けることで簡単に遮音ができるので、ぜひ使用してみてほしい。
重量感のあるカーテンを使ったり、カーテンを二重にしたりするだけでもある程度の効果が期待できる。自宅でオンライン会議をする人は、機密情報保持のためにも役立つだろう。手持ちのカーテンの内側に設置するタイプの防音ライナーも便利なアイテムだ。
マットやカーペットを使った床の防音対策
階下に生活音を響かせないためには、スリッパを敷いたり、防音性の高いマットやカーペットを使ったりしてみよう。話し声やテレビの音を遮るだけでなく、足音や家具家電の振動を吸収し、騒音を抑えてくれる。
参考商品:防音タイルカーペット 静床ライト|防音専門ピアリビング
防音カーペットの購入はハードルが高いと感じるのであれば、マットと普通のカーペットなど異素材の床材を組み合わせてみるといい。その際は、できるだけ複数の層があり、繊維がたくさん含まれている材質の商品を選ぼう。
ちなみに、EVA樹脂やポリエチレンが素材の「ジョイントマット」は、単独ではあまり大きな防音効果を期待できない。カーペットの下に敷く、足音を抑えるマットなどと組み合わせて使うとよい。
参考商品:足音マット|防音専門ピアリビング
家具を使った隣接する部屋の防音対策
服が詰まったタンスや本が詰まった本棚などの家具を、隣の部屋に面した壁沿いに設置をすることで、家具が音の障害壁になる。隣に音を響かせたくないときにも、隣からの音を遮りたいときにも有効な手段だ。設置する家具がない場合は、防音のための障害壁を取り付けるのも手。「ワンタッチ防音壁」など原状回復が可能なグッズも販売されている。
家電やドアに防音グッズを取り付ける
洗濯機の振動音、ドアの開閉音などは、カンタンな工夫ですぐに軽減できる。洗濯機や冷蔵庫には足元に振動を吸収するゴムマットなどを設置してみよう。
ドアについては開閉回数の多い洗面所やキッチンの扉の音に対して苦情が発生しがちだ。戸があたる部分に100円均一などで売られているフェルトの吸音材や戸当たり防止テープを貼り付けるだけでも充分効果がある。
なお、最近では静音タイプの掃除機やロボット掃除機が普及したことから掃除機の音が苦情の元となるケースは少なくなった。それでも騒音が問題になっているのであれば、フローリングの目地に沿ってかける、カーペットを敷くなどの工夫をしよう。
賃貸物件の防音対策、騒音に悩みにくい物件選びについて詳しく知りたい方はこちら
参考記事: ジョイントマットは効果が薄い?賃貸の防音対策と防音グッズを専門家に聞いた
鉄骨造のお部屋にひと工夫して快適に暮らそう
鉄骨造の物件は、鉄筋コンクリート造などと比べると防音性は劣るものの、家賃が抑えられ、木造物件よりも耐震性に優れるなどのメリットもある。
また、鉄骨造でも使われている壁や床の材料によって防音性は変わってくるため、内見時には今回紹介したような方法で防音性をチェックすることが重要だ。必要に応じて防音グッズも活用しながら自宅の防音性を高めよう。
賃貸物件の防音対策、騒音に悩みにくい物件選びについて詳しく知りたい方はこちら
参考記事: ジョイントマットは効果が薄い?賃貸の防音対策と防音グッズを専門家に聞いた