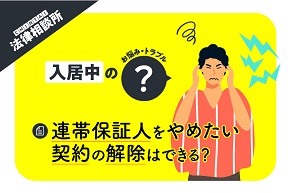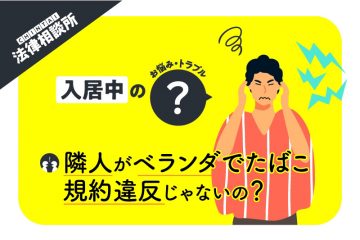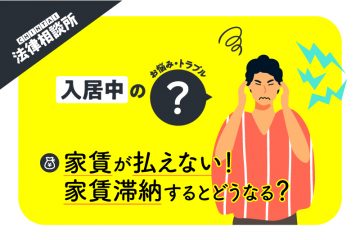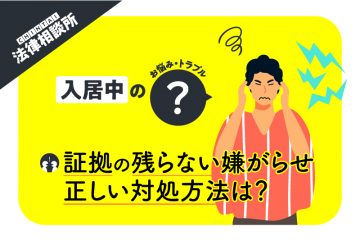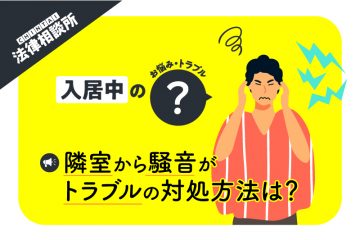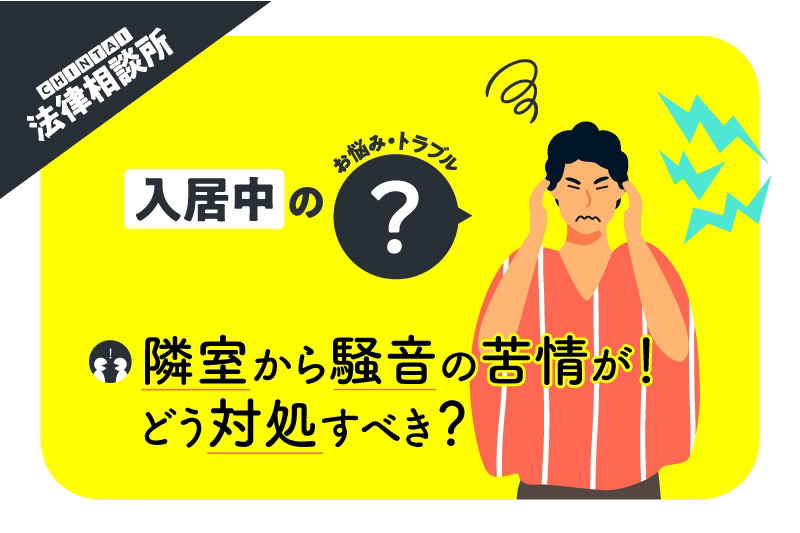
マンションの隣室から騒音で苦情を言われた!どう対処すべき?【CHINTAI法律相談所】
賃貸物件に関する疑問に弁護士がアドバイス
賃貸にまつわるトラブルや疑問について解説する【CHINTAI法律相談所】。
入居前から入居中、退去時まで、さまざまなタイミングで発生しやすい賃貸トラブル。その疑問や対応について、不動産トラブルに強い瀬戸仲男弁護士に聞いた。
賃貸トラブルは、いつ巻き込まれてしまうかわからない。現在トラブルにあっている人だけでなく、これから賃貸物件を借りる予定の人もぜひ参考にしてほしい。
Q.マンションの隣人と騒音トラブル。心当たりがないんだけど、どう対処すべき?
マンションの隣室の住人から「うるさい!」と騒音の苦情を言われた……。ただ、普通に生活しているだけなので心当たりがない。納得いかないが、隣室の住人と揉めたくない。どのように対処するべき?
A.隣人と一緒に騒音を解消できるよう行動しよう
音の感じ方は人それぞれ。自分が普通に生活しているだけでも少なからず音は出るし、人によっては大きく感じる人もいる。自分に非がなかったとしても、同じ建物内で共同生活をしている以上は、話し合って対応することが基本になる。
まずは相手の話を聞いて、騒音を聞いた時間や方角、音の強さや種類などを確認。騒音の原因が特定できたなら、防音材を敷くなり、音を立てないよう生活するなりして対策を講じよう。もし特定できなかったら「また騒音を聞いたら連絡ください」と丁寧に対応すること。納得がいかないからと言って、高圧的な態度や非協力的な対応を取るのはNGだ。
近隣への迷惑行為は「用法遵守義務」違反に該当するので、きちんと対応する必要がある。仮に相手を無視し続けていたらトラブルへと発展する可能性があるし、近隣への迷惑行為とみなされる恐れがある。
用法遵守義務とは、入居者に課せられた「賃貸借契約で定めた用法に従って建物を使用する義務」のこと(民法594条1項、616条)。騒音や迷惑行為について契約書で記載されていなかったとしても、周りに迷惑をかけることは用法遵守義務に反する。自分に非がない場合も、問題解決に努めた方が良いだろう。
「騒音でないこと」を証明するため、証拠を求めるのも手
通常の生活音でも隣人がナイーブなら「騒音だ」と感じてしまうかもしれない。そういった場合は「騒音でないこと」を理解してもらう必要があるだろう。基本的に「受忍限度」を超えない音量であれば、騒音とみなされることは少ない。
受忍限度とは、過去の判例によると「社会生活を営むうえで我慢するべき限度」のこと。各自治体が設けている規制基準が目安となっており、生活音は40~60デシベル程が一般的だ。その音量は下記に該当する。
- 40デシベル:閑静な住宅地の昼
- 50デシベル:静かな事務所の中
- 60デシベル:デパート店内
最近では音のデシベルを調べられるスマホ・アプリもあるので、隣人に測定してもらうと良い。客観的な「騒音の証拠」を求めることは、相手を納得させるためにも、自身の潔白を証明するためにも有効。
特に、相手の苦情が言いがかりに近かった場合は、怯まず要求しておくべきだろう。
もし苦情に対して真摯に対応しているにも関わらず、相手が納得してくれない場合は、第三者に入ってもらおう。今回のような賃貸物件内での問題なら、管理会社に相談するのがベターだ。
ここがポイント!
隣人がナイーブなら、ただの生活音だったとしても騒音トラブルに発展することもあります。納得がいかなくても相手の話に耳を傾け、問題を解決するよう行動しましょう。まずは、同じ賃貸物件で生活する者同士、協力し合うことが大切です。
覚えておきたい法律用語「用法遵守義務」
入居者には用法遵守義務が課せられている。その内容は、民法616条で準用されている594条1項で定義されている。
民法第594条第1項
民法 – e-Gov法令検索
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない
この規定によって、入居者は賃貸借契約に従って生活することだけでなく、目的物の性質=「他の住民に迷惑をかけず共同生活すること」も義務づけられていると考えることができる。
当然、騒音は用法遵守義務に反する。騒音の解消に協力することも「賃貸物件での共同生活」においては必要な行為だ。入居者の義務と捉え、前向きに対応するのが良いだろう。
取材・文=綱島剛(DOCUMENT)
【CHINTAI法律相談所】入居中のトラブルについての記事はこちら!
【CHINTAI法律相談所】隣人のお悩みについての記事はこちら!