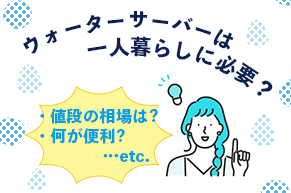床下収納はどう使う?活用方法やメリット・デメリットを解説
このページの目次
キッチンの床下収納はどうやって使えばいいの?

戸建て住宅のキッチンに設置されていることが多い「床下収納」。実は、賃貸物件にも設置されていることがある。賃貸物件のキッチンには、収納場所が少ない場合が多く、床下収納が付いた物件の人気は高い。
今回は、床下収納の活用方法や、メリット・デメリットを解説していく。
床下収納って?
キッチンの床下収納のはじまりは、明治時代にさかのぼる。床下は冷たくて暗いため、お酒やぬか漬けなどの保存に適していた。現在では、主に缶詰や調味料の買い置き、使わないキッチンアイテムなどを収納する場所として活用されている。
建築基準法により、家の床の高さは基礎となる地面から45cm以上と定められているため、床下には広いスペースができることになる。そのスペースを有効利用して作られたのが床下収納だ。
床下収納は、主に、1階のキッチンや洗面台の床などに設置されることが多い。
床下収納の種類を確認しよう!
床下収納は大きく3種類に分類される。それぞれの特徴を見ていこう。
床下収納の種類
・フタの外れるタイプ
・扉タイプ
・スライド収納タイプ
フタが外せるタイプは、物の出し入れが簡単で使いやすく、中の様子もすぐにわかるのが特徴。しかし、収納スペースが広い床下収納の場合、フタが重くなったり数が多くなったりするなど、使い勝手が悪くなってしまう。
扉タイプの床下収納は、収納スペースが広い場合でも使い勝手がよく便利だが、扉が邪魔になり出し入れがしにくいというデメリットがある。
スライド収納タイプは、収納自体がスライドするので1つの扉で複数の収納スペースを確保することができる。しかし、重いものを入れるとスライドしにくくなってしまうため、収納物には注意したい。
床下収納に適しているものって?

せっかく床下収納があっても、何を入れてよいのかわからず、うまく活用できていないという人も多いのではないだろうか。まずは床下収納に適しているものを紹介していこう。
床下収納に適しているもの
床下収納は頻繁に開け閉めするものではないため、賞味期限の短い食品の保存は避けよう。長期間保存ができる、醤油や味噌などをストックしたり、防災用の缶詰やレトルト食品などをまとめて保存したりしておくと安心だ。
床下収納は、湿気が多いため、じゃがいもや人参、玉ねぎなどの根菜類は時期によっては傷んでしまう。保存するなら冬の間がおすすめ。なお、防災グッズを収納する際は、床下収納が耐震補強されているかどうかを確認してみよう。
年に数回しか使用しないような鍋や、テーブルウェアや小物類などの置き場所にも便利であり、さらにガスコンロのストックやコンロなども床下収納に向いている。しかし鍋などの重いものは、運ぶときに落としてしまうこともあるので注意が必要だ。
床下収納のメリット
床下収納にはどのようなメリットがあるのか見ていこう。
床下収納のメリット①:場所を取らずに収納スペースを確保できる
居住スペースの邪魔になることなく収納できるのがメリットだ。特に狭い賃貸物件の場合は収納スペースが限られてくるので、床下に収納できるのはうれしいポイント。
床下収納のメリット②:収納スペースが目立たない
通常収納スペースを確保すると、生活の動線を邪魔してしまいがち。しかし、床下収納は床とほとんど同じであるため、目立たないのがメリット。
床下収納のメリット③:床下点検口として使うこともできる
点検口は、通常床下や天井裏の普段は見えないような場所に異常がないかを点検するためのもの。そのため、床下収納は床下点検口としても使えるので便利。
床下収納のデメリット
とても便利な床下収納だが、デメリットはどのようなものがあるのか見ていこう。
床下収納のデメリット①:床に段差ができる
床下収納の扉は、床と同じようになっていることが多い。しかし、取っ手などの部分で段差ができてしまう。段差部分に溜まったホコリが取りづらいなどのデメリットがあるので、掃除の際は注意しよう。
床下収納のデメリット②:湿気対策・虫対策が必要
床下は季節に応じて温度や湿度が変化する。梅雨時期は特に湿気が多く、カビが発生しやすいので、湿気に弱いものを収納するのは避けた方がよい。また、床下収納の収納スペースは1階部分にあることが多く、時期によっては虫対策も必要だ。
床下収納のデメリット③:出し入れに手間がかかる
床下収納は深型が多く、下の方に収納したものは出しにくいというデメリットがある。また、膝を折って出し入れをしなければならないので、腰痛などに注意が必要だ。そのため、使用頻度の高くないものを収納するとよいだろう。
床下収納を活用するためのポイント5点
床下収納は、ちょっとした工夫でより便利な収納スペースとして活用することができる。ここからは、床下収納で取り出しやすくするための方法や、便利に活用するためのポイントを紹介していく。
床下収納を活用するためのポイント①:上から見やすい収納を心がける
収納ボックスは深型が多いため、ファイル型のボックスなどを使い、上から見たときに一目で何がどこにあるかわかるような収納を心がけるとよいだろう。
床下収納を活用するためのポイント②:取っ手のある入れ物を選ぶ
物の出し入れが不便というのが床下収納のデメリット。しかし、取っ手のある入れ物で収納しておくと、取り出しやすいのでおすすめだ。
床下収納を活用するためのポイント③:湿気対策や定期的な掃除をする
床下収納の湿気対策には、除湿剤や湿気を吸ってくれる新聞紙などを入れておくのがおすすめ。隙間からホコリが入って汚れてしまうことも考えられるため、定期的に掃除をしておくとよいだろう。
床下収納を活用するためのポイント④:ホコリ対策にはフタ付きの入れ物を選ぶ
床下収納は使用する機会が少ないので、溜まったホコリが気になってしまうこともあるだろう。その場合はフタ付きのボックスなどを活用して、しっかりとホコリ対策をしよう。
床下収納を活用するためのポイント⑤:収納したい物の成分や取り扱い方法を事前に確認しておく
床下収納に食品を保存する場合には、密閉容器が便利。しかし、食品によっては密閉容器に保存できないようなものもあるので、事前に成分を確認しよう。スプレーなどの取り扱いが危険なものも、取り扱い方法をしっかり確認する必要がある。
床下収納はDIYできる?
床下収納は便利だが、賃貸物件では勝手にDIYやリフォームを行うことはできない。床に穴を開けてしまうと、退去の際に原状回復費用がかかってしまう。DIYを行いたいと思ったら、必ず事前に大家さんや管理会社へ相談をしてみよう。
床下収納を活用して上手に収納しよう!
床下収納は保存食などを便利に収納できるので、有効に活用するとより快適な生活を送ることができる。湿気対策などを行うことで、収納に関するトラブルも回避できる。床下収納付きの物件に住んでいる人や、これから住みたい人などは、収納のコツを押さえて上手に床下収納をしよう!
関東の人気市区町村から賃貸物件を探す
草加市 豊島区 成田市 浦安市 市川市 荒川区 武蔵野市 戸田市 市原市 日野市
関東の人気沿線から賃貸物件を探す
西武池袋線 南武線 東急目黒線 横浜線 東急田園都市線 武蔵野線 青梅線 みなとみらい線 横須賀線 小田急小田原線