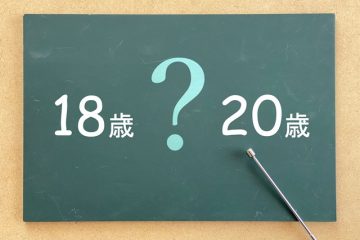成年年齢(成人年齢)が見直し! 18歳のお部屋探しがどう変わったか不動産会社に聞いた
「成年年齢(成人年齢)の引き下げによる賃貸借契約への影響」について調査
賃貸物件や暮らしに関するニュースを深掘り。賃貸ユーザーが知って得する情報をお届けする。
今回は「成年年齢の引き下げ」をピックアップ。成年年齢が18歳になったことで賃貸借契約はどう変わるのか? 気になるポイントを調べた。
このページの目次
【ニュース】成年年齢(成人年齢)の引き下げで民法上18歳の賃貸借契約が可能になった
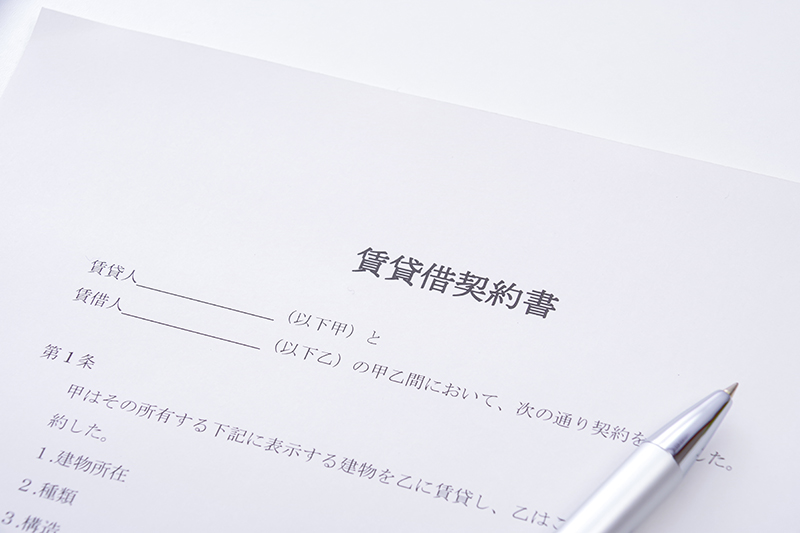
2022年4月1日、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられた。これに伴って18歳でも親の同意を得ず、賃貸借契約を締結できるようになった。
日本では明治9年(1876年)から民法によって20歳が成年と定められていた。しかし、2018年に選挙権などを与えられる年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを受けて、民法も改正。18歳が成年年齢に変更された。
成年とは民法上、父母の親権に服す必要がなくなる年齢のこと。さらに1人で契約をすることができる年齢を意味する。そのため、18歳から親を介さずローンを組んだり、クレジットカードを発行したりと、さまざまな契約が可能となった。一方で、飲酒や喫煙などは青少年保護の観点から、従来通り20歳以上と年齢制限が設けられている。
具体的に18歳になったらできること、20歳にならないとできないことは下記の通りだ。
■18歳になったらできること
- 親の同意を得ずに契約
- 親の同意を得ずに結婚
- 10年有効となるパスポートの取得
- 公認会計士や医師免許などの国家資格の取得
- 性別の取扱い変更の審判(性同一性障がい者の場合)
■20歳にならないとできないこと
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬など公営競技の投票権購入
- 養子の迎え入れ
成年年齢の引き下げで18歳の賃貸借契約に「親の同意書」が必要なくなった
正確に言うと18歳の賃貸借契約自体は以前から可能だったが、未成年なので必ず親権者の同意が必要だった。
もし親権者の同意がなく契約した場合、取り消しを求めたら原則として契約を白紙に戻せる。未成年の法律行為を保護するための権利(未成年者取消)であり、賃貸借契約のトラブルを防ぐために不動産会社は親権者の同意書をもらう手順を設けていた。
それが成年年齢の引き下げで18歳19歳が成年となったため、同意書がなくとも賃貸借契約を結ぶことができるようになる。
【深掘り】成年年齢の引き下げは賃貸物件にどう影響する?

成年年齢の引き下げによって民法上は自由に賃貸借契約ができるようになったが、実際に18歳で賃貸物件を借りるのは可能なのか? 学割制度を設けるなど学生を応援している不動産会社「エイブル」祐天寺店の店長・前田華子さんに話を聞いた。
基本的には、18歳の賃貸借契約は今まで通り親族などの同意を得た上で締結することになると思います。民法で可能になったとはいえ、賃貸借契約では契約者の支払い能力が審査されます。就職していても18歳だと収入が十分ではない場合が多いでしょうから、多くの不動産会社は親族などの承諾を求めると思います。
成年と言っても18歳の多くは経済的に親族などの庇護下にあり、もし家賃を滞納したらその親族などに立て替えてもらうケースが多いはず。そういった実状を加味して、不動産会社は「18歳でも、賃貸借契約は従来どおり親族などの同意を必要とする」可能性が高いと推測できる。
社会人でも18歳の賃貸借契約では親族などの確認が求められる可能性が大
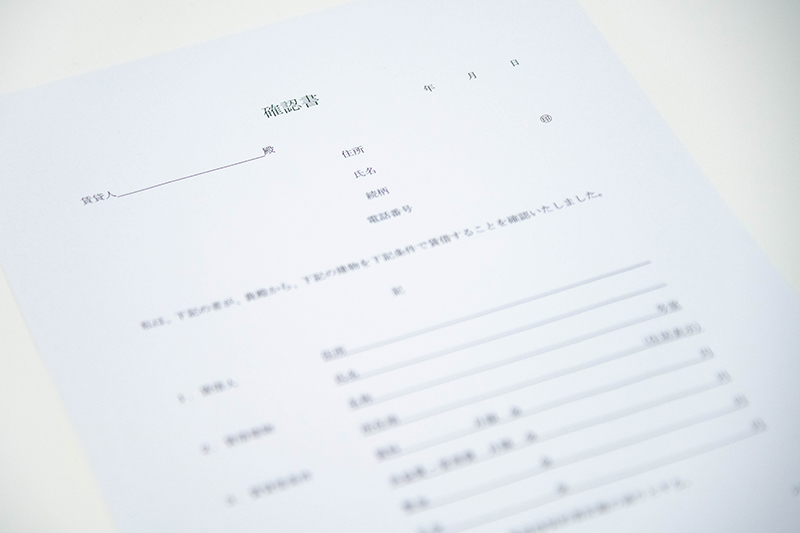
実際エイブルでは20歳以下と賃貸借契約を結ぶ場合、親族などの「確認書」を用意している。これは法的な拘束力を持たないが、原則として賃貸借契約することを事前に親族などが知れるようにしたそうだ。
成年年齢の引き下げによって、さまざまなトラブルが想定されています。例えば、家賃を滞納してから親御さんなどが「初めて賃貸借契約をしていることを知った!」というケースも発生するかもしれません。しかし、成年になると契約は取り消せません。こういった問題を防ぐため、エイブルでは同意書の記載をお願いしています。
これは同社の一例にすぎず、18歳19歳の賃貸借契約は不動産会社によって扱いが異なるだろう。ただ、20歳以下の経済力や契約に関するトラブルを考慮すれば、他の不動産会社も同様に対応する可能性は高いだろう。
【ポイント】18歳19歳のお部屋探しは「誰が契約者となるか」が重要

18歳19歳でお部屋探しをする場合、契約方法は2種類ある。1つは「親族などに同意してもらって自分が契約者となる」方法。もう1つは「親族などが契約者となる」方法だ。後者の場合、事前に入居者が契約者でなく自分であると説明する必要があるが、賃貸借契約上は大きな問題はない。
2つの方法どちらを選ぶかは個人の判断によるが、前田さんは「親族などが契約者となる方がオススメです」と言う。
年齢問わず成年なら、賃貸物件を借りられるかどうかは審査次第。そして、賃貸物件の契約では契約者と入居者が異なっても問題ありません。そうなると信用度がより高い人が契約者となった方が入居審査には有利でしょう。
他にも契約者の違いによって、以下のようなメリットとデメリットがある。
自分が契約者となるメリット・デメリット
独り立ちした証として自分で契約したい人もいるだろう。そういった精神面の利点も見逃せないが、契約面での良し悪しを把握して冷静に判断することが重要だ。
18歳19歳が契約者となるメリット「連帯保証人が立てやすい」
自分が契約者となる場合、親族などに連帯保証人をお願いすることができる。特に両親の場合は年齢的に働き盛りだろうし、同居している場合が多いため頼みやすい。連帯保証人としての信用度が高いのもポイントだ。
18歳19歳が契約者となるデメリット「必要書類を集める手間が大きい」
親族などの同意書だけでなく、賃貸借契約では実印を求められるケースがある。18歳19歳の場合は持っていない場合が大半だろうから印鑑を買って、印鑑登録しなければならない。さらに、管理会社やオーナーによっては親族などの分の収入証明証も提出する必要がある。
親族などが契約者となるメリット・デメリット
親族などが契約者となる場合、契約者の信用度が高くなる。お部屋探しにおいては大きなアドバンテージだ。一方で、デメリットも存在するので、きちんと把握しておこう。
親族などが契約者となるメリット「物件の選択肢が増える」
収入だけでなく職歴や第三者機関の信用情報が加味される可能性があるため、18歳19歳の人より親族などの方が入居審査に通りやすい。つまり、それは選べる賃貸物件が多くなるということ。入居審査で落ちるリスクが下がるので、引っ越しのダンドリが組みやすいのもメリットだ。
親族などが契約者となるデメリット「契約者を変更する際に費用が発生する」
将来的に契約者を親族などから自分名義に変更したい場合、再契約となって初期費用を再度支払うことになる。例えば、大学や専門学校を卒業して新社会人になったら「自分で家賃を払いたい」という人もいるだろう。同じ物件でも、契約者を変える際は費用が発生するので注意が必要だ。
【まとめ】18歳19歳のお部屋探しは親族などに相談することが大切

成年年齢が引き下げられたからといって、18歳19歳が手軽に賃貸借契約できるようになるわけではない。しかし、法的に認められたということは、今後18歳19歳の社会進出が加速していくはず。現状では不動産会社も様子見だが、今後は対応が変わってくるかもしれない。
2023年1〜3月の引っ越しハイシーズンを経て、不動産会社の対応が変わる可能性は十分にあり得ます。また、18歳19歳の方でさまざまな事情により親御さんの同意を得るのが難しい場合でも、物件によっては賃貸借契約を結ぶことが出来るかもしれません。まずは気軽に不動産会社にご相談ください。エイブルも、18歳19歳のみなさまのお部屋探しを全力でサポートいたします。
そもそも18歳19歳なら、ほとんどの人が初めてのお部屋探しだろう。民法上は親の同意なしで賃貸物件を借りられるとしても、お部屋探しについて親族などに相談するのが良いだろう。周囲の意見をよく聞き、“オトナ”な立ち振る舞いをすることが大切だ。
▽お部屋探しを始めたい人はこちらもチェック!
取材・文=綱島剛(DOCUMENT)