「住みたい街ランキング」の街は自分にとって住みやすい?ケース別に押さえるべき条件をご紹介
「住みたい街ランキング」常連の街=住みやすいの?

「住みたい街ランキング」は、アンケート結果を基に発表される多くの引越し世代が住みたいと思う街をランキング形式で紹介したもの。不動産情報サイトなどさまざまな企業・団体が発表しており、「吉祥寺」や「恵比寿」「大宮」などが上位にランクインすることでも知られている。
アクセスや利便性、商業施設の充実度が高い街が多く、住む街を決める判断材料にしている人も多いのではないだろうか。
この記事では、「住みたい街ランキング」から今後住む街を検討しているあなたに、自分にぴったりの住みやすい街を決めるポイントや、引越し前に街をお試しする「試住」について紹介していく。
「住みたい街ランキング」がみんなにとって住みやすい街とは限らない
「住みたい街ランキング」は各社発表しているが、「今後」住んでみたい街や自治体を聞いているものが多いため、憧れに感じやすい街や良く知られている街が上位にあがりやすいともいえる。
たとえば上京するなど、これから住む街を検討する場合に活用しやすい「住みたい街ランキング」だが、「実際に住んでみて良かった街」とはまた別のもの。
特に引越しにおいて重要なのは「あなた自身のライフスタイルに合った街なのか」どうかだ。
「人気の駅に引越してみたが、週末の人混みが苦手で引越した」など、意外なことが原因で住みにくく感じてしまうこともある。
住みやすい街の条件は?確認すべき6つのポイント
住む街を決めるためのポイントを押さえて、自分に合った街探しのヒントにしよう!
街を選ぶ際に検討する条件は「家賃相場が安い」「通勤・通学に便利」「聞いたことがある/行ったことがある」などが思いつきやすい。
条件で絞り込んでいくのは確かに決めやすいが、住む街は、周辺環境が自分のライフスタイルに合っているかどうかも含めて考えることが大切だ。
ここからは基本的なものも含めて、住む街を決めるポイントについて順を追って紹介していこう。
「住みたい街ランキング」などからすでに街を選んだ人にも、ぜひ街の住みやすさの確認に活用してほしい。
住む街を決めるポイント①:交通アクセスが良い

アクセスの良さを重視している人も多いのではないだろうか。
通勤・通学時間や乗り換えの回数、週末出かける街へのアクセスなどを調べてみよう。
意外と見落としやすいのが電車やバスの混雑状況や、乗り換えの利便性。同じ駅での乗り換えのつもりがひと駅近く歩いたり、電車が満員で数本乗れなかったりするなど、実際に見に行ってはじめてわかることもある。
利用する時間帯にその駅を訪れ、通勤・通学ルートを利用してみるのもおすすめだ。
住みやすい街の条件②:家賃相場が自分に合っている

適切な家賃の相場は手取りの3分の1といわれている。この金額を超えてしまうと、毎月の生活費が足りなくなる可能性もあり、場合によっては健康的な生活がおびやかされることも考えられる。
そのため、通勤時間や広さに比べ、家賃は「一番動かせない条件」ともいわれている。
いきなり不動産屋へ駆け込まず、住みたい街のおおよその家賃相場を調べておくと良いだろう。物件を比較するときの参考になる。
数駅移動するだけで金額が下がることも多いので、沿線の駅もあわせてチェックしてみよう。
また、CHINTAIには家賃相場からお部屋を探す機能もあるのでぜひ活用してほしい。
住みやすい街の条件③:周辺環境の利便性が良い

街を決めるときは、どんな商業施設や公共機関があるのかを確認しておこう。
駅前の様子や、毎日の買い物が手軽にできる店が近くにあるかなど実際に足を運んで確認しておくと安心だ。
スーパー、コンビニ、薬局、銀行、郵便局、万が一の場合に利用できそうな病院があるかも調べておきたい。品ぞろえはもちろんだが、スーパーの価格帯もチェックできると生活のイメージもつきやすい。
住みやすい街の条件④:治安が良い

毎日過ごす場所だからこそ、治安も重要なポイントのひとつ。
犯罪の発生数を行政・警察のページなどで確認したり、周りに交番があるかをチェックしたりするのもおすすめ。
また、データ上は安心できそうでも気になるのが人通りや道の明るさ。特に住宅街は昼の間はにぎやかでも夜になると人通りが少なくなりやすい。時間帯によって雰囲気が変わる場合もあるため、夜間の様子だけでも事前に確認しておきたい。
また、路上にポイ捨てが多くないか、放置された自転車がないか等も、その街の治安を判断するポイントのひとつになる。
住みやすい街の条件⑤:大きな音を発する施設がない
住む街を選ぶ際は、騒音についても考慮したい。駅近で利便性の高い場所は、お店や人が多く集まり夜中まで人の声や車の音など大きな音がする可能性は高い。
静かな場所を希望するのであれば、ある程度の利便性には目を瞑り、駅や商店街などから少し離れたところを選んだ方が良いだろう。
また、線路や交通量の多い道路、工場が近くにある場合も騒音に悩まされる可能性があるため、静かに暮らしたいなら避けた方が無難だといえる。
住みやすい街の条件➅:災害リスクが低い
地震や台風、津波など、自然災害時の災害リスクが少ない地域を選びたい。
海抜がマイナスの地域は津波などの被害や河川の氾濫による水害が起こりやすく、埋立地などでは地震の影響による地割れなどの被害を受けやすいエリアといえるだろう。
契約前に地域のハザードマップを確認し、災害が起こりやすい地域かどうか調べておくと安心だ。
住みやすい街の条件➆:街の雰囲気が自分に合っている

自分に合った街を選ぶには街の雰囲気も重要な判断材料になる
抽象的にも感じるが「街の雰囲気」が自分に合っているのかも確認しておきたい。
お部屋探しに訪れたときは、実際に街を歩き、街の様子を見てみよう。生活している自分をイメージして街並みやお店の雰囲気、自然が多いかなどをチェックしてみると良い。
普段のおでかけの際にも「この街はいいな」と感じたら、どういうところが気に入ったのか、どういう要素が苦手なのかを考えてみると住む街選びの参考になりやすい。

重視する条件や好みは人それぞれ。
・個人店の多い街が好き→チェーンの飲食店ばかりの街は合わないかも
・大きな公園のある街が好き→都会すぎると緑を感じづらいかも
・駅前は栄えている方がいい→駅ビルのない地下鉄の駅や、私鉄の小さな駅は合わないかも
上記のように、好きな要素から候補の駅を絞り込める場合もある。
たくさんある場合は、物件選びと同様に、譲れない条件から順番に並べていくと優先度を決めやすい。
【一人暮らし向け】住みやすい街の条件

一人暮らしをする人が住みやすい街はどんな街?
一人暮らしをする人が住みやすい街はどんな街だろうか?生活が不規則になりがちな一人暮らしでは、食事の優先度が高い傾向にある。
一人暮らしをするうえで、重要な2つのポイントを紹介しよう。
一人暮らしが住みやすい街の条件①:深夜まで営業しているスーパーがある
残業や飲み会などで遅くなったときでも、帰り道に遅くまで営業しているスーパーがあると重宝する。
最近は、品ぞろえが良い24時間営業のお店も増えてきた。そういったスーパーが近所にあれば、帰るついでに買い物もできるので、一人暮らしに過ごしやすい街だといえるだろう。
できれば中型店舗以上のスーパーが複数ある街がおすすめだ。
一人暮らしが住みやすい街の条件②:一人でも気軽に入れる飲食店がある
近所に1人で気軽に入れる飲食店がない場合、食事をするのにわざわざ遠くまで出かける必要があったり、コンビニのお弁当等中心の偏った食生活になってしまう可能性がある。。
健康的に過ごすためにも、このような飲食店が近くにあると便利だ。
【子育て世帯向け】住みやすい街の条件

子育て世帯が住みやすい街はどんな街?
それでは、子育て世帯が住みやすい街とは、一体どのような街だろうか?ここではポイントを4つ紹介していく。
子育て世帯が住みやすい街の条件①:子育てを支援する制度が整っている
子育て支援制度の内容は、市区町村ごとにかなりの差があるのをご存じだろうか?
たとえば医療費助成、第2子以降の保育料無償化、幼稚園の入園金の補助など、独自の支援を行っている自治体がある。また金銭的な支援だけではなく、学童保育の充実や子育てコミュニティの運営などを行っている自治体もある。
更に子育てだけではなく、妊娠中の人を対象としたヘルパー派遣制度や出産祝い金の制度など、妊娠・出産に対する支援制度を設けている街もある。各市区町村の支援制度はしっかり調べておきたい。
子育て世帯が住みやすい街の条件②:待機児童数が少ない
共働きの家庭であれば、地域の保育園事情が気になるところ。自治体によっては待機児童が多すぎて、希望する時期に保育園へ入れないこともあるそうだ。
厚生労働省の令和3年4月の待機児童数調査によると、待機児童が50人以上いる自治体は全国に20市区町村あるようだ。引越し先がたまたま待機児童の多い地域だということもある。
街を決める際には、待機児童が少ない地域を選んだ方が良いだろう。また、住みたい物件から毎日通える範囲に保育園があるかも確認しておきたい。地域の保育園事情が知りたければ、市区町村役場にある「子育て支援課」等の窓口で相談してみると良いだろう。
子育て世帯が住みやすい街の条件➂:大きめの公園がある
近くに大きめの公園があることも子育て世帯には住みやすい条件となる。
公園や児童館があれば、子どもを気軽に遊ばせることができ、親同士の親睦を深めることも可能だ。
親は子どもを遊ばせながら、お互いの子育てに対する情報交換ができるため、孤独になりがちな子育ても楽しくできる可能性も高くなる。
子育て世帯が住みやすい街の条件④:夜間診療を行っている病院がある
子どもが小さいうちは、夜間に突然発熱することも多い。
特に1年未満の乳児は、容体が急変することも多く、対応が遅れると命に関わってしまうこともある。そんなときに、夜間診療に対応している病院が家の近くにあれば安心だ。
自分にとって住みやすい街を選ぶためには「試住」がおすすめ
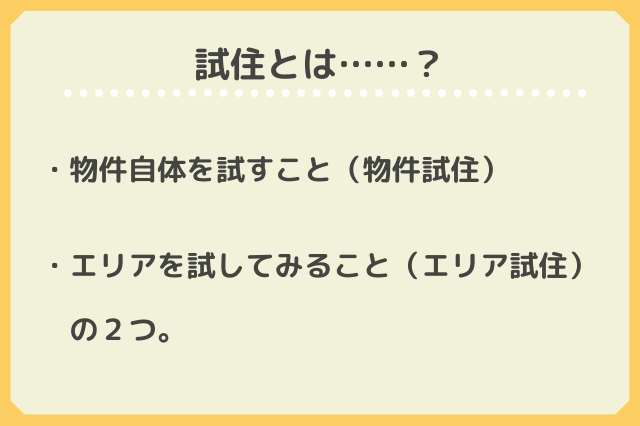
納得して引越し先を決めたい人におすすめなのが街をお試しする「試住(しじゅう)」。その街での暮らしを体験してみることで、その街で暮らすイメージが湧きやすくなる。
「試住」には物件自体を試す「物件試住」と、エリアを試してみる「エリア試住」の2つがある。
通常のお部屋探しの場合、賃貸契約を結ばずに「物件試住」を行うにはハードルがあるため、賃貸物件の場合は「エリア試住」で街を体験してみてほしい。
昨今観光のみならず「テレワーク」や「ホテル暮らし」でも注目されているが、「ホテルステイ」として住みたい街での「エリア試住」も活用できる。

ここまでのポイントで紹介してきた駅や電車の混雑具合、街の雰囲気、治安などネットでは確認しきれない要素も、朝・昼・晩それぞれの時間を過ごしてみることで、より深く体験することができる。
街の候補として確認するだけであれば、一泊二日~二泊三日でも十分なので、週末などの休みを利用するのがおすすめだ。
「住みたい街ランキング」から自分にとって住みやすい街を見つけよう
「住みたい街ランキング」上位の街が、自分にとって必ずしも合うとは限らないが、多くの人から支持されているということは、相応する魅力があるともいえる。
特にこだわりがないのであれば、まずは「住みたい街ランキング」上位の街を引越し候補として調べてみるのも良いだろう。
その際、今回の記事で紹介したようなポイントをふまえ、自分の価値観で判断することが大切だ。しっかりと事前調査することで後悔のない街選びができるだろう。
























